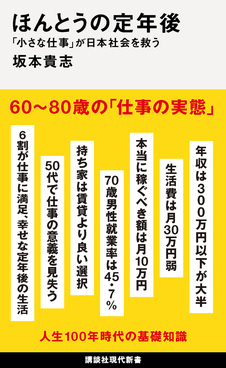「退職金」にはもう頼れない
日本企業独特の慣行と言われる退職給付制度。厚生労働省「就労条件総合調査」によれば、2018年時点で同制度がある企業は80.5%、1,000人以上の企業に限れば92.3%の企業が採用している。
退職給付制度は、退職時に一括していわゆる退職金を給付する「退職一時金制度」と、「確定給付企業年金(DB)」や「確定拠出年金(DC)」など退職後に年金の形で給付する「退職年金制度」で構成される。退職給付制度を持つ企業のうち退職一時金制度のみをもつ企業が73.3%、退職年金制度のみを有する企業が8.6%、両制度を併用している企業が18.1%ある。
同調査では、従業員一人当たりの平均退職給付金額を集計している。それによれば、2003年に2,499万円あった退職給付金額は、2018年には1,788万円と、近年急速に減少している[図表1‒7]。退職金額が減少している背景には、バブル崩壊以降の低金利によって退職積立金が減少していること、などが影響している。
近年、退職金制度を取り巻く状況は大きく変わっている。日本企業では歴史的に給付額が約束されている退職金のみを支払う企業がほとんどであったが、バブル崩壊による低金利などを背景に前払い賃金の性格が強い確定拠出年金への移行が進んでいる。
65歳までの雇用義務化による影響も大きい。企業としては、定年以降も生じる再雇用における人件費の補填のため、退職金を縮小させている側面もあるのだと考えられる。
過去、退職金制度は、従業員の老後の生活の安定を図るとともに、後払い賃金の性格を有し、長期雇用を促進して従業員を自社につなぎとめておく役割があった。
経済が右肩上がりで成長していた時代には従業員にとっても企業にとってもそのメリットは大きかったが、国とともに高齢化する日本企業において、長期雇用を推奨する退職金制度はもはや時代にそぐわないものとなってきている。今後も各企業において退職金制度の縮減・廃止は長期的な趨勢として進んでいくだろう。
増える「早期退職」
一方で、退職金額の推移をみると、2013年から2018年までの間、勤続年数が20~24年では826万円から919万円に、25~29年では1,083万円から1,216万円と、比較的短い期間の勤続年数の社員の退職金が増えている。これは企業が早期退職による退職金額を相対的に増加させているからだとみられる。
過去、リーマンショックによる景況感の悪化に応じて、多くの企業で早期退職が行われたのと同様に、近年、コロナ禍における業況悪化に伴い、早期退職が増える傾向が見て取れる[図表1‐8]。