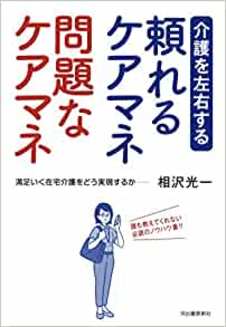親と子の不仲が露わになるケースも多い
■ケアマネのやる気をそぐ要因④…人間性
このタイプの介護者には、介護費用をケチる人がいます。経済的に困窮しているのであれば、それも仕方がありませんが、生活ぶりなどから見て経済的に何の問題もなさそうなのに「このサービスは無駄だ」といってケアプランの見直しを求める人がいるのです。これは前項の「ケアに対する姿勢」にも通じる介護者としてのマイナス要素です。
利用者と介護者、つまり親と子の不仲が露わになるケースもケアマネを困らせます。
「ケア相談を受けているとき、利用者の親御さんと介護者のお子さんがケンカを始めることがあるんです。一応、あいだに入ってなだめますが、対応には苦慮しますよね。どの家にも他人にはうかがい知れない事情がありますし、確執もあるものです。
とくにきつい介護をしているときは感情が爆発しがちなのは我々もわかっています。でも、それは家族間で折り合いをつけてもらわなければならない問題であって、ケアマネはどうすることもできないんです。少なくとも、目の前でケンカをするようなことは避けてほしいですね」
そして、ケアマネがやる気を失う以上に、担当することを避けたいと思わせるのが、介護者が利用者に虐待をしているケース、利用者・介護者にパワハラ、モラハラ、セクハラの言動があるケース、サービスをはじめ何かにつけてクレームをつけてくるケースです。
この場合は担当することになったケアマネのほうが不運。トラブルが絶えませんし、ケアマネ自身が担当を拒否することが多くなります。そして、困難事例として扱われ、経験豊富なケアマネが担当につくことになります。
それでも事態が改善されないと、地域の介護ネットワークのブラックリストに載り、誰も担当しなくなる。介護難民になってしまうのです。
そうしたトラブル・メーカーは、たとえ家族がいたとしても、まともなケアはしてくれないはずです。
そのうえ、ケアマネに見はなされ、ホームヘルパーなどが来なくなったら、食事さえ摂ることができなくなる。行政はそういう人でも放置することはありませんが、生活環境は悪化するばかり。良いことはひとつもないので、その傾向がある利用者・介護者は自省し、言動を慎つつしむしかないのです。
ここまで記したような対応をすると、ケアマネのやる気を失わせてしまう。満足のいく支援をしてくれないダメなケアマネになるのです。
このような対応をしないよう心がけたうえで、ケアマネにはリスペクトして接する、アドバイスを素直に聞き、質問、相談をするなどコミュニケーションを積極的にとる、良好な人間関係(できれば信頼関係までもっていきたい)を築く、前向きな目標を設定し、達成への協力を求める……といった姿勢を見せれば、ケアマネは担当する30人前後の利用者・介護者のなかでも、とくに多くの熱量を注ぎ、満足のいく仕事をしてくれるはずです。
相沢 光一
フリーライター