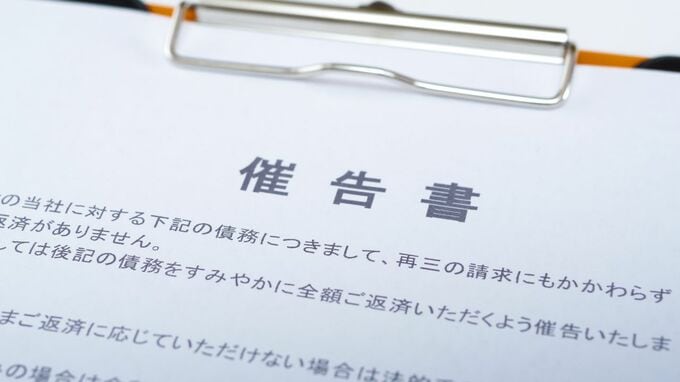相続放棄の申述が認められた判例・認められなかった判例
(3) 熟慮期間の起算点と相続分のないことの証明書
相続分のないことの証明書が作成された場合も、熟慮期間の起算点に関するルールに変更はありません。
もっとも、上述のように、基本となるルールについても解釈論が分かれている状況ですので、特に、相続分のないことの証明書が相続財産である不動産の所有権移転登記をする際に便宜的に作成された場合については、熟慮期間の起算点について慎重に判断しなくてはなりません。
例えば、相続債権者からの訴状の送達の時を熟慮期間の起算点とした裁判例があります(仙台高決平7・4・26家月48・3・58)。
この裁判例では、被相続人の死亡当時、相続分のないことの証明書を作成した相続人は被相続人名義の不動産が存在していたことを認識していた事実が認められました。
その一方で、共同相続人の間では「被相続人の生前から、被相続人名義の不動産の一切を長男〇〇が取得することで合意していたものであって、被相続人の死亡後も、当然にその合意のとおり長男〇〇に権利が移転するものと考え、自らが取得することとなる相続財産は存在しないものと考えていたことが窺える」との事情を認定の上、「被相続人名義であった不動産が相続の対象となる遺産であるとの認識はなかった」とされました。
そして、相続債権者である金融機関からの訴状の送達により、相続分のないことの証明書を作成した相続人は、相続の対象となる被相続人の債務の存在を初めて認識したと認定され、その時点が熟慮期間の起算点だとされたのです。
これに対し、被相続人が死亡した直後に、被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議し、これを長男に単独取得させる旨を合意したケースでは、相続分のないことの証明書が作成されたことを理由に、遅くとも、同証明書の作成日頃までには、被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものとされ、その結果、相続放棄の申述は認められませんでした(東京高決平14・1・16家月55・11・106)。
以上の状況を踏まえると、実務的には、相続分のないことの証明書を作成した相続人が、後日、相続放棄を希望する場合には、個々の事情を踏まえながら、たとえ一部の相続財産に対する認識があったとしても、金融機関からの相続債務の支払請求があった時などを熟慮期間の起算点と考えて、相続放棄の申述を試みる姿勢が必要ではないかと考えます。
なぜなら、相続放棄が認められるか否かに迷っている間に、金融機関からの相続債務の支払請求があった時から3か月が経過してしまえば、たとえ熟慮期間を後らせることができたとしても、相続放棄が認められることはないからです。
(4) あてはめ
本事例の妹は、父が亡くなった当時、被相続人が事業を実施し、当該事業を兄が引き継ぐことを認識していましたので、相続財産の一部の認識があったといえます。昭和59年判決を前提として上述の限定説を採用した場合には、熟慮期間の起算点は、遅くとも相続分のないことの証明書を作成した頃となり、相続放棄の申述は認められそうにありません。
一方で、相続分のないことの証明書を作成した当時、妹が、生前から被相続人の事業を承継するのは兄だと決まっており、遺産分割協議さえも不要であると考えていたような事情がある場合には、金融機関からの請求時が熟慮期間の起算点だと認められる可能性があります。
こうした事情がある場合には、熟慮期間の起算点が後れる可能性に賭けて相続放棄の申述を試みた方がよいでしょう。
〈執筆〉
関一磨(弁護士)
平成29年 弁護士登録(東京弁護士会)
〈編集〉
相川泰男(弁護士)
大畑敦子(弁護士)
横山宗祐(弁護士)
角田智美(弁護士)
山崎岳人(弁護士)