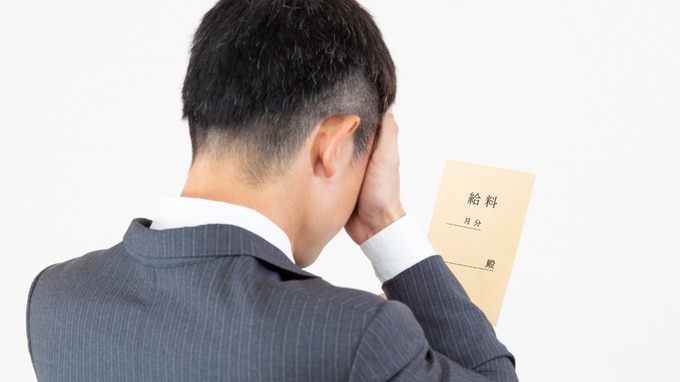賃上げ交渉に消極的な日本の労働組合
ボイスを上げないのは労働者だけではありません。労働組合も近年、賃上げ交渉に対して消極的でした。そもそも、労働組合は組織率が低下、存在感を失いつつあります。労働組合の組織率は1949年の56%をピークに、低下の一途をたどっています。1980年頃には約30%まで低下、2000年代頭に20%を切り、2022年には16.5%となっています。
労働組合の重要な役割は賃金交渉ですが、日本は他国に比べて労働組合の存在感が乏しいのが現状です。リクルートワークス研究所「5カ国リレーション調査」では、賃金決定の重要な要因として「労働組合と使用者の団体交渉」を上げた人の割合は、日本は20%で最も低くなっています。
日本経済が長期停滞する中で、労使交渉において賃金の引き上げよりも雇用の安定を優先することが「公正」とされたことも、賃金が上がらなかった原因のひとつとなっています。
日本の労働組合は企業ごとに存在し、個々の企業の実態に応じた労使交渉ができるというメリットがあります。しかしこれと同時に、企業の存続と利益がなければ、雇用が維持されず、労働組合自体が困る状況が生じます。それゆえ、近年、日本の労働組合は雇用維持を優先し、企業が賃金を上げないことを容認するなど、その役割が低下しています。
このように、賃金に不満があるにもかかわらず、日本では労働者個人あるいは労働組合による賃金交渉が十分に行われておらず、さらには賃金の決定要因を理解していない労働者が3割もいるなど、労働者の賃金の当事者意識が低いことも賃金の低迷につながっていると考えられます。
最近の経済学の研究では、労働者は過去よりも賃金が下がることを嫌う一方で、賃金が下がらない限り、賃金上昇にそれほど執着しない傾向が明らかになっています※。
このような状況では、企業は賃金を一度上げると元に戻せなくなるため、賃上げに慎重になります。さらに、日本では終身雇用制度があり、正社員の解雇が簡単ではないので、賃金を上げた場合、下げることがさらに難しくなると考えられます。
※ 玄田有史編(2017)『人手不足なのになぜ賃金があがらないのか』慶應義塾大学出版会
宮本 弘曉
東京都立大学経済経営学部
教授
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】