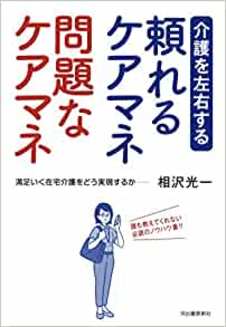【関連記事】押しつけられた親の介護…子どもを追つめる終わりのない絶望感
「知識ゼロの受け身」ではいけない理由
介護者になることは、人生でせいぜい数回です。
実の両親が要介護になったとして2回、お嫁さんが義父・義母のケアもしなければならない場合はプラス2回、配偶者が要介護になる「老老介護」をすることになったらプラス1回、ほかに兄弟や姉妹の、あるいは親が子の介護をする、なんてこともありますが、そんなケースは数少ない。大方は実父、実母の2回ぐらいでしょう。
その両親も、病気や事故によって、突然亡くなった場合は介護を経験することはありません。
また、親が高齢になっても元気でいるうちは、介護をするイメージなど湧かないものです。
「いずれは、そんなことになるかも」と頭をよぎることはあったとしても、具体的に考える気にはなれず、そのままスルー。そうして問題を先送りしているうちに、いつの間にか親の心身の衰えは進行し、要介護状態になっていたりする。介護にかんする知識はほぼゼロの状態から、いきなりケアに追われる日々が始まるわけです。
介護をする人は、肉体的にも精神的にもいっぱいいっぱいの状態になり、介護にかんする詳細な知識を頭に入れる余裕はありません。知識が足りていなければ、ケアマネがつくったケアプランをチェックできず、そのまま受け入れるしかないし、指示にも従わざるをえなくなる。そんなこんなで、介護者の多くはケアマネに対し、及び腰の対応をすることになるのです。
しかし、介護は死期が近づいた肉親の残された日々を良いものにできるか、悪くしてしまうかが問われる重い行為。介護をする人は「自分なりにできる限りのことはした」と思えなければ、後悔にさいなまれることになるのです。
そんな思いをしないためにも、知識ゼロのままケアマネがいうことに従っている受け身の姿勢ではダメ。基本的な知識を身につけたうえで、納得がいかないことがあれば質問し、要望を伝えることもできなければなりません。
また、介護は人間の感情が表れる、けっこう生々しい行為でもあります。局面に応じて、「介護される人」対「介護する人」、あるいは「介護される人と介護する人」対「ケアマネ」といったあいだで、さまざまな腹の探り合いや感情のぶつかり合いが起きるものです。ケアマネとしっかりコミュニケーションをとり、良い仕事をしてもらうためにも、知っておくべきことはたくさんあるのです。
そうした感情面も含めた、介護の始まりから終わりまでの流れを記していきます。