\1月10日(土)-12日(月)限定配信/
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
名義預金=口座名義人と実質的な預金者が異なる預金
相続においてあまりいいイメージのない「名義預金」。名義預金とは「口座名義人と実質的な預金者が異なる預金」をいいます。親が作った子名義の預金などですね。
相続税においては、名義に関わらず、実質的に故人の所有と認められる財産は課税財産として計上しなければなりません。お金を出したのが故人で、実際に口座を管理していたのも故人なのであれば、真の所有者は故人だということになります。これは、資金拠出者、通帳や印鑑等の管理状況、口座が作られた経緯などから総合的にみて判断されます。
税務調査で指摘される申告漏れ財産には名義預金が相当数含まれるとみられ、申告漏れともなれば追徴課税に延滞税などもかかってきます。「何十年も前に作った口座だから時効が成立しているのでは…」とおっしゃる方も多いのですが、名義預金はそもそも贈与が成立していないので、贈与税の時効は適用されません。
ですので、相続税申告を承った際にはそういった口座がないかよくよく確認するのですが、それでも後から発覚することがあります。故人が自分の生活費の余りを少しずつ子名義の口座に貯めていたような場合、税理士が預金移動調査をしてもなかなか気づくことができません。また別の例では、故人が名義預金を元手に株や不動産を購入していたことがありましたが、預金に限らずこれらもすべて名義財産と判断されます。
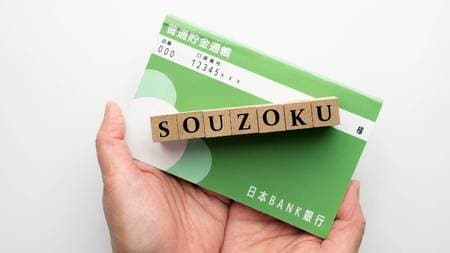
【1月14日(水)開催】地主の方必見!
相続税の「払い過ぎ」を回避する不動産の評価術
葬儀費用等、名義預金が役立つ場面があるのも事実
そんなわけで、申告漏れしやすい要注意財産として扱われがちな名義預金ですが、役に立つ場面もないことはありません。
例えば相続開始直後にお金が必要となる場面です。医療費の精算等のほか、大きな出費は何といっても葬儀費用でしょう。家族葬が増えてきたとはいえ、概ね150~200万円はみておかなければなりません。
この費用を賄うために故人の銀行口座からお金を引き出したいと考える方は多く、名義人の死亡を金融機関が自動的に知る術はないので、暗証番号を知る家族がキャッシュカードを使って預金を下ろすことは事実上不可能ではありません。しかし、故人の口座はあくまで相続開始とともに凍結され、遺産分割が終了するまで引き出せないのが原則です。
一方、名義預金はどうでしょうか。金融機関は税務署のように「実質的な所有者は誰か」とは考えません。口座のお金は名義人が自由に引き出せるのです。仮に残される奥様の名義で名義預金を作っておけば、相続開始後、奥様は口座凍結の気兼ねなくそのお金を当面の生活費や葬儀費にあてることができます。
ただし、きちんと相続財産に計上して相続税申告するのは大前提です。
また、遺産分割上は他の相続人に対してもその存在を明らかにし、名義預金の存在を踏まえた遺言を残すなど、他の相続人から不満が出ないようにしておくべきです。税務署やほかの家族に内緒の名義預金はトラブルの元です。この点は十分ご注意ください。




























