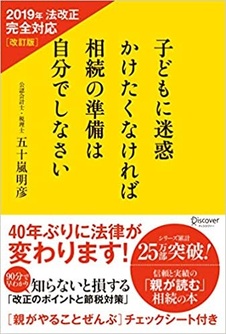日本における一般的な相続財産の内訳は「自宅と多少の預貯金のみ」というケースでしょう。そこで、自宅は分割できないから兄弟で仲良く共有しよう…という安易な選択をすると、あとあと大きなトラブルを引き起こしかねません。争いを避け、相続を無事に乗り切るには、自宅などの「物理的な分割が難しい財産」をいかに平等に相続するかが重要です。※本記事は、税理士法人・社会保険労務士法人タックス・アイズ代表 五十嵐明彦氏の著書『親が元気なうちからはじめる後悔しない相続準備の本』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より一部を抜粋し、被相続人である親自身が取り組むべき相続対策を解説します。
「遺言書には絶対服従」という勘違い
財産が特定できたら、次はいよいよ遺産をどうやって分けるかを決めていきます。遺言書の内容は法定相続分より優先されますから、遺言書があればそのとおりに相続しなければならないと考えられていますが、実は必ずしも100%そうではないことをお伝えしなければなりません。
意外と知られていないのですが、遺言書に書いてある財産を相続する人が法定相続人だけの場合、法定相続人全員の合意があれば、親が書いた遺言と違う分け方で相続することができます。
親が書いた遺言の内容と、みなさんの気持ちが違うこと──たとえば、遺言書には「長男に自宅、二男には預金、三男には株」という遺言があったとしても、みなさんは「長男は預金、二男は株、三男は自宅」が欲しいことってありますよね?
このような場合、みなさんは必ずしも親の遺言にしたがう義務はありません。3人が話し合って合意すれば、自分たちの思いどおりに相続することができるのです。
同じように、遺言書で「兄弟仲良く均等に財産を分けるように」と書かれていたとしても、兄弟間で「長男にすべて相続してほしい」という合意があったら、すべての財産を長男が相続することもできます。自分たちの希望があるなら、相続人間でよく話し合いをするようにしてください。
税理士法人タックス・アイズ 代表社員
公認会計士、税理士、社会保険労務士
明治大学商学部3年在学時に公認会計士試験に合格。その後、監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)に勤務し、国内企業の監査に携わる。2001年には、明治大学特別招聘教授に。
現在は、税理士法人タックス・アイズの代表社員として相続税などの資産税業務など税務業務を中心に幅広い仕事を行う。
著書に『子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載知らないと損!親が元気なうちからはじめる「後悔しない」相続準備