2018年の不動産市場に見る「2つの特徴」
中国経済を見る上で、不動産市場の動向は次の2点から常に大きな注目を集めている。①ミクロ的に、中国の一般の人々の生活上の最も大きな関心が住宅問題であること、②マクロ的には、不動産市場規模がGDPの16.7%(18年実績)、不動産業部門が生み出す付加価値はGDP全体の6.7%(同)だが、鉄鋼、セメントなど関連部門も含めるとGDPの20〜30%に及ぶと見られており(中国中銀証券他推計)、その動向が経済全体を大きく左右するためだ(参考:不動産依存が深刻な中国 住宅の価格と在庫の実態は?)。
●特徴その1…加熱していた市況の沈静化と軟化
第1の特徴は16年から過熱していた市況が18年半ばに至り沈静化し、その後、月を追う毎に市況が軟化したことだ。中国不動産情報サイト「房天下」は18年新築住宅取引面積14.6億㎡、売買金額12兆元、中古住宅は3.95億㎡、売買件数420万棟で、新築と中古を合わせた取引量は17年比ほぼ横ばいで、かつての勢いはなくなったとしている。
中国国家統計局統計でも商品不動産取引面積17.2億㎡(前年比1.3%増)、金額15兆元(同12.2%増)で、17年の各々7.7%増、13.7%増から伸び率が鈍化しており、また不動産業部門の創出した付加価値は3.8%増で、産業部門別で農業の3.6%増に次いで低い伸びだった。国家統計局の主要70都市の新築住宅価格も年後半から前月比マイナスを記録する都市が増え始めた[図表1]。
中古住宅も含む中国指数研究院の百都市価格指数も参考に、景気循環的観点から過去10年間の不動産市場を見ると、09〜15年、平均約3年の周期が2回観察され、現在の周期は15年3月から始まった市況回復→上昇→安定を経て下降の局面にある。すでに約4年経過し、市場では19年下期に市況が底を打つと予測されている。また、同価格指数の上昇率も18年に入ってから月を追う毎に鈍化している[図表2]。
中でもこれまで相対的に上昇率の高かった2、3線級都市と呼ばれる地方都市の上昇率鈍化が著しい。地域別特色としては、長江・珠江デルタ地区周辺の取引が活発な一方、住宅購入抑制策が最も厳しい北京周辺、新たな抑制策を導入した海口(海南省)やこれまで取引が過熱していた成都(四川省)の落ち込みが際立った(参考:再び上昇の兆しが見られる中国大都市の住宅価格)。
●特徴その2…不動産賃貸市場の活況
第2の特徴は、そうした中で不動産賃貸市場が活況を呈したことだ。過去、賃貸市場の未発達が住宅価格高騰の一因になってきたとの認識から、2015年以降、賃借人と住宅購入者の同等権利保障(租售同権)、賃借物件の供給増などの政策的後押しで「租售併挙」、つまり住宅の賃貸と購入を同時に発展させていくとの理念の下、賃貸市場、特に「長租公寓」と呼ばれる長期賃貸マンション市場の育成が進められてきた。長租公寓市場には万科、龍湖、保利、碧桂園といった大手不動産企業を中心にすでに20社以上が参入しており、今やその主要業務領域となっている。
中国の有力市場調査会社「智研咨詢」や賃貸市場情報を提供する「貝殻租房」などによると、18年総人口13.9億人のうち賃貸人口は約2億人、賃貸面積67.33億㎡(19年1月17日付21世紀経済報道によると、賃貸人口は都市部で1.6億人、都市部人口の21%という統計もある)、賃借者は大学を卒業したばかりのホワイトカラーを中心に個人が6割、企業が3割を占める。
特に新1線級都市と呼ばれる重慶、長沙、武漢、成都などの賃貸市場の成約が著しく伸び(各々前年比52%、48%、13%、6%増)、これら都市の賃料はほぼ毎月前年比20〜40%の上昇を記録した[図表3]。
ただ、上海、広州など1線級都市の賃貸料は比較的低い上昇率に止まり、また新1線級でも年後半以降上昇率が鈍化している。また、競争激化で今後参入不動産企業の淘汰が進むとの見方もある(19年1月3日付経済参考報)。
中期的には、住宅購入抑制策、住宅価格の高止まり、持家志向の弱まりといった人々の考え方の変化などから、23年までに賃貸面積は84億㎡、賃貸人口2.48億人にまで拡大すると予測されている。なお、住宅価格の高止まりから購入をあきらめて賃借を続ける者が増加し、各地で賃借人の平均年齢がこれまでの20歳代から18年は30歳半ばにまで上昇した(特に北京、天津、杭州が高く、各々35.6歳、34歳、33.2歳)(参考:地方都市で過熱化 中国「住宅市場」の状況)。
2019年の不動産政策を見る手掛かり
18年末に開催された中央経済工作(活動)会議(毎年、党・政府が年末に開催し、翌年の経済運営の基本方針を決定する重要会議)は「住宅市場の健全な発展に資する長期的・効果的なメカニズム(長効機制)を構築するため、住宅(房)は住むためのものであって、投機(炒)するためのものではない(房住不炒)との考え方を堅持。都市(城)毎の実情を踏まえた政策(因城施策)・分類指導を推進。各地政府の主体的責任を強化する」としている。
これを手掛かりに、中国の不動産業界や専門家は以下の3点を指摘している(18年12月22日付中国新聞網、19年1月31日付環球網他)(なお、2019年全人代も含め、その後の動きについては、追って別稿を発表予定)。
①16年の工作会議で提起された「房住不炒」の考え方が再度強調されている点が注目される[図表4]。多くの都市で価格が調整局面を迎え、さらに米国との貿易戦争など不透明な外部環境下で経済全体への下押し圧力が強まる中で、住宅購入抑制策を見直し不動産市場をてこ入れする動きが出てくるのではないかとの憶測が強まっているが、「房住不炒」が再度強調されたことは、少なくとも抑制策の大幅な見直しや大規模な市場刺激策が導入される可能性は小さいことを示している。他方、工作会議でこれまであった「不動産調控(管理調整)」の文言が消えたことは、抑制策がさらに強化される可能性も小さくなったことを推測させる。
![[図表4]「房炒」を揶揄する中国サイト (注)住宅(房)を鍋に入れて投機(炒)、その結果、庶民は高住宅価格にあえいでいる。 (出所)中国百度百科](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/500/img_ad056fbaf29beb49cc028c720c4fac0633842.jpg)
(注)住宅(房)を鍋に入れて投機(炒)、その結果、庶民は高住宅価格にあえいでいる。
(出所)中国百度百科
②以前は中央政府が各都市に「一刀切」と称される一律の政策を押し付けていたが、「因城施策」の継続が確認され、また、各地政府の主体責任が強調されたことから、各地政府が各々の市場の実情や需給実態を踏まえ、主体的かつ柔軟に政策の微調整を行うことで、市場の過熱や暴落を回避することが期待されている。実際、19年1月に各地で開催された地方両会(全人代と政治協商会議)に提出された地方政府工作報告には、多くの省で「一城一策」の文言が挿入された。具体的には、1線級都市、一部2線級都市の中で、住宅購入頭金比率の引き下げ、住宅金利引き下げといった抑制策の部分的緩和を行う都市がかなり出てくる可能性が高くなった。さらに、これまで使用されていた、中央による「分類調控」という表現が「分類指導」に変わった点も注目される。これらは、中央政府は補助的な役割をするだけで、各地の不動産市場の「調控」主体はあくまで各地政府であり、住宅価格が暴騰または暴落した場合に直接責任を負うのは市長や市党委書記らであることを明確化したものである。
③「長効機制の構築」はこうした会議で常に言及されているが、表現がその都度微妙に変化しており、政策の行方を見る上で重要な手がかりとなる[図表5]。19年1月に党中央委党校で開催された省部級(各省と中央の党・政府各部門)幹部の専門課題検討班での習演説では「長効機制方案を穏当・着実(穏妥)に実施」と「穏妥」という文言が加えられた。これは、これまで価格暴騰を抑えることが不動産政策の主目的だったが、18年後半からの市況軟化とマクロ景気減速を受け、19年は価格暴落とそれが金融全般へ波及するリスクを防止することも視野に入ったことを示唆するもので、「穏」が今後の不動産政策の1つの重要な「旋律」になるとの見方がある。実際、不動産政策を所管する住房城郷建設部(住建部)はすでに18年12月の全国住建工作会議で、地価、住宅価格、将来予想を何れも穏やかなものにするとの「三穏」方針を提起している。またこれを受けて、地方政府工作報告には上記「一城一策」と並び、多くの省で不動産管理政策は「穏」を基軸とするとの文言が挿入された。
また「長効機制の構築」の一環としても位置付けられている賃貸市場育成については、19年1月、国土資源部と住建部が共同で、大都市近郊の農民集団所有用地に賃貸住宅を建設する試行地域を拡大する旨発表(17年に北京、上海、南京、成都、武漢など13都市を試験地として指定、19年1月、新たに福州、南昌、青島、海口、貴陽の5都市にも導入)、また北京市が19年から家賃収入に課す税率を引き下げる(一律5%→月収入10万元未満2.5%、10万元以上4%)などの政策的後押しが続いている。
ただ、工作会議で賃貸市場への明示的言及がなかったことは、賃貸市場が政府主導ではなく市場主導で発展する段階に入ったとの認識を反映しており、19年に直接的な市場育成策がさらに強化されていく可能性は小さくなったとする見方もある(上海易居院智庫研究中心)。
その他、11年に上海と重慶で試験的に導入された不動産税(房産税)を他都市にも導入していくのかという懸案がある。ミクロ的には契約税や住宅購入者に対する所得税など他税との関係も考慮した税制全般の改革の一環として房産税をどう位置付けるのか、地方政府の新たな歳入源として地方政府債務問題を緩和する効果が期待できるか、マクロ的には、特に現下の経済減速傾向の中で、不動産市況への影響をどう見極めるかといった点が焦点となる。
景気減速の中での不動産政策
18年GDP成長率は6.6%と28年ぶりの低い水準で、四半期毎の成長率も6.8%、6.7%、6.5%、6.4%と傾向的に低下した。中国政府シンクタンクの国家信息(情報)中心は19年6.2%、20年6%と「穏中趨降」、つまり穏やかな成長の中で伸び率が傾向的に鈍化すると予測している。
中国政府はすでに18年、預金準備率引き下げや減税などの措置を発動し、19年はさらに景気てこ入れを図る構えだが、08年や12年の景気刺激策が債務膨張や住宅バブルを招いた教訓から、李克強首相ら指導部はその後、「大水漫灌(ばらまき、本来は農業の灌漑方式を指す表現)」、「飲鴆止渇(後先を考えない急場しのぎ、直接的には毒を持った鳥である鴆の羽を浸した毒酒を飲んで渇きを癒すという意味)」的な政策は採るべきでないと繰り返し述べている(例えば、最近では19年2月20日国務院常務会議、3月全人代政府活動報告で李首相発言)。
中国当局にとって、19年経済政策は「高レバレッジ(高債務依存)からの脱却(去杠杆)」と「レバレッジ強化(加杠杆)」という相矛盾する政策目的を追求しなければならない局面となる。その中で、不動産政策については、中国では景気刺激のためには減税や消費刺激策だけでは不十分で、不動産市場に頼らざるを得ないという認識が根強くあり、一部地方政府が住宅購入抑制策を緩和する動きに出てくることは十分予想されるが、全国的に大きな政策転換をすることには中央政府が躊躇する可能性が高い。そうすると、住宅価格上昇の勢いは削がれ、場合によっては下落し、成長率に下方圧力をかける要因となる。
しかしそもそも、不動産価格上昇に支えられた経済成長は「部分均衡的考え」「虚假(見せかけ)繁栄」でしかなく、むしろ以下の点から、中長期的には経済成長にマイナスの影響をもたらしているとの認識が中国の専門家の間からも出始めている(例えば、18年8月22日付経済参考報に掲載された中央財経大学経済学院長論考)。すなわち、
①企業はイノベーションのための研究開発より高収益を生む不動産投資に走り、個人は住宅購入資金を蓄えるため、リスクを伴うベンチャー企業の創業を避けて安定収入に頼る傾向が強まり、社会全体としてイノベーション創出能力が抑圧されている。
②不動産価格上昇で潤う不動産業、その関連産業である鉄鋼、セメントなどの相対的に生産性が低い部門に様々な資源が向かう結果、産業構造の高度化、資源の再配置による生産性向上が進まなくなっている。かつては製造業の生産性向上の50%は生産性の低い産業から高い産業への資源再配置によってもたらされていたが、04年以降、不動産価格上昇で資源再配置の生産性向上に対する貢献率は大きく低下し、グローバル金融危機以降はほぼゼロとの推計もある。
③直接的には企業の土地建物にかかる固定費用が上昇し、また個人の生活費上昇が賃金を押し上げる要因として働き、全体として企業の生産コストが上昇する結果、企業ひいては国の国際競争力が低下している。最近の研究結果では、04年以降、中国と先進国の賃金格差が急速に縮小したが、これは人口構造の変化というより不動産価格上昇によるところが大という指摘だ。
車の運転手は時に、アクセルとブレーキを使い分けながら複雑な道路をうまく走行する。それと同様に、中国当局は「去杠杆」と「加杠杆」という一見相矛盾する経済操作を通じて、短期的には急激な景気減速を避けつつ、中期的に経済をより質の高い発展段階に導いていけるのか。当面の経済政策、特に不動産政策の注目点だ。

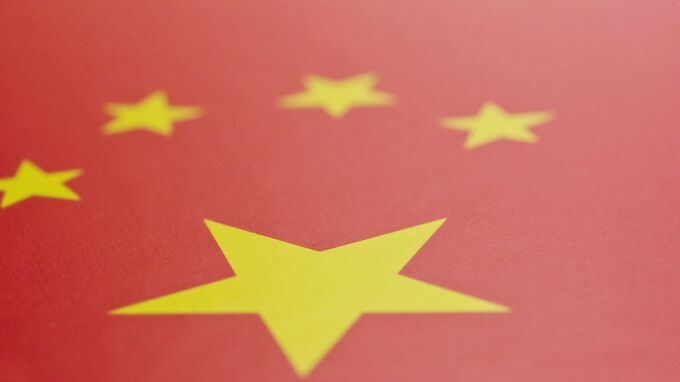
![[図表1]新築商品住宅価格(前月比) (注)保障性住宅を含まない。 (資料)中国国家統計局「70大中城市住宅販売価格変動状況」より筆者作成](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/640/img_71b1e863a69a74bfe3b6069968818d1868673.jpg)
![[図表2]百都市価格指数 (注)新築住宅と中古住宅を含む。 (出所)房天下産業網等より筆者作成](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/e/c/640/img_ec7f3291720aa1d96f5a443f39bf4d2c143793.jpg)
![[図表3]都市部家賃の推移 (出所)城市房産排行榜より筆者作成](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/5/4/640/img_549e22957e64b28a15ae3f8f5368bd35103221.jpg)
![[図表5]微妙に変わる「長効機制」への言及 (出所)券商中国報道](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/9/9/640/img_99a5aee43a88d282140565defe9853ae119033.jpg)





























