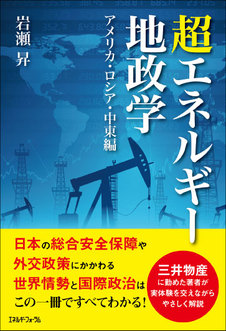1971年、栄華の頂点にいたイラン皇帝シャーだが…
前回はサウジアラビアの歴史を説明した。かたやイランの歴史はどうか。
1971年10月、イラン南西部の街シラーズ郊外のペルセポリスで世紀の大祝宴が開催された。
イラン皇帝シャーが、キュロス二世によるアケメネス朝ペルシャ帝国の建国2500年を祝い、自らを「キュロス大王の後継者、神に選ばれた王」であることを内外に宣言したのだった。
世界各地から国王、首長を20人、女王5人、大統領14人、副大統領3人など各国のリーダーを600人以上招き、本店を2週間休業してシェフをはじめ165人のスタッフを送り込んだレストラン「マキシム・ド・パリ」による豪華絢爛たる食事でもてなした。1959年産のドン・ペリニョンで乾杯したあとは2万5000本のフレンチワインが来賓を満足せしめた。なお、日本からは三笠宮殿下御夫妻が参加されていた。
石油収入が20億ドル程度の年に、1億ドルとも2億ドルともいわれる費用を費やしたこの世紀の大響宴の会場は、2000年以上も放置されていたアケメネス朝ペルシャ帝国の首都ペレスポリスの地に、パリのデザイン会社が設計・デザインし、新たに設営したものだ。中央には大噴水を配置、周囲には植林を施し、一見、緑の大地の真っ只中に見えた。そして来訪者をもてなすため、プレハブ住宅を黄金のテントで包み込んだ「テントシティ」が設えられたのだった。
招待されたものの、イギリスのエリザベス女王やアメリカのニクソン大統領、フランスのポンピドー大統領が欠席し、それぞれ代理を送り込んだところに微妙な国際的な力関係が垣間見られるが、折から石油需給がタイト化しており、OPECが攻勢を強めている中での式典であり、シャーにとっても栄華の頂点にそそり立ったときだった。
イラン・イスラム革命によりエジプトで客死
シャーには、万感胸に迫るものがあったことだろう。なぜなら、自らは22歳のときにイギリスにより祭り上げられた傀儡の皇帝としてスタートしたからだ。
コサック兵だった父レザー・ハーンが、第一次世界大戦直後の1921年にクーデターを起こしてカジャール朝を倒し、自らが皇帝に即位してパーレビ朝を興したのが1925年。だが、第二次世界大戦が始まると、第一次世界大戦のときと同じように、北からソ連が、南からイギリスが進駐し、南北を分け合うように占領されてしまった。
さらにイギリス政府は1941年、イギリスやソ連に対抗すべくナチス・ドイツに靡いていた皇帝レザー・ハーンを退位させ、まだ若く、経験不足で気弱な、22歳のムハンマド・レザー・シャーを皇帝に祭り上げたのだった。
あれから30年。石油がシャーに力を与えていた。
第三次中東戦争の翌年、1968年にイギリスが3年後の「スエズ以東」からの撤退を宣言し、ペルシャ湾内のイギリス保護領であったバーレーンやカタール、オマーン、アラブ首長国連邦(UAE)が1971年に相次いで独立した。
イギリス撤退により空白が生じたペルシャ湾に共産ソ連が南下するのを恐れたアメリカは、サウジとともにイランを自らの地域「代理人」とする「二柱政策(Twin Pillars Policy)」を打ち出し、イランのシャーに「ペルシャ湾の憲兵」としての役割を期待し、応分の支援を行っていた。
さらに1973年のオイルショックにより石油収入は激増した。
シャーは自らの力を過信していた。そして1979年1月、イラン・イスラム革命によりシャーは亡命を余儀なくされ、翌1980年8月、エジプトで失意のうちに客死した。
パリから凱旋帰国したホメイニ師は「最高指導者」に
1979年2月にパリから凱旋帰国したイラン・イスラム革命の父ホメイニ師は、「ヴェラーヤテ・ファギーフ(法学者の統治)」を確立し、「最高指導者」となった。
「イスラム革命の輸出」を唱導したが、イラクのフセイン政権に攻め込まれ、8年に及ぶイラン・イラク戦争を戦うこととなった。戦争終結の翌年の1989年にホメイニ師が逝去すると、「イスラム革命輸出」の声は表向き小さくなった。だが、イラン国内では、1979年から40年近くになる今日も「最高指導者」による統治の絶対性は崩されていない。
イラン・イスラム革命後に生まれた国民の数は7割を超えている。現在の統治スタイルとなった以降に生まれた人がもはや圧倒的多数派なのだ。
焦点は、ホメイニ師のあとを継いだハメネイ師(1939年7月生まれ)の後継者として、新しい「最高指導者」に誰がなるのか、という点に移っている。2017年5月、2期目の当選を果たしたロウハニ大統領が任期を終える2021年までにハメネイ師が逝去された場合、ロウハニ師があとを継ぐのであろうか。
あるいは2018年5月、アメリカのトランプ大統領がイランとの「核合意」から離脱して「体制変更(レジームチェンジ)」を要求し始めたことが影響して、保守強硬派路線の「最高指導者」が出現するのだろうか。
このような歴史を踏まえ将来を予測すると、サウジもイランも、現行の統治体制は近い将来、大きな修正を余儀なくされるとみるのが妥当だろう。
「人口増」がサウジを脱石油に駆り立てる
結論をいえば、サウジは、人口増の圧力から、「揺りかごから墓場まで」の「家産制福祉国家」を維持することはできないと思われる。国民にこれまでと同じ満足を与えられるだけの石油収入の伸びを期待できず、代替の収入源確保も容易ではないからだ。
パリ協定に代表される地球温暖化への政策的対応と、シェール革命による非在来型石油生産の拡大により、かつての「ピーク・オイル論」は姿を消した。世の中に存在するものはいつかなくなる、とのわかりやすい考え方にも裏打ちされて、石油供給が近い将来「ピーク」を迎えるという「ピーク・オイル論」は長い間、支持されていた。
だが、今では「新ピーク・オイル論」、すなわち「供給」よりも先に「需要」が「ピーク」を迎えるという考え方が定説となっている。したがって、100ドル時代の再来と、そのあと再び右肩上がりで上昇することは望むべくもなくなっている。
価格は上がらず、需要が近い将来「ピーク」を迎えるとすれば、石油収入に頼った国家運営ができなくなるのは明らかだ。
このような状況下、彗星のように権力の中央に躍り出たサウジのムハンマド・ビン・サルマーン副皇太子(当時)は、脱石油経済体制への脱却を目指す「サウジアラビアビジョン2030(以下、「ビジョン2030」)」を2016年4月に発表した。
脱石油は、過去にも石油価格が下落するたびに、何度となく政府方針として謳われた。だが、石油価格が上昇すると、いつも忘れ去れてきた。
だが、今回は第三世代(イブン・サウド初代国王の孫世代)の表舞台への登場によって打ち出されたところに新味がある。従来の「王族長老によるコンセンサス統治」を脱却しようとしているだけに、今回は過去とは違う、というわけだ。
今回はうまくゆくのだろうか。
次回は、まずサウジの現況を紹介しておこう。