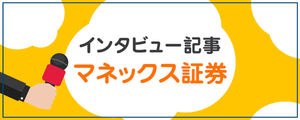できるかどうかではなく、教えることが大事
マナーというと堅苦しいイメージだったり、子どもに教えても意味がないのではないかと思われたりするかもしれませんが、幼少期に学ぶことはその後の人生に大きく影響します。
ちゃんとできるかどうかは関係なく、小さいうちからマナーに触れることで、人付き合いが上手になっていきます。
あいさつはコミュニケーションの基本
あいさつは、一番に身に付けたいマナーです。たとえば絵の才能が豊かな小学生がいたとします。でも、学校で一言も話さず、ずっと教室の隅っこで絵を描いてたら、今の時代は「変なやつ」だと思われて、いじめられてしまうかもしれません。
しかし、同じ行動をしても、「おはよう」と笑顔で元気にいえるだけで、才能を才能としてまわりから認めてもらえるのです。
会話のキャッチボールができることがコミュニケーションの基本です。そこで返事がないと「相手はどんな気持ちになるか」というところから教え、本人に気づかせることが重要です。たとえ小さな声だったとしても、少しでもできたらちゃんとほめてあげましょう。
「子どもは小さな人間」として尊重する
子どもに教えようとすると、どうしても上から言うような形になるかもしれませんが、「子どもは小さな人間」というのが前提です。上とか下という意識をもたず、横並びの気持ちで「友達に話すように」伝えることが肝心です。
また、子どもがきれいな言葉使いで話せるようにするには、正確な敬語はともかく、丁寧語に慣れさせることです。朝起きたら「おはようございます」、夜は「おやすみなさい」、そして「忘れ物ないですか」など、丁寧な日常会話に慣れさせることで、きれいな言葉遣いができる子に育っていきます。
座って食事ができないときは
食事の悩みで多いのが、じっと座っていられず、うろちょろと立ち歩いてしまう場合です。対策としては、食事は最初から取り分けて個別に盛ること、そして食事の時間を何時までと決めることです。その子が食べるペースを考慮して、「長い針が6になるまでね」などと決め、その時間になったら食べ終わっていなくても、食事を下げてしまうのです。
厳しいようですが、時間が過ぎたら食べ物は与えないようにしてください。ダラダラして食べずにいると下げられてしまうとわかったら、ちゃんと時間内に完食できるようになります。ただし、食べられないのはお腹が空いていないことが原因の場合もありますから、食事の前におやつを与えるのは控えましょう。
また食べ物の好き嫌いがある場合には、食べることは「命をいただくこと」だと教えることです。食べ物には育ててくれた人、作ってくれた人がいることを伝え、思いやりの気持ちを持たせることから始めましょう。
箸の使い方をどう教えるか
箸の使い方も多くの人が悩むところです。上手な持ち方は大人になってからでも直すことができますから、子どものうちは持ち方よりも、やってはいけないお箸の動作、「嫌い箸」について教えることが大事です。
たとえば、おわんを叩く「叩き箸」、食べ物を刺す「刺し箸」、食器をお箸で食器を寄せる「寄せ箸」などさまざまなものがありますが、箸のタブーは一緒に食べている人を不快にさせてしまうこともありますから、早めに教えましょう。
自分のことは自分でできる子に
日常生活の中で、身のまわりを整理整頓する、着替えをする、脱いだ服を洗濯かごに入れるなど、子どもにできることはたくさんあります。マナーやルールは、子どもが生きていくためのもので、「自分のことは自分でする」というのが基本です。
ですから、「自立」こそがキッズマナーのゴールといえるでしょう。子ども扱いをせず、何事も自分でやらせること。たとえば電気のボタンに手が届かないなら、かわりにやってあげるのではなく、どうやったらできるかを教えるのです。
無人島に放り出されても生きていけるような、物事を自分で考えることのできる強い子に育てることが、他の誰でもなく本人のためになるのです。