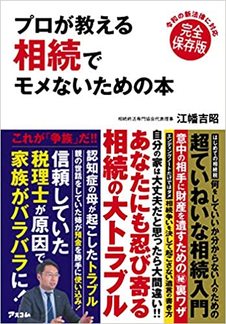遺言能力の曖昧になった母とともに「争族」スタート
初江は、都内の自宅で一人暮らしをしていた。しかし、和美、太一、良次、佳美の4人の子どもたちが近くに住んでいたので、毎年正月には彼らが訪れ、家族の交流が途切れることはなかった。
ある年の正月、和美、良次、佳美の一家は実家を訪れたが、長男の太一は顔を出せなかった。年末年始の仕事でトラブルが発生したからだ。トラブルの内容は、経理担当者による使い込みの発覚だったが、その責任は経理部長兼常務の良次(次男)にあったと、社長の太一が裁定した。
ここで兄弟の仲に亀裂が入ってしまう。正月の挨拶(あいさつ)を巡るすれ違い、初江の老化、そして社内のいざこざが重なる中、和美(長女)のもとに冒頭の電話がかかってきた――というわけだ。
もともと和美たちは、自分たちが財産をもらえるなどと思っていなかった。既に述べたとおり、初江は、「太一にすべてを相続させる」と宣言していたからだ。ところが、初江が「太一に騙されている」と言い出したことで、自分たちにも財産をもらえる芽が出てきた。兄弟みんなに「もらえるものはもらっておけ」という欲がわき上がってきたのだ。
太一は明らかな濡れ衣である。しかし、「遺言を偽造した長男」を、初江が忌み嫌いはじめた。初江が新しい遺言を作成すると言い出したために、「長女・次男・次女」グループと「長男」グループに分かれて「争族」の火蓋(ひぶた)が切って落とされた。
和美グループが主導し、寝たきりの母の元に公証人を呼び寄せる。口述筆記で母の公正証書遺言を作成させるためだ。かくして、すべてを長女と次男と次女に相続させる公正証書遺言が完成した。このとき初江の判断力が正常であったかどうか、もはや検証するすべはない。
遺言は日付が新しい方が優先される。この時点で、10年前に書いた自筆証書遺言は無効となった。太一は途方に暮れた。初江から一方的に嫌われ、自宅に入ることも許されず、公正証書遺言についても一切知らされなかった。