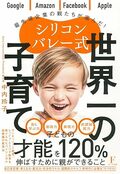成長し続けたアメリカ・中国、停滞していた日本
この30年間は、ちょうど平成の30年間にあたります。この間、日本にいったい何が起きたのでしょうか。もちろん日本の企業も、この30年もの間になんの努力もしなかったわけではありません。日本が世界の市場で戦えなくなったのは、アメリカや中国などの急速な成長に追いつけなかったからなのです。それは、国の経済力を示すGDP(国内総生産)にはっきりとあらわれています。
日本は長年、世界のGDPのランキングでアメリカに次いで2位をキープしていましたが、2010年頃には中国に抜かれ、3位になりました。2019年のGDPは、アメリカは21.4兆ドル、中国は14.3兆ドル、日本は5兆ドル(ドル換算)で、上位2か国と日本の間には大きな差があります。
実は、1995年の日本のGDPは5.4兆ドルでした。つまり、日本のGDPはこの25年間、ほとんど変わっていないということです。日本の産業そのものが衰退したわけではなくても、ほかの国が成長するなかで停滞していれば、相対的に日本は後退することになってしまいます。そして、世界における国の力が弱まれば、それは国の技術力や文化の遅れ、教育の遅れにもつながります。
日本人には高い技術力も知識もある。難問にぶつかっても挑み続ける粘り強さもある。日本の製品は、その性能の高さで世界から信頼も得ている。それなのに、なぜ日本企業は世界トップの市場で戦えなくなってしまったのでしょうか。なぜ、日本にはアップルやグーグルのような、イノベーションを起こす企業がこの30年間に生まれなかったのでしょうか。
シリコンバレーの企業がどのようにして世界をリードするようになったのか、そして何が日本に足りなかったのかを振り返りながら、その答えを探ってみましょう。
日本ではアップルやグーグルが生まれていない
私が住むシリコンバレーは、カリフォルニア州北部のサンフランシスコから車で45分ほど南に下ったところにある地域です。コンピュータの部品である半導体の産業がさかんだったことから、半導体の原料である「シリコン(silicon)」と「谷(valley)」と呼ばれる盆地の地形を合わせて、「シリコンバレー」と呼ばれるようになりました。
シリコンバレーには、GAFA(IT業界のトップに君臨する巨大企業の頭文字をとった略称)と呼ばれるグーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルのほか、ツイッターやインスタグラム、マイクロソフトやヤフーなど、誰もが知る世界的企業が集まっています。また、ライドシェアや日本でも普及しつつあるウーバー・イーツなどのサービスを生み
出したウーバー、自動運転車の産業をリードするテスラなど、今まさに世界を変えている企業もシリコンバレーで誕生しました。
これらの企業は、多くが数人のスタートアップから始まっていますが、それまでにない製品やサービスによって世界を一変させる「イノベーション(革新)」を起こすことで、巨大企業へと成長を遂げています。
もう一つ、シリコンバレーに欠かせない存在となっているのが、スタンフォード大学です。スタンフォード大学は、グーグルの共同創業者であるラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンなど、多くの優れた人材を輩出しました。大学での研究と周辺企業の技術開発を結びつける「産学連携」を行うことで、シリコンバレーの発展とともに成長し、今では世界の大学ランキングで第2位(2020年9月現在)にランクインしています。
世の中を一変するような製品やサービスを生み出す企業群と、それを支える頭脳であるスタンフォード大学。この環境が数々のイノベーションを生み出し、シリコンバレーは「イノベーションの聖地」とも呼ばれています。