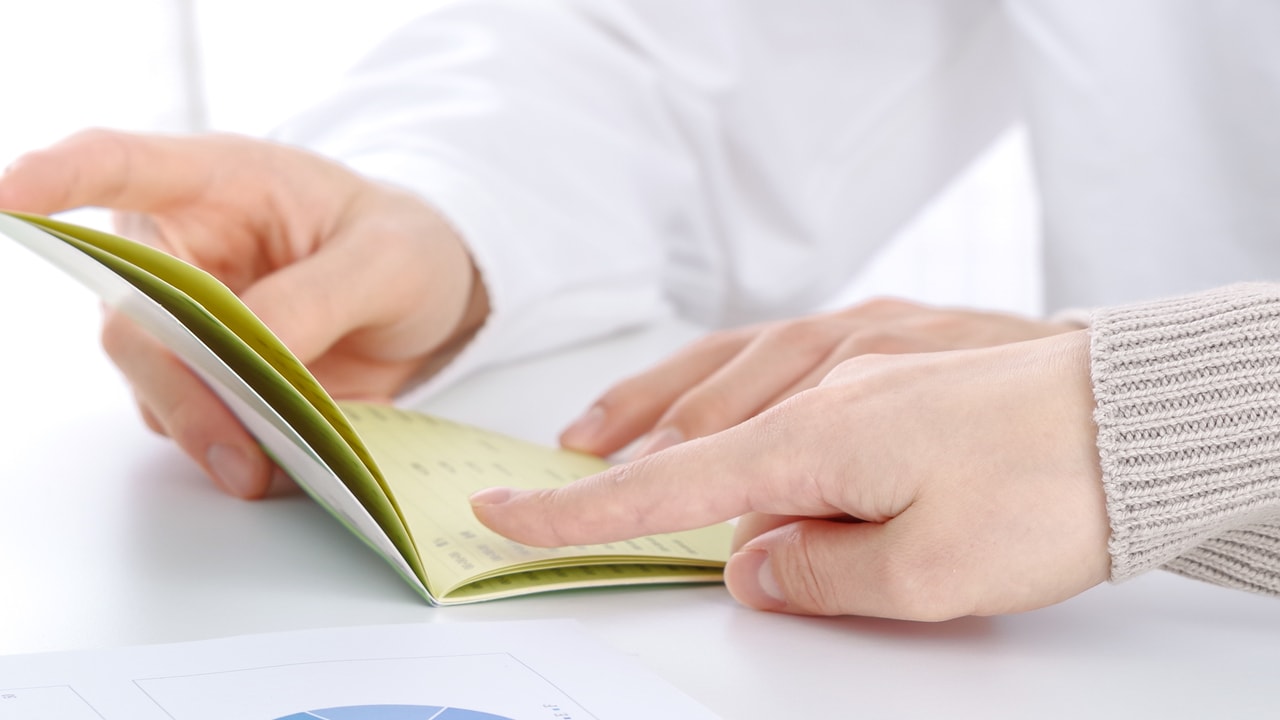 (※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
高収入世帯でも苦しい家計、奨学金が重くのしかかる現実
都内に暮らすAさん夫妻(40代)は、大学生の長男と中学生の長女がいる4人家族だ。共働きで世帯年収は約900万円。一般的には“高収入世帯”に分類されるだろう。しかし都内暮らしでこの収入状況は、家計が楽とはいえない。15年前に購入したマンションの住宅ローン。2人の子供の将来を見据え、中学から私立学校へ通わせるための教育費。Aさんのこれまでの経験から、私立への進学は将来2人が都内で生活していくうえで必要な進路と考えている。
これらに伴い塾代などの教育費も想定以上に膨らんだ。長男の大学入学にかかる初期費用は、貯蓄でなんとか対応できそうだが、長女の進学も控えており、すべてを使い切るわけにはいかない。そこで、長男には給付型の奨学金を受けてもらおうと考えた。
しかし、年収が高いために日本学生支援機構(文部科学省が所管する独立行政法人)の給付型奨学金の対象外となった。貸与型の奨学金の場合、将来的に子供が返済義務を負うことになるため、夫妻は民間の給付型奨学金にも積極的に応募したが、いずれも不採用。「年収は関係ないと謳っていても、実際には年収順に選考しているのではないかと感じざるを得ませんでした」とAさんは語る。
親の「見た目の年収」が子供の未来を左右する不条理
結局、Aさんの長男は有利子の貸与型奨学金を利用することになった。経済的に恵まれているはずの家庭環境が、子供に多額の借金を背負わせるという皮肉な結果を招いた。
「子供に経済的な負担を強いることになり、親として申し訳ない気持ちでいっぱいです」Aさんの妻は打ち明ける。子育て世帯にとって、住居費や教育費に加え、習いごとや同世代との交際にかかる費用、日々の生活費は大きな負担となる。たとえ年収が高くても、自由に使えるお金が潤沢とは限らない。
Aさん夫妻の月の手取りは約65万円であり、さまざまな支払いを済ませたあとの残額は数万円程度に留まるという。このように、見た目の「高収入」と、実際の可処分所得や生活余力は必ずしも一致しないのが現実だ。









