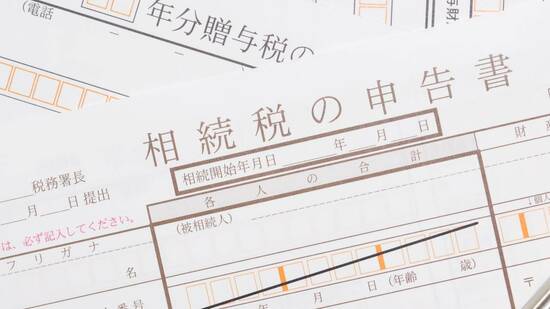相続税の申告件数が増加
国税庁が令和6年12月に公表した「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると、令和5年分において亡くなった人のなかで、相続税申告書を提出した人は15万5,740人、割合でいうと9.9%となっています。約10人に1人が相続税申告書を提出している計算になります。
相続税の申告者は、平成26年には56,239人だったのが、平成27年には10万3,043人に倍増。その後も増加し続け、令和5年には前述のとおり15万5,740人に達しました。
相続税の課税件数が増加している主な要因は、高齢化による死亡者数の増加に加えて、不動産価格(地価)や株式市場の上昇によって、相続財産の評価額が高くなったことが挙げられます。具体的には、都市部を中心に土地の価格が上昇し続けていることや、株式市場が好調で保有株の価値が増加していることにより、これまで相続税の対象にならなかった人でも課税対象となるケースが増えてきています。
なかでも地価の上昇は顕著で、令和7年3月に国土交通省が発表した「地価公示」によると、地価は4年連続で上昇しており、昨年よりその上昇率が拡大しています。
これは景気が緩やかに回復していることや海外からのマネーや人の流れ込みが大きな影響を与えているとされています。地価の上昇は三大都市圏のみならず、全国的に波及しています。
また令和6年より相続税と贈与税の一体化が行われ、たとえば生前贈与の加算期間が従来の『相続開始前3年』から『相続開始前7年』に延長されました。これにより、生前に行った贈与も相続財産としてより長い期間さかのぼって課税対象となるようになり、結果として相続税の課税対象となるケースが増加することになります。
また『相続時精算課税』についても、令和6年1月以降は『年110万円の基礎控除』が新設され、より利用しやすくなった一方で、この制度を使った贈与分はすべて相続時に合算して課税されるため、思ったより課税対象となる財産が多くなり、課税対象者が増える要因となります。これらの改正は、生前贈与による節税効果を縮小させ、より多くの人が相続税の申告や納税義務を負うことにつながっています。
さらにタワマン節税を防止する対策として、令和6年よりほとんどのマンションの評価額が引き上げられることとなり、相続税の課税対象者は今後さらに増える見込みです。
株式会社エールが販売する不動産小口化商品「eLShare(エルシェア)」
詳細パンフレットを無料プレゼント中!
申込はこちら≫