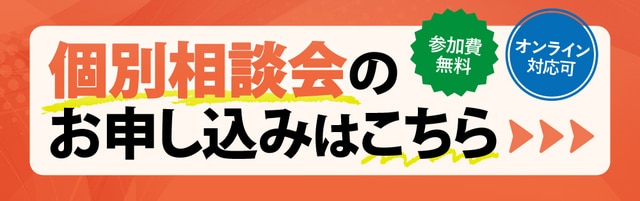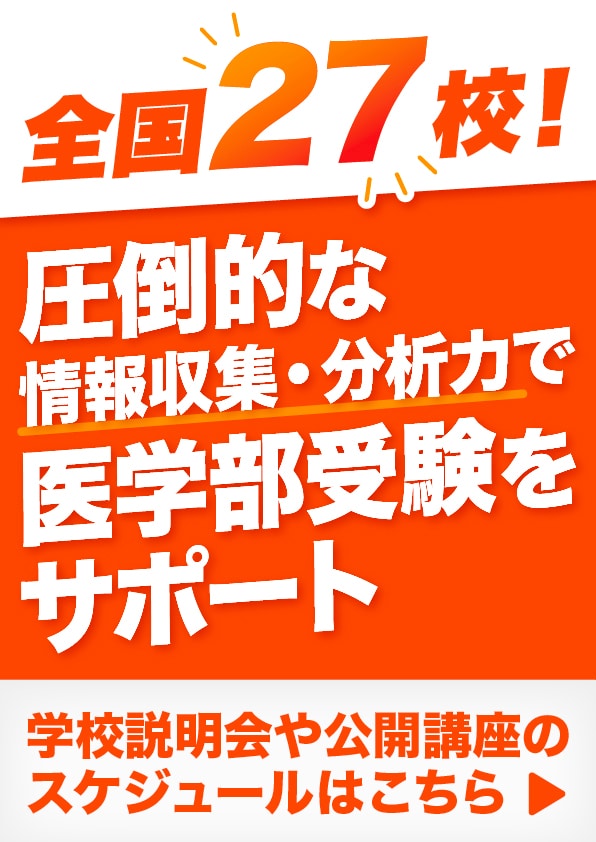数学に苦手意識がある受験生が意識したいこと
では、数学が苦手な生徒が力をつけるためには、どんな点に注意しながら勉強すればいいのでしょうか。
「基礎を徹底的に固めた上で、先ほども述べたように、とにかく量をこなすことです。数学の成績が伸びない生徒の共通点は、学習量が足りていないということに尽きます。「宿題や課題をやらない」「練習問題を解かない」。または、「問題を1回解いて、答えを見て、わかった気分になって終わる」。こう言った生徒は成績が伸びません。
予備校で授業を受けた直後は、誰でもたいていはわかった気になります。われわれプロが懇切丁寧に、図や式を書きながらわかりやすく説明するからです。
それで、「あー、わかった!」となっても、実際には「わかったつもり」になったにすぎず、そこで終わらせてしまう生徒はだいたい伸び悩みます。
なので、私は必ず「わかった!」の後に5回復習するようにと言っています。今日やったら翌日、3日後、1週間後というように、少しずつインターバルを置いて復習する。
繰り返し復習することで、どこでミスをするかに気づきます。そうして何度も何度も反復練習することで、ミスを最小限に抑えられるように力がついてくるのです」
数学の試験の解き方は?
加えて、医学部合格を勝ち取る上で、入試本番での問題への対峙の仕方も大事なポイントになると、寺井先生は指摘します。これは普段の勉強、練習問題や模試へ取り組む姿勢にもつながるといいます。
「医学部入試の数学は、大問が3〜4問出題されるのが一般的です。さらに、一部の証明問題などを除くと、各大問に4〜5問の小問が設定されています。
このとき、医学部受験生はどうやって問題を解き進めるのでしょうか? 大きく二つのパターンがあり、一つは大問の完答を目指すタイプ、つまり、小問をすべて解き切るタイプです。
もう一つは、すべての大問について、小問を2〜3問解いて次の問題に移るタイプです。
残念ながら、後者のタイプはあまりよい受験結果が出ない傾向がみられます。
極端な例でいうと、大問1~4のうち二つ完答して全問正解し、残り二つの大問には手がつけられなかった受験生のほうが合格の可能性が高く、大問1~4のすべてを(2)までで終えた受験生は合格の可能性が低くなるということです。
それには理由があります。一般的に大問1つが40点で、小問が4つある場合、(1)が6点、(2)が8点、(3)が12点、(4)が14点というように、後半に進むにしたがって配点を高く設定してあることが多いのです。もちろん、配点が高い設問ほど難しくなっているのは言うまでもありません。
したがって、大問1つを完全にを解き切れば、合格率は上がると考えられます。合格した生徒を見ても、たいてい1つを完全にを解き切っています。すべての大問をつまみ食いするのではなく、1門ないし2問の大問を完答していました。
おそらく、大学側もその力、すなわち全問解き切る力があるかどうか、を見ているように感じます」
「目の前の問題に集中する」不安の乗り越え方
受験勉強をしていると、思うように成績が伸びず、不安に苛まれることがあります。そうすると勉強しなくてはと思いつつも、なかなかエンジンがかからず、ますます焦りが生まれて勉強が手につかないという悪循環に陥りかねません。そんなときはどうすればいいのでしょうか。寺井先生は次のようにアドバイスしてくれました。
「難しいですが、吹っ切るということだと思います。こんなことをやってもムダなんじゃないか、やっても落ちるんじゃないかなど、誰にもわからない未来を勝手に想像して心配し、悩んでも意味がありません。悩むとやる気もなくなります。考えても仕方ないことは考えないことです。
私はいつも『いまを燃やしてください!』と話しています。スーパーポジティブになって、目の前の問題に全力で集中する。わからない未来のことを考えて悩むのではなく、自分が望む未来を実現するために、いまを頑張りましょうと。
ただし、『自分なりに頑張った』というレベルではダメです。親御さんが心配するくらい、別人になってしまったと驚くくらいがんばれば、必ずいまの自分を超えられるはずだと励ましています」