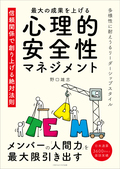(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
職場内での楽しい雰囲気は必要か?
楽しい雰囲気の職場は、決してゆるい職場ではないことを理解してください。心理的安全性を推進する話をしますと、誤解されている人にたびたびお会いします。そのときに話されることで、「ダラダラした、ピリッとしていない職場では仕事の効率は上がりません」と全否定でいわれます。
心理的安全性という言葉の響きから、このような発想をされる人がまだ多いのですが、これは明らかに間違いです。また、笑顔あふれる職場を目指すことも推奨しているのですが、これも真っ向から反対される人がいます。
日本の企業では、「仕事は真面目に取り組む厳しいものだ」「職場で笑顔になるのは不謹慎である」などの意見をまだもっている経営者がたくさんいます。楽しい雰囲気だから不真面目に仕事に取り組んでいるわけでもないのですが、伝統的な労働文化がフォーマルさをもったまま進んできたために、楽しい雰囲気を受け入れられない部分があるのでしょう。
伝統的な労働文化を大事にしつつも、雰囲気のよさや仕事の楽しさ、笑顔を同居させる新たな流れをつくり上げ、それを新しい価値観として文化を育てていく努力が必要です。
「働き方」の課題もあります。長時間労働が一般的な日本の職場では、社員が楽しい時間を過ごす余裕が足りていません。長時間働くことがよい成果を生むとは限らないため、どのようにすると効率的な時間管理ができて労働時間の長短ではなく、労働の質と成果によって評価がされる仕組みにしなければいけないのです。
そのためには、長い時間働いている人が頑張っているという従来の考え方や意識を捨て去り、自己の目標が達成できているかどうかで仕事ぶりを判断するようにしなければなりません。そのような活動により、社員のワークライフバランスが整い、余裕が生まれてきます。