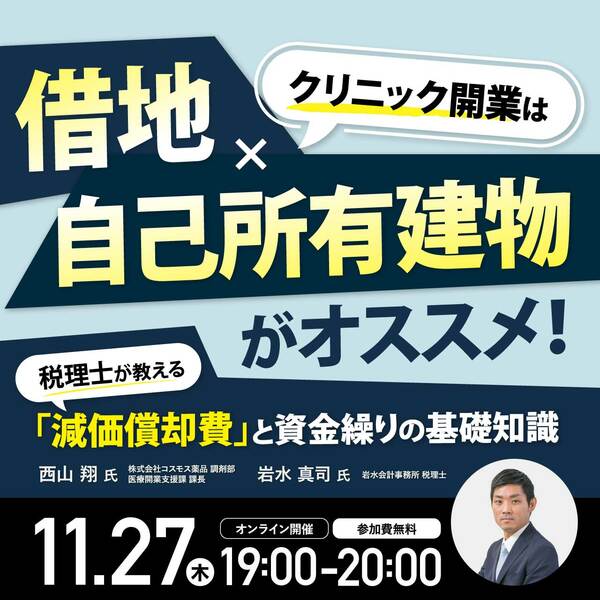ハラスメント対策が重要な理由
パワハラをはじめとする「ハラスメント」は、問題が起こってからの正しい対応はもちろんのこと、それ以上に、ハラスメントが起こらないようにする、入念な事前対策が重要です。
ハラスメント対策がなにより重要となる理由は、労働法の構造にあります。
ハラスメントが起こった場合、被害者は加害者に対する請求のみならず、会社に対して「ハラスメントが起きないような職場環境を作らなかった・ハラスメントに対する適切な対応をしなかった」ことを理由として損害賠償をすることができます。
日本の労働法の世界では、このような「会社対労働者」の構図になった場合、労働者に対して優しい結果が出やすく、会社にとって厳しい結果になるケースが多いのです。
一度法的紛争になってしまえば、会社側に厳しい結果になりやすいことから、そもそも紛争が起こらないように対策することが、なにより重要なのです。
パワハラとは?
では、ハラスメント、とくにパワハラを起こさないためにはどのような点に気を付ければよいのでしょうか?
まずは、パワハラとは一体どのようなものか、まずは定義から見ていきましょう。
パワハラとは、
「同じ職場で働く者に対して、①職務上の地位や人間関係等の職場内の優越的な関係を背景に、②業務上必要かつ相当な範囲を超えて、③精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場・就業環境を悪化させるもの」
と法律的に定義され、3つの要件すべてを満たす必要があります。
このうち、とくに問題となるのは「②業務上必要かつ相当な範囲」といえるか、という点です。いいかえるなら「どこまでであれば、やりすぎだといわれないのか」という問題です。
「どこまでであれば業務上の指導として認められるものなのか?」
「どこまでやってしまったらパワハラに該当してしまうのか?」
という疑問は、しばしば職場でも取り沙汰されており、弁護士の元にも管理職から同様の質問が多数寄せられています。
「パワハラか、それとも指導か」…判断基準はどこに?
では、パワハラと業務上必要な指導とを分けるものはなんでしょうか。画一的な回答はありませんが、裁判例によって示された基準と、パワハラの類型に沿って検討してみましょう。
パワハラには下記のような6つの類型があるとされています。
①暴行・傷害
②脅迫・名誉毀損・侮辱・度を越えた暴言
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④仕事の妨害、業務上明らかに不必要なことや遂行不可能なことの強制
⑤業務上の合理性なく、能力・経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないこと
⑥私的なことに過度に立ち入ること
このうち、①はほとんどパワハラ認定され、②③も原則パワハラにあたり、④⑤⑥がケースバイケースで判断が難しいものと分類されます。
そして、パワハラかどうかが争われた裁判において、パワハラかどうかは「言動の目的、労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性」の要素を総合的に考慮して判断するとされており、非常に個別具体的で、事例ごとによって判断される傾向にあります。
現場での具体的な対応策
クリニックの経営者、管理者の立場からすれば「なにをしたらダメなのか?」という具体的な指針が知りたいところだと思います。パワハラは個別性が高いことから、すべてに当てはまるものではないのですが、先に挙げた、
・労働者優位の法的構造
・パワハラの6類型
・考慮要素の多さ
に着目し、以下の点に留意してください。
●暴行、有形力の行使をする
→ 100%ダメ
●「バカ」「死ね」等の不適切な発言や、大声での怒鳴り付け
●人格を否定するようなニュアンスの言動
→ パワハラ認定される可能性が高い
●社員のミスの程度や頻度はどうか
●日頃の上司との関係性や態度はどうか
●他の社員に見せしめるような手段かどうか
→ これらの有無や程度によってパワハラかどうか判断が変わる
加えて、医療機関であることや、患者様が周りにいる職場環境であるクリニックという特殊性を加味すると、以下のような点も検討できるでしょう。
●身だしなみ、衛生面の指摘
→ 医療機関である以上一定程度の担保が必要であり、指摘する必要性が高まる。つまり、指導の必要性が高い
●強い言葉遣い
→ スタッフだけでなく患者様をも委縮させる可能性があり、ハラスメントとは別途クレームも生じかねない
●指導・指摘
→ 原則として、患者様がいない場で行う。患者様の目の前で指導・指摘を行う等、スタッフを必要以上に傷つけない
●その他
→ 年次と実力に応じた患者様を担当させる
クリニックのような医療機関は、命の危機を扱う等の緊張感やストレス性が普段から高く、なかなか日々のハラスメントの心遣いまで気が回らないことも多いと想定されます。しかし、これは現場で働く新入の医師や看護師も同様であり、ストレス性の高い職場であるがゆえに、苦痛や就業環境悪化が起きやすい(=ハラスメントが起こりやすい)ものです。
弁護士に寄せられたパワハラの相談も、
「指摘してもらった指導の内容には納得しているが、言い方が許せなかった」
「自分のミスはわかっているが、ミスの程度からしてそこまで言われるとショックだった」
といった内容も多く、言葉のいいまわしや指摘の仕方ひとつで、トラブルになるかどうかが分かれていることも多いのです。
緊張感のある職場環境であるからこそ、あえて意識的に柔らかい言葉を使う、初歩的なことでも繰り返しアドバイスする、指摘する場所や環境に気を配る…といった細かい配慮が必要であり、管理職や指導する立場にある医師にも、これらを徹底するよう注意喚起することが重要です。
こういったような小さな意識づけの連続が、ハラスメント対策のなによりの重要ポイントだといえるでしょう。
寺田 健郎
弁護士 弁護士法人山村法律事務所