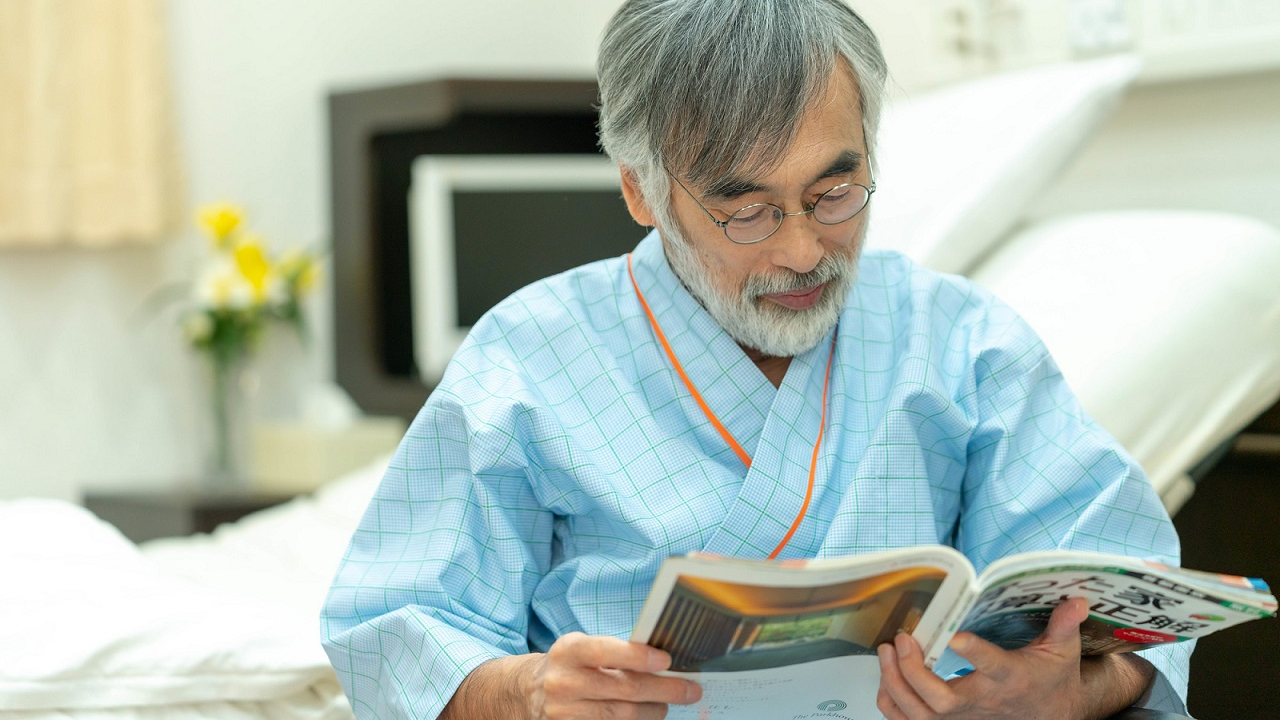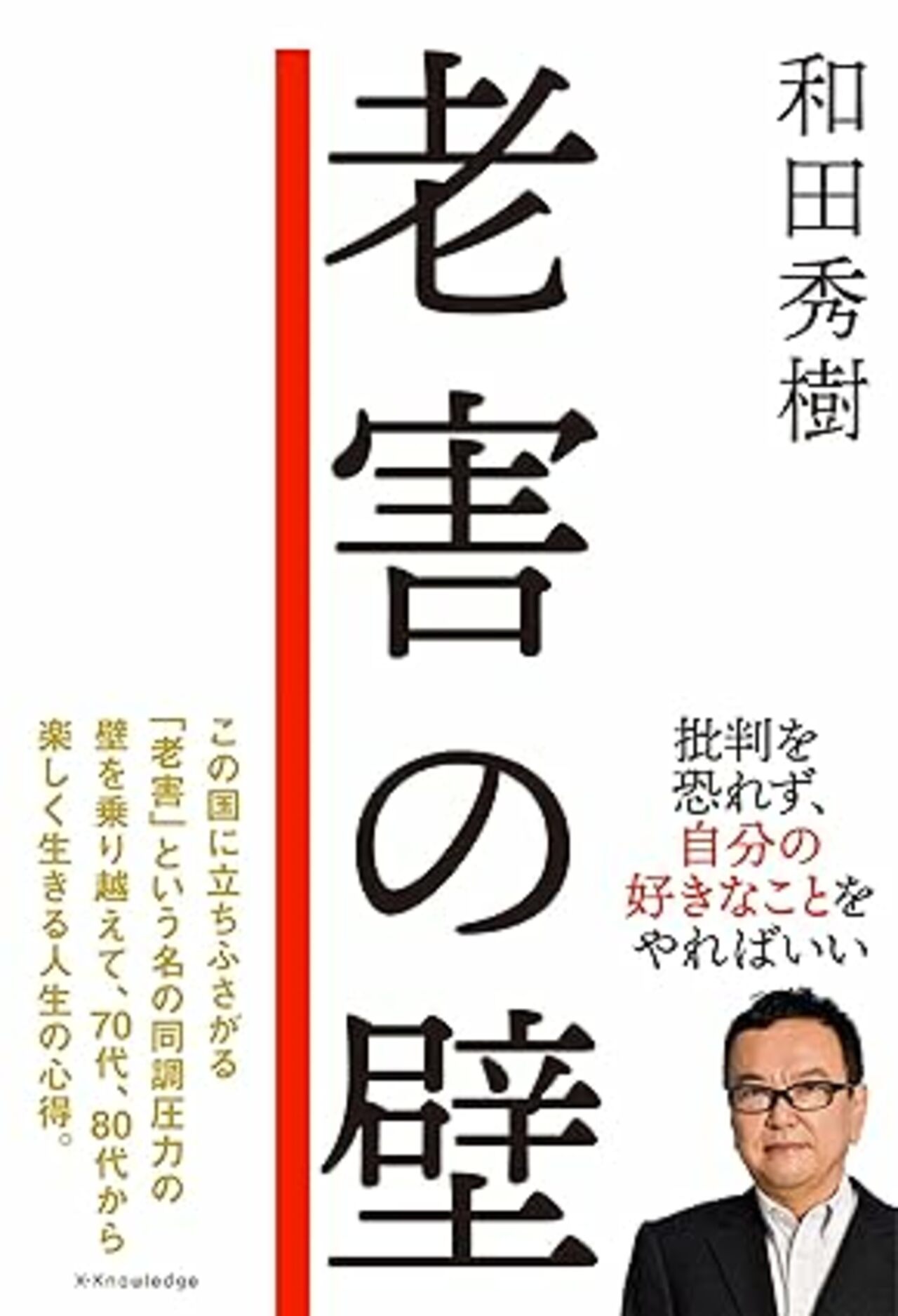マスコミによって報道される高齢者の交通事故。「免許返納」を促す言説が飛び交うばかりですが、はたして鵜呑みにしてよいのでしょうか。東大医学部卒の医師である和田秀樹氏の著書『老害の壁』(エクスナレッジ)より、高齢ドライバーによる交通事故が後を絶たない理由と、免許返納が高齢者におよぼす影響について、和田氏の見解をみていきます。

普段は安全運転だが…日本で「高齢ドライバーによる交通事故」が後を絶たないワケ【東大医学部卒の医師の見解】
高齢者による交通事故…原因は「薬の副作用」だった!?
長年、高齢者医療に携わってきた医者の立場から言うと、高齢ドライバーが交通事故を起こす原因の1つとして、常用している薬の影響が考えられます。特に、いつも安全運転を心がけている人が暴走して事故を起こすのは、薬の副作用で意識障害を起こしている可能性が否定できないのです。
薬の中には眠くなるなどの理由で、服用した場合、運転が禁止されているものがあります。その場合は、薬局で薬をもらうとき、薬剤師さんから「運転をしないようにね」と注意されるので、間違えて運転することは少ないでしょう。
これに対して、高齢者は糖尿病や高血圧の薬を常用している人が多いのですが、これらの薬(血糖降下薬や降圧薬)のほとんどは運転が禁止されていません。ところが、これらの薬を飲んだときでも運転が困難になることがあるのです。
例えば、血糖降下薬を飲むと、薬が効き過ぎて低血糖を起こすことがあります。冷や汗が出るなど、つらい症状が現れることがありますが、安全な場所に車を移動させるくらいの余裕はあります。
また、降圧薬でも血圧が下がりすぎて、ふらついたりすることがあります。この場合も、意識がなくなってしまうわけではないので、危険を回避することは可能でしょう。
ただし、これはあくまで若い人の場合です。若い人なら、上の血圧が80mmHgくらいまで下がっても、意識障害を起こすことはまずありません。これに対し、同じくらい血圧が下がっても、高齢者の場合は意識障害を起こすことがあるのです。その理由は、高齢者のほうが血管の壁が厚いからです。
動脈硬化といって、血管は年齢とともに厚く硬くなるのはご存じですね。私がかつて勤務していた高齢者専門の浴風会病院では、亡くなった入院患者を解剖して死因などを調べる「剖検」を行っていましたが、それらの剖検例でも、80歳以上の人で動脈硬化がなかった人は1人もいませんでした。
動脈硬化を起こした血管は狭くなっているので、血液の流れが若い人より悪いのですが、そこで血圧を下げると血流が滞ってしまいます。その結果、脳に酸素やブドウ糖(脳のエネルギー源)が届かなくなり、低血糖や低血圧を起こして、意識が飛んでしまうのです。