1. 建物の減価償却の基本的なしくみ

まず、減価償却とはどのようなしくみなのか、建物についてなぜ減価償却の処理を行う必要があるのか、解説します。
1.1. 減価償却とは
最初に、減価償却とは何か、簡単におさらいします。減価償却とは、建物等の事業用固定資産を購入した場合に、購入代金の全額をその年の費用とするのではなく、複数年に分けて費用計上していくという考え方です。
毎年の利益を正しく表すことができるようにするには、費用はその年度の収益に対応する形で計上していく必要があります(費用収益対応の原則)。
そこで、減価償却の処理を行うのです。すなわち、事業用固定資産の多くは、事業で使用すると損耗して使用価値が低下していきます。減価償却は、複数年度にわたって、使用価値の低下分を、費用として計上していくというものです。
実際上も、事業用固定資産は単年度ではなく、複数年度にわたって収益を生み出していくので、その購入代金も、複数年度に分けて計上していくのが合理的だということです。その年数を「耐用年数」といいます。
1.2. 不動産(建物・土地)の減価償却の考え方
不動産には「建物」と「土地」がありますが、減価償却の処理が行われるのは建物だけです。建物は事業に使用することによって損耗していくので、減価償却の処理になじみます。
これに対し、土地は損耗による価値の低下がありえないので、減価償却の対象にはなりません。
1.3. 建物の減価償却が必要なケース
建物について減価償却の処理が必要となるケースは、以下の2つです。
【建物の減価償却が必要なケース】
- 建物を事業のために使用した場合
- 建物を賃貸した場合
これらの場合には、建物は収益を上げるための事業用資産として使用されるので、購入代金を経費として計上していく必要があります。そこで、減価償却の処理が必要となるのです。
1.4.「建物附属設備」と区別して行う
建物の減価償却の計算は、「建物」本体と「建物附属設備」を区別して行います。建物附属設備は、ガス設備や給排水設備、自動ドアなど、建物本体に固着して取り外しできない設備をさします。物理的にも機能的にも建物の一部ですが、減価償却の計算をする際は、別の資産として扱うのです。
2. 建物の減価償却の計算方法

建物の減価償却を行う場合の計算方法について、特に、現在用いられている「定額法」に重点を置いて説明します。
2.1.「取得価額」と「償却率」で計算する
建物の減価償却費は、「取得価格」と「償却率」を用いて計算します。
償却率は、「1年度に資産の価値が減少する割合」であり、「4.建物の減価償却の計算における法定耐用年数」で解説する「法定耐用年数」に応じて定められています。この「償却率」については「定額法」と「定率法」の2つの異なる考え方があり、減価償却の計算式自体も異なります。それぞれの数値は国税庁HP「減価償却資産の償却率表」で確認することができます。
建物本体の減価償却においては1998年4月1日以降に取得したのであれば「定額法」を使用しなければなりません。また、定額法も、2007年4月1日以降の現行の定額法と、同年3月31日以前の「旧定額法」とで異なります。
なお、1998年3月31日以前に取得したものについては「定率法」(旧定率法)も選択できましたが、現在は認められていません。
2.2. 建物の減価償却は「定額法」が基本
定額法は、資産の取得価額を耐用年数で均等に割り、毎年同額ずつ経費として計上していく方法です。ただし、多くの場合、耐用年数できれいに割り切れません。そこで、建物の取得価格に「償却率」をかけ、端数を最終年度で調整するという形をとります。
【定額法の計算方法】
取得原価×定額法の償却率
ただし、償却が完了したら貸借対照表に「1円」の記載を残します。その資産が会社に存在するという痕跡を示すためです。
2.3.「2007年3月以前」に取得した建物には「旧定額法」
2007年3月31日以前に取得された建物については「旧定額法」が適用されるため、「計算式」及び「償却率」が現在のものとは異なります。
「旧定額法」で計算する必要がある場合は、国税庁HP「旧定額法と旧定率法による減価償却」を参照してください。
(参考)定率法(「1998年3月以前」に取得した建物に使えた計算方法)
前述のように、減価償却の計算方法には「定額法」のほか「定率法」もあります。しかし、建物の減価償却で定率法を使えるのは、1998年3月31日以前に取得した場合のみです。ただし、「旧定率法」といって、現在の定率法とは異なります。そこで、定率法については、参考までに、現在にも通じる基本的な考え方のみ紹介しておきます。
定率法は、毎年度の未償却残高に「償却率」をかけた額を経費として計上していく方法です。
【定率法の計算方法】
当該年度の未償却残高×定率法の償却率
定率法では、早い年度ほど減価償却費が大きくなります。したがって、他の資産では定額法よりも定率法が選ばれる傾向にあります。
3. 建物の減価償却における取得価額の計算方法

建物の減価償却費を算出するスタートラインとなる「取得価額」の計算方法について説明します。
3.1. 建物の取得価額とは
取得価額は、建物を購入した場合は「建物の購入対価」、建物を建てた場合は「建築にかかった費用」をさします。それに加え、以下のような費用が含まれます。
【建物の取得価額に含まれる費用】
- 購入時の仲介手数料
- 登録免許税、不動産取得税等の税金
- 契約書の印紙代
- 整地にかかった費用
- 古屋建物の取り壊し費用
3.2. 取得価額に含めないことができる(減価償却の処理が不要な)費用
ただし、建物の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に含めなくてよい費用もあります。減価償却の処理をしなくてよい、つまり、支払った年度に全額を一気に計上してしまって構わないということです。以下の費用です。
【建物の取得価額に含めなくてよい費用】
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 新増設に係る事業所税
- 登記に要する費用
- 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
- いったん結んだ契約を解除した場合の違約金
- 土地を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでに生じたもの)
3.3. 建物の取得価額の確認方法
建物の取得価額のメインは、「建物の購入対価」「建築にかかった費用」です。売買契約書や工事請負契約書に「建物の金額」が記載されていれば、その額を取得価額と考えます。
3.4. 建物と土地の内訳が不明の場合
しかし、売買契約書・工事請負契約書を紛失した場合や、そもそも売買契約書に土地と建物の内訳が記載されていない場合もあります。その場合は、減価償却の対象になる建物と、対象にならない土地で、算出し直さなければなりません。
厳密な金額を算出するには不動産鑑定士に依頼する方法がありますが、費用がかかるのが難点です。そこで、それ以外で認められている、比較的簡単な算出方法を3種類紹介します。
3.4.1. 消費税額から算出する
まず、売買契約書が手元にある場合は、「消費税」を手掛かりとして建物価格を計算することも可能です。なぜなら、消費税は建物にかかりますが、土地にはかからないからです。
たとえば、売買代金総額 5,000万円、消費税220万円(消費税率10%)の場合、建物代金は、
220万円÷10%(消費税率)=2,200万円
となります。
3.4.2. 固定資産税評価額で按分する
売買契約書すらない場合は、「固定資産税評価額」から土地と建物の割合を按分(あんぶん)して算出する方法があります。
固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書に記載されているほか、役所で評価証明書を取得することも可能です。
3.4.3. 建物の標準的な建築価額から算出する
最後に、国税庁HPで提示されている「建物の標準的な建築価額表」を利用する方法です。この表は、建物の建築年と構造をもとに、1㎡あたりの標準的な建築価額を示したものです。
たとえば、「昭和59年(1984年)建築 木造住宅(90㎡)」であれば、標準的な建築価額は「10.28万円/㎡」なので、建物代金は以下の通りです。
10.28万円×90㎡=925.2万円
4. 建物の減価償却の計算における法定耐用年数

建物の減価償却の計算は「耐用年数」に従って行います。ここでは、新築建物に適用される「法定耐用年数」について解説します。
4.1. 法定耐用年数とは
減価償却の計算は、「法定耐用年数」にしたがって行います。建物の場合は、「構造」「用途」によって、細かく分けられています。
法定耐用年数は、「本来の用途に使用して、通常期待できるだけの効果を上げることができる年数」をいいます。財務省令で定められています。会計処理の便宜のために設けられた期間なので、それを超えて使用することは何の問題もありません。
4.2. 主な建物の法定耐用年数(耐用年数表つき)
建物の法定耐用年数については、以下の2点を押さえておけば、理解しやすいと思われます。
- 構造:頑丈であるほど耐用年数が長い
- 用途:利用頻度が高いほど耐用年数が短い
たとえば、構造が同じ「木造建物」であっても、下記のように、利用頻度が高い「用途」ほど、法定耐用年数が短く設定されています。
【木造建物の「用途別」法定耐用年数】
- 事務所用:24年
- 店舗・住宅用:22年
- 飲食店用:20年
- 旅館用・ホテル用・病院用・車庫用:17年
- 公衆浴場用:12年
- 工場用・倉庫用(一般用):15年
このようなイメージを持って、以下【図表】の建物の耐用年数表をご覧ください。
【図表】建物の法定耐用年数表
| 構造・用途 | 細目 |
耐用年数(年) |
| 木造・合成樹脂造 |
事務所用のもの |
24 |
|
店舗用・住宅用のもの |
22 |
|
|
飲食店用のもの |
20 |
|
|
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの |
17 |
|
|
公衆浴場用のもの |
12 |
|
|
工場用・倉庫用のもの(一般用) |
15 |
|
|
木骨モルタル造 |
事務所用のもの |
22 |
|
店舗用・住宅用のもの |
20 |
|
|
飲食店用のもの |
19 |
|
|
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの |
15 |
|
|
公衆浴場用のもの |
11 |
|
|
工場用・倉庫用のもの(一般用) |
14 |
|
|
鉄骨鉄筋コンクリート造・ 鉄筋コンクリート造 |
事務所用のもの |
50 |
|
住宅用のもの |
47 |
|
|
飲食店用のもの |
- |
|
|
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの |
34 |
|
|
その他のもの |
41 |
|
|
旅館用・ホテル用のもの |
- |
|
|
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの |
31 |
|
|
その他のもの |
39 |
|
|
店舗用・病院用のもの |
39 |
|
|
車庫用のもの |
38 |
|
|
公衆浴場用のもの |
31 |
|
|
工場用・倉庫用のもの(一般用) |
38 |
|
|
れんが造・石造・ ブロック造 |
事務所用のもの |
41 |
|
店舗用・住宅用・飲食店用のもの |
38 |
|
|
旅館用・ホテル用・病院用のもの |
36 |
|
|
車庫用のもの |
34 |
|
|
公衆浴場用のもの |
30 |
|
|
工場用・倉庫用のもの(一般用) |
34 |
|
|
金属造 |
事務所用のもの |
- |
|
骨格材の肉厚が、(以下同じ) |
- |
|
|
4mmを超えるもの |
38 |
|
|
3mmを超え、4mm以下のもの |
30 |
|
|
3mm以下のもの |
22 |
|
|
店舗用・住宅用のもの |
- |
|
|
4mmを超えるもの |
34 |
|
|
3mmを超え、4mm以下のもの |
27 |
|
|
3mm以下のもの |
19 |
|
|
飲食店用・車庫用のもの |
- |
|
|
4mmを超えるもの |
31 |
|
|
3mmを超え、4mm以下のもの |
25 |
|
|
3mm以下のもの |
19 |
|
|
旅館用・ホテル用・病院用のもの |
- |
|
|
4mmを超えるもの |
29 |
|
|
3mmを超え、4mm以下のもの |
24 |
|
|
3mm以下のもの |
17 |
|
|
公衆浴場用のもの |
- |
|
|
4mmを超えるもの |
27 |
|
|
3mmを超え、4mm以下のもの |
19 |
|
|
3mm以下のもの |
15 |
|
|
工場用・倉庫用のもの(一般用) |
- |
|
|
4mmを超えるもの |
31 |
|
|
3mmを超え、4mm以下のもの |
24 |
|
|
3mm以下のもの |
17 |
国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」より
5. 建物の減価償却の計算例

建物の減価償却の計算例を一つ紹介します。「定額法」を利用します。
【設例】木造の事務所用建物
- 取得価額:2,000万円
- 法定耐用年数:24年
- 定額法償却率:0.042
このケースにおいて、各年度の減価償却費は以下の通りです。
- 1年目~23年目:2,000万円×0.042=84万円
- 24年目:2,000万円-(84万円×23)-1円=67万9,999円
23年目までは毎年同じ「84万円」を減価償却として計上します。これに対し、24年目も「84万円」を計上してしまうと取得価額を超えてしまうため、最終年度は残った金額(68万円)について、1円だけ残して償却します。この1円だけ残す処理は、前述したように、建物が事業用資産として存在することを示すためのものです。「備忘価値」といいます。
6. 中古建物の耐用年数

ここまでお伝えしてきたのは「新築」の建物を取得した場合の減価償却の方法です。中古建物を取得した場合については、「耐用年数」を別に考える必要があります。
中古建物の場合、一般に、「簡便法」という計算方法を用いることができます。簡便法では、以下の2つのケースに分け、それぞれ異なる計算方法を用います。
- 築年数が法定耐用年数を経過していない場合
- 築年数が法定耐用年数を経過している場合
なお、中古建物でも、補修等のための支出(資本的支出)をした場合、その額が取得価額の50%を超えていれば、簡便法は使えません(詳しくは国税庁HP「タックスアンサーNo.5404」をご覧ください)。この場合は資産価値を高め、耐用年数を伸ばしたとみられるからです。
さらに、資本的支出の額が「再取得価額」(同等の新築建物を購入・建築する場合にかかる金額)の50%を超えた場合は、新築建物と同視され、法定耐用年数が適用されます。
以下では、簡便法の計算方法について説明します。
6.1. 築年数が法定耐用年数を経過していない場合
まず、築年数が法定耐用年数を経過していない場合、簡便法の計算式は以下の通りです。
【法定耐用年数を経過していない場合】
耐用年数=(法定耐用年数-築年数)+築年数×0.2
ただし、この計算式を用いると、多くの場合、1年未満の端数が生じることになります。その場合は切り捨てます。
たとえば、築21年の工場用物件を購入した場合、耐用年数は以下の通りです。
【計算例】
鉄筋コンクリート造、工場・倉庫用(法定耐用年数38年)、築21年
⇒(38年-21年)+21年×0.2=21.2年⇒耐用年数21年
6.2. 築年数が法定耐用年数を経過している場合
次に、築年数が法定耐用年数を経過している場合、簡便法の計算式は以下の通りです。
【法定耐用年数を経過した場合】
耐用年数=法定耐用年数×0.2
ここでも1年未満の端数は切り捨てです。
以下、不動産賃貸業に使用するために木造中古アパートを購入した場合の計算例です。
【計算例】
木造、住宅用(法定耐用年数22年)、築25年
⇒22年×0.2=4.4年⇒耐用年数4年
なお、よく、「築22年超の木造中古アパート」が節税になるといわれるのは、このように、4年で減価償却を終えることができるからです。特に、個人の場合、この減価償却で不動産所得の赤字を出し、それを給与所得から差し引く「損益通算」ができるということで、大変人気があります。
6.3. 住宅等を事業用に転用した場合の減価償却
住宅等、もともと事業用でなかった建物を事業用へと転用した場合には、計算方法がやや複雑です。以下の2段階で計算します。
- 第1段階:事業用でなかった期間分の「減価償却相当額」を計算する
- 第2段階:事業用に転用した後の分について簡便法で減価償却費を計算する
第1段階の「事業用でなかった期間」については、「減価償却相当額」を算出します。以下の計算ルールを用います。
【減価償却相当額の計算ルール】
- 耐用年数は法定耐用年数の1.5倍
- 償却率は取得日に関係なく「旧定額法」が適用される
第2段階では、事業用に転用した時点で中古建物を取得したと同視して、減価償却費を計算します。
まとめ
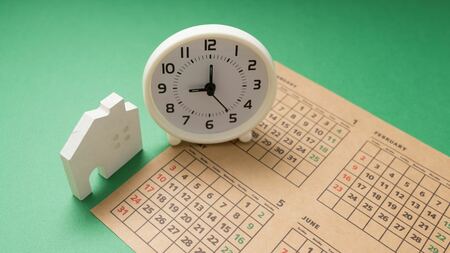
建物の減価償却においては、「構造」「用途」によって「法定耐用年数」が詳細に定められています。また、計算方法は基本的に「定額法」のみが認められています。
減価償却を行うにあたってはまず、建物の取得価額を確定する必要があります。建物の価格が不明な場合には、消費税額、固定資産税評価額、標準的な建築価額から算出する方法があります。中古建物については、法定耐用年数を基準として、それより短い期間で償却できることになっています。
このように、建物の減価償却は、耐用年数が細かく定められているほか、他の資産にない特徴があります。本記事で解説した事項を十分に理解して、正確に処理してください。


