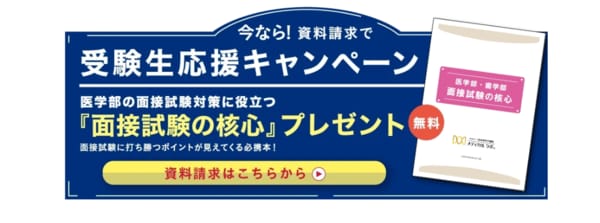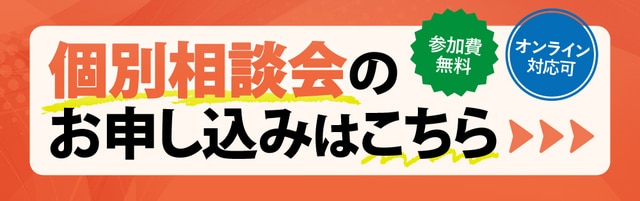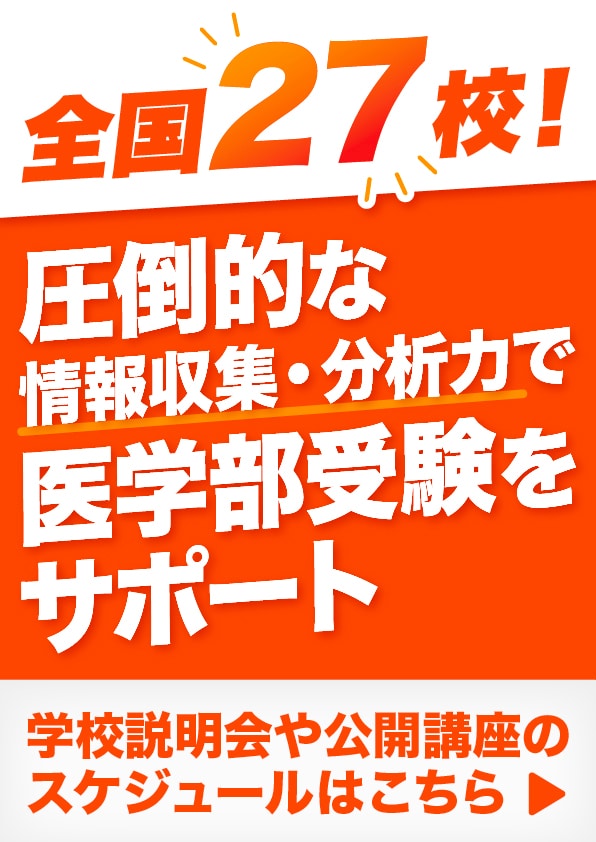「親は最後の砦であってほしい」保護者の役割
動画学習に慣れた子どもたちが「書く力」を失いつつある現状や、「親が子どもの進路に保険をかけること」の危うさについて語った森氏。
では、医学部受験生の保護者は親として何をすれば良いのだろうか?
それに対して森氏は「今日の講演の趣旨は『答えを教えること』ではありません。答えは、皆さんとお子さんとの関係の中にしかないんです」と訴える。
「大学受験は親子関係を見直すタイミング」「親子でしっかり対話をしてほしい」––。今回の90分の講演の中でも森氏が何度も訴えてきたことだ。
「やっぱり、親は“最後の砦”なんです。世の中の全員が敵になったとしても、やっぱりお父さんやお母さんは、最後の砦でいてほしいんです」
たとえば、子どもが帰宅した瞬間に「勉強してるの?」「なんでスマートフォン(スマホ)ばかりいじってるの?」と詰問してしまう家庭も多いだろう。しかし、子どもたちは外でも戦っている。塾や学校で小言を言われ、ネットでは匿名の非難にさらされる。そんな“戦場”のような世界から帰ってきて、家の中まで戦場になってしまえば、心を閉ざしてしまうのも無理はない。
「家は受け入れてもらえる場所だ」「ここは味方なんだ」と子どもに感じさせることができれば、「じゃあ一緒に悩んでみようか」と親子で向き合う関係が築ける。森氏はそう助言する。
比較は「ステルス悪口」
さらに森氏は、子どもとの比較についても注意を促す。「落ちる受験生の親は『よそはよそ、うちはうち』と言いながら、実際には周囲と比べている」。たとえば、「◯◯君はすごいね」「◯◯ちゃんのお兄ちゃんは東大行ったらしいよ」など、悪気なく投げかける一言が、子どもの心を傷つけることがある。
「それって子どもには『お前は遅れているんだよ』という裏メッセージとして伝わってしまうんです。だから私は、“比較はステルス悪口”だと(自著に)書きました」
比較されればされるほど、子どもの自己肯定感は損なわれていく。必要なのは「比較」ではなく「承認」と森氏は力を込める。
一度スマホを捨ててみる? 問われる「親の姿勢」
では、どうすればいいのか。その具体的なアクションとして森氏が提案するのが、「家族全員で一度スマホを捨ててみる」という試みだ。「落ちる親は『スマホをやめなさい』と言いながら、自分はやめない。一方、受かる親は『やめなさい』とは言わず、まず自分がやめる。そこが決定的に違います」
実際、森氏の元に「今偏差値30なんですが、1年で早稲田に行けますか?」と相談に来た生徒がいたという。森氏が「スマホを見てたら無理だよ」と言うと、その生徒はその場でスマホを机に置き、「もう僕、スマホいりませんわ」と言った。その1年後、彼は本当に早稲田に合格した。
この覚悟は、保護者にも必要だと森氏は語る。
「最近は、寝るときにリビングにスマホを置く、というルールが注目されています。でも『目覚ましに使ってるから』と反論されることも多い。だからこそ、食事中は家族全員でスマホの電源を切る、特定の時間だけは一切触らないといった“実行できる習慣”を作ることが大事なんです」
本と同じように、スマホも「使わない姿を見せる」ことが大切だと森氏は語る。
「子どもに『読書しなさい』と言うなら、自分も読んでいなきゃ説得力がない。本を読まなくても“読んでるふり”だけでもしなさい、という先生もいるくらい。積ん読でもいいんです。大事なのは”見せること”です」
同様に、「スマホも、まず親が使わない姿勢を見せるべきなんです。あるいは、『俺はもう使わない!』と目の前でバキッと割るくらいの覚悟を見せてもいい。……まあ、壊すのはおすすめしませんけど(笑)」
こうした親の姿勢が、子どもの心を動かす引き金になることがある。
「子どものスイッチが入らない」と悩む親は多い。しかし森氏は、「それは大人だって同じです」と言う。「うちの母も『ダイエットスイッチが入らない』って言ってますから(笑)」
人間は誰しも思うように動けないもの。だからこそ、親は子どもに「なぜできないの」と詰めるのではなく、言葉と態度で寄り添う必要がある。
加えて森氏は、「親が自分の経験をもとに決めつける危うさ」にも言及する。
「『もう16歳なんだから』と言っておきながら舌の根も乾かぬうちに『まだ子どもなんだから』と言う親御さんもいらっしゃいますが、都合によって基準を変えると、子どもは混乱します」
そんな森氏自身も、実は日々反省の連続だという。「毎晩、あれは言いすぎたなと反省しています。次に会ったときは謝ろうって思う。気にしすぎて逆流性食道炎にもなりました(笑)」
だからこそ、親も「謝る姿勢」を見せることが大切だという。「あのときは言い方が悪かった。ごめんね」と素直に伝えること。すぐに許されなくても、時間をかけて向き合う姿勢が子どもに伝わる。
“効率化”では伝わらない、親の背中
近年は親子の会話にも「タイパ(タイムパフォーマンス)」や「コスパ」という概念が浸透しているが、森氏はそれに異を唱える。
「コミュニケーションは効率化できるものじゃない。衝突もあるし、面倒なもの。でも、それを乗り越えるからこそ家族なんです」
親の役割は、子どもにレールを敷くことではなく、背中をそっと押すことだという。
「『お前が頑張るなら、私も自分の人生を頑張ってるよ』と。そんな姿を見せることが一番の教育です」
特に、子どもが思春期に入る頃は、親自身も仕事で責任の重い立場を任される時期と重なりやすい。だからこそ、頑張る親の姿そのものが、無言のメッセージになる。
「子どもが生きがい、というお母さんも多い。でも、まだ幼かった頃の“かわいさ”に執着してしまうと、思春期の子どもにはそれが重たくなってしまう」
読書を楽しむ、趣味に打ち込む、仕事に向き合う……。そうやって「自分の世界を持っている大人」は、子どもから見ても魅力的に映るのだという。
「教育は投資じゃない」親は“チームメイト”
ある講演会の後、父親から「先生、息子が一番リターンの悪い投資でしたわ(笑)」と冗談を言われたことがあったという森氏。「そのくらい笑って言えるなら大丈夫。でも、最近は教育を“投資”として真面目に捉える親も増えている。それならもう、ビットコインでも買ってくださいって言いたくなりますよ(笑)」
森氏は、親を「プロジェクトチームのチームメイト」と表現する。父と母で連携し、情報共有をしていくことが重要である。
「たとえば、お父さんが久しぶりに子どもと話すときに、威厳を見せようとして厳しくなりすぎてしまう。『普段は優しいのに、勉強の話になると人格が変わる』という学生からの相談、たくさん受けてます」
そうしたときは、子どもからも勇気を出して「お父さんのこと好きだけど、その言い方はイヤ」と伝えてみてほしい。大事なのは、親が「気にかけてくれている」と感じられることだ。
最後に森氏は、こう語りかけた。
「ここまで医学部の話をしてないじゃないかって思いましたよね?(笑)でも、実はここが本質なんです。医学部だからこそ、“真っ当で本質的な勉強”が必要なんです。その土台にあるのは、“特別なメソッド”ではなく、“地に足のついた親子関係”なんですよ」
そして「この話を聞いて、賛成でも反論でも構いません。それをご家庭に持ち帰って、唯一無二の“あなただけの答え”を見つけてください」と会場に集まった保護者に語りかけ、「私は所詮、踏み台です。チョーク芸人です(笑)」と講演を締めくくった。
森 千紘
河合塾英語科講師