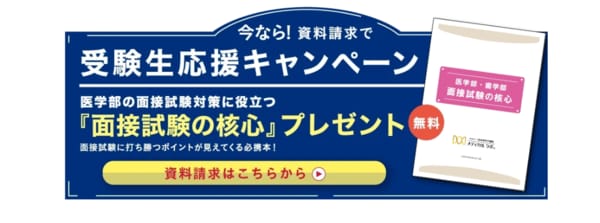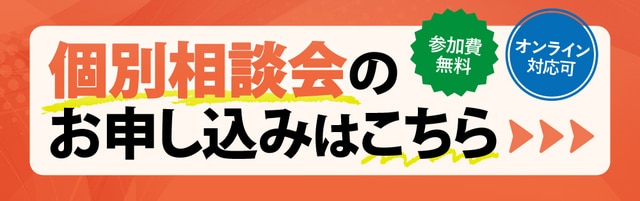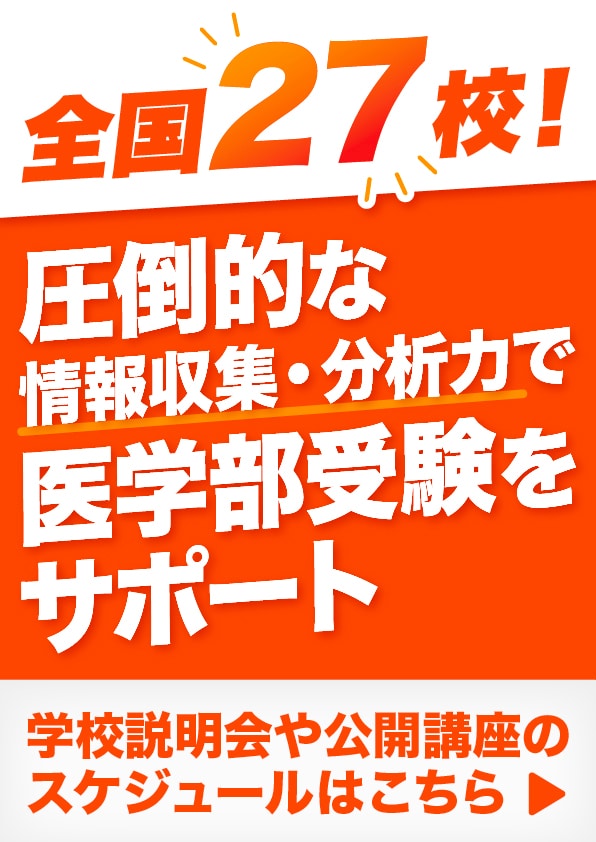コロナ禍以降、“勉強する姿勢”が大きく変わった
今回の講演のテーマは「医学部に受かる親子とは?」。森氏によると、まず保護者に知っておいてほしいのが「学生たちの現状」だ。
「ある高校1年生の授業では、後ろの席の子が壁にもたれて腕を組み、鉛筆もノートも出さず、まるで理事長のような態度で授業を聞いていました。完全に“見てるだけ”の状態です」(森氏、以下同)
森氏は「コロナ禍で定着した、動画学習による『受け身の学び』の弊害」と指摘する。
「Zoom授業では画面オフ、背景非表示、場合によっては裏でNetflixを流していたような子もいたかもしれません。情報をただ受け取るだけで『やった気』になってしまう。コンテンツを“消費”するだけ。ノートを取らない、鉛筆を持たない、書かない。この『書かない文化』は、深刻なレベルにまで進行しています」
森氏は「デバイスを使い分けるのは時代の流れかもしれません」としながらも「大学入試はまだ手書き。字は薄かったり濃かったり、バランスも悪く、なかには英語の答案をすべて平仮名で書いてくる生徒もいました。『世界』が『せかい』。学校の先生が『わからなかったら、平仮名でいいよ』とか言ってるんでしょうね。それは教育ではありません」とキッパリ。
さらに、答案にきちんと文字が書けないのは「タブレット学習の影響が大きいんです。筆圧がうまく伝わらないので、答案の文字は薄かったり濃かったりして読みづらい。紙と違って適度な抵抗がないから、変な文字になってしまうんです」と説明する。
一方、学校側はそんな生徒たちにどんな指導をしているのか?
「ちょっと注意しようものなら、すぐにクレームが入る。だから先生たちも見て見ぬふりをするようになるんです。大人がちょっと声をかければ済むようなことでも、『言ったら損をする』と思われて、結局誰も何も言わない。そうして子どもたちは、完全に野放しの状態になってしまっている。『自分で気づいてね』と放り出されて、それに気づける子はどんどん伸びていく。でも、気づけない子は社会から取り残されていくんです」
学校も周りの大人も生徒たちに気を遣って何も言えない状況にあって、生徒たちを指導するのは「自分の責任」と森氏は力を込める。
「僕は授業で、勉強の出来には文句を言いません。偏差値が3でも、0点でも、全然構わないおめでとうございます。『よく頑張ったな』と言います。だって、0点を取るって、ある意味すごいことなんですよ。普通なら心が折れてしまうはず。でも、それでも教室に来て、そこに座っている。その精神力は並大抵じゃありません。学力は偏差値3でも、精神力は偏差値90。そういう子は、必ず伸びていきます」
そして「書く力」の重要性を繰り返す。
「今は、動画を見て、ポチポチ答えるだけで『勉強した気』になれる時代。確かに、アプリが『すごい!』と褒めてくれるのは気持ちいいかもしれません。でも、そんな方法で医学部に合格できるわけがありません。そんな医者、ゴリラと一緒です。冗談抜きで、『書く力』が問われる時代なんです」
中高生にとって大事な「自立」
そんな時代にあって、最も大事なことは何だろうか? 森氏が何度も繰り返すキーワード、それは「自立」だ。
「私たちメディカルラボでは、授業の中に『講義→テスト→解説→宿題→演習→模試』という一連の流れを組み込んでいます。その中で特に重視しているのが、『問題演習』の時間です。ここでは、生徒がまず自分の力でやってみる。たとえ間違ってもいい、とにかく自分の頭で考えて、手を動かす。この姿勢が、『本当の学び』に直結するのです」
中学生であれば、まずは定期テストに真剣に向き合うこと。「一夜漬けでもいいから、本気で悪あがきしてみろ!」と語るように、取り組む姿勢そのものが学びにつながると説く。
「もちろん、一夜漬けを“狙う”のはダメですよ。『今回も一夜漬けでいこう』とかね。それはよくない。でも、結果的に一夜漬けになっても、必死にやってみるという経験は必要です」
高校生になると、模擬試験を「学びの節目」として活用することが重要になってくる。結果の良し悪しではなく、模試という機会をいかに活かせるかが問われる。
加えて、森氏は「変化の激しい時代だからこそ、『変わらない本質』を見抜く力が必要」と強調する。
「『この資格も、あの検定も』と増やしても、それは場当たり的な対応にすぎない。『今、本当に必要なことは何か?』を、子ども自身が考えられるようにしていくべきです。入試制度が変わっても、問われる力の本質は変わりません。英語なら論理を読み取る力、語彙力、和訳力です。速読なんて言葉に惑わされて、SVOCも知らずに読み飛ばす……そんなのは『史上最速の不合格』です」
親は“保険”をかけたつもりでも…保護者の役割とは?
では、保護者の役割とは何だろうか。
森氏が紹介するのは、ある東大卒の父親と高校3年生の娘のエピソードだ。
「彼女は、私立薬学部を志望していました。英語・数学・化学の3科目で受験できる、比較的コンパクトな入試です。でも、お父さんは『国公立理系にしておけ』と進路変更を促しました。『将来潰しがきくから』というのが理由です」
しかしその結果、彼女は興味のない科目(国語・社会・物理など)を追加で学ばなければならなくなり、赤点を連発。模試は丸1日がかり。ついには不登校になり、部活も辞め、人間関係も崩れた。そして浪人を経て、最終的に最初に希望していた私立薬学部へと進学した。
「誰が悪いという話ではありません。お父さんは善意で言った。でも、娘さんも『無理です』ともっと強く言うべきだった。お母さんも、どこかで引いてしまった。お父さんが東大卒だからって、何も言えなくなってしまった。親子でしっかりと話し合わなきゃいけなかったんですね」
そして森氏はこう続ける。
「“保険”をかけたつもりでも、その“保険料”を払うのは子どもです。社会人ならお金で払える。でも高校生は、時間と労力で支払うしかない。国公立理系を『潰しがきくから』と安易に勧めるのは危険です。しっかり対話して決めるべきなんです」
受験は“家族関係が試される”タイミング
進路をめぐる対話は、家族の関係性を映し出す鏡でもある。
「『ちゃんと話し合えたよね』という記憶は、子どもにとって何よりの財産になります。『人生を決める場』ではなく、『信頼を深める場』として受験を位置づけてほしい。私はずっと、そう伝えてきました」と森氏。
そして会場に向かって「お子さんに『あなたはどうしたいの?』と聞いてみてください。そして、親御さん自身の考えも素直に伝えてください。『一緒に考えよう』という姿勢こそ、信頼を育てる第一歩です」と呼びかけた。
森 千紘
河合塾英語科講師