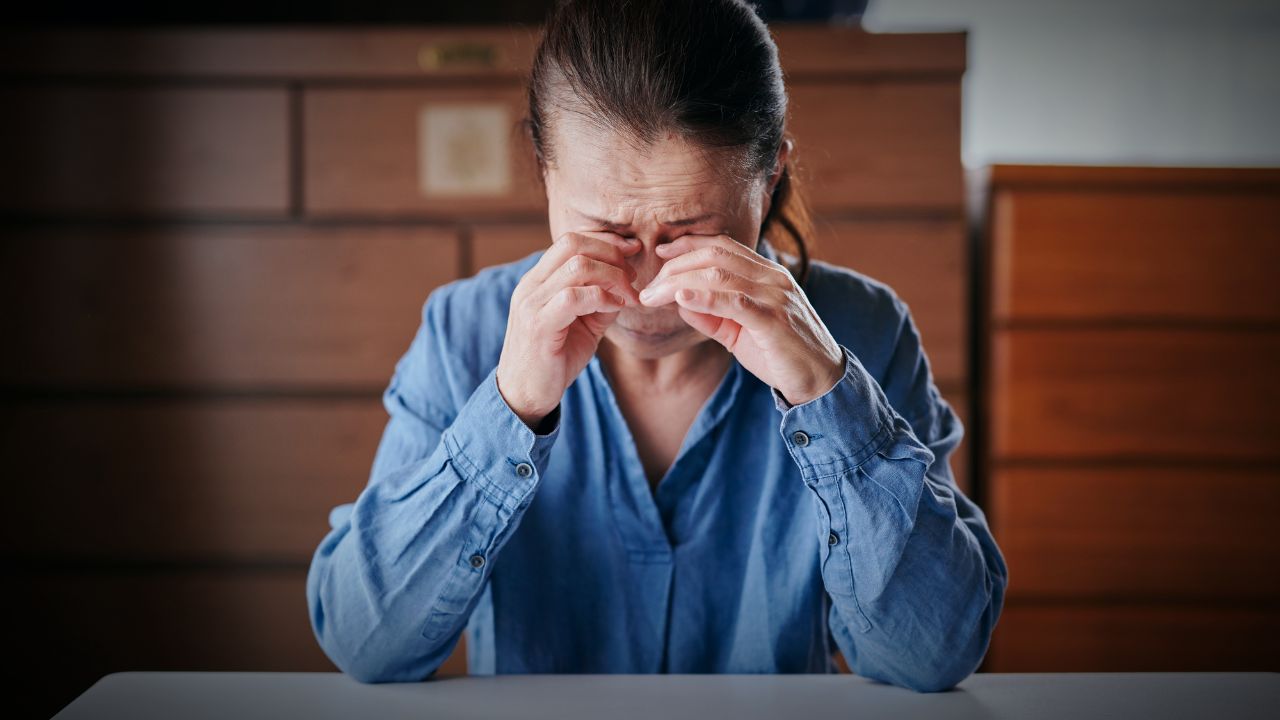 (※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
夫婦の年金で「老後生活を計画する」ことの落とし穴
多くの夫婦が「老後を迎えたら……」と会話をしていることでしょう。田中さん夫婦の場合も、夫・健一さんが70代となり、老後の生活について話すことが増えていたといいます。
――そろそろ、夫婦水入らずでゆっくりと過ごそうか……
そう、思いをはせていたときに、健一さんが急逝。急性心筋梗塞だったといいます。智子さん、最愛のパートナーを失った悲しみとともに号泣。しかし、すぐに今後の生活について考えていかないとなりません。まず直面するのがお金の問題。老後の生活の基盤であった公的年金ですが、夫の死によって、智子さんが受け取るのは夫の遺族厚生年金と自身の年金となります。
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある智子さんの場合、夫の死亡による遺族厚生年金を受け取る際には、「①夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」と「②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1と自身の老齢厚生年金の額の2分の1を合算した額」を比較し、高い方が遺族厚生年金の額となります。結果、智子さんが受け取れる遺族厚生年金は11.4万円。自身の年金と合わせると月18.4万円。しかも遺族厚生年金は非課税なので、手元に残るのは月17万円ほどだといいます。
最愛の夫を亡くしたとはいえ、手取り月17万円の年金があれば十分。しかし、田中さん夫婦は年金+アルバイト代で老後の生活設計を行っていました。つまり月33万円程度の収入がある、という前提で家計を運営していたわけです。それが夫の急逝を受けて半分近くに減ってしまったわけですから大問題。しかも田中さん夫婦の場合、住まいが賃貸マンションだったこともあり、賃貸生活では家賃の負担が重くのしかかります。
――2人暮らしで家賃月14万円のマンションに住み続けるには、貯蓄の取り崩しは必須。でもそんな生活は不安が大きすぎるので、引越しをしないと
家なし危機を解決するために「息子家族との同居」を考えたが
株式会社R65の『高齢者向け賃貸に関する実態調査』によると、高齢者の入居を「受け入れていない」とする賃貸オーナーが約4割。「積極的に受け入れている」とする賃貸オーナーは2割未満です。また調査では、不動産会社の4社に1社が、高齢者が入居可能な賃貸住宅がゼロであることも明らかになっています。つまり、賃貸生活を送る高齢者は、将来的に「あなたには部屋を貸せません」という事態に直面する可能性が高いのです。
智子さんも同様です。「もう家賃が払えない!」と部屋の更新をやめて引越しを決意したものの、「年金で生活している人は……」「働いていない高齢者は……」などと断られ続けています。
――このままだと家なしになってしまう
智子さん、危機感を募らせます。ひとり息子を頼ろうかと思いましたが、義娘とは折り合いが悪く、距離を置いています。とても頼ることはできなさそうです。株式会社AlbaLinkが行った『親との同居に関する意識調査』によると、親と同居するメリットとして「金銭面で楽になる」が圧倒的に多い一方で、デメリットとして「気を遣って自由に過ごせない」「干渉・管理される」「ケンカが増えそう」などの理由が挙げられ、懸念事項が多いことが浮き彫りになっています。
家なし危機に対し、智子さんが出した答えとは……「老人ホームへの入居」でした。
――ほかの入居者と比べると、65歳の私は若いみたいで。少し浮いているけど「住む家がない」というストレスからは解放されました
高齢者の住まいの有力な選択肢になりつつある「老人ホーム」。その入居条件は、60歳、または65歳からというホームが多く、最近は介護を必要としない自立していることが条件とするホームも増えています。高齢者が直面する家なし問題。その解決策として、今後ますます老人ホームが果たす役割が大きくなっていきそうな気配です。
【THE GOLD ONLINE おすすめの会員限定記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ
[参考資料]









