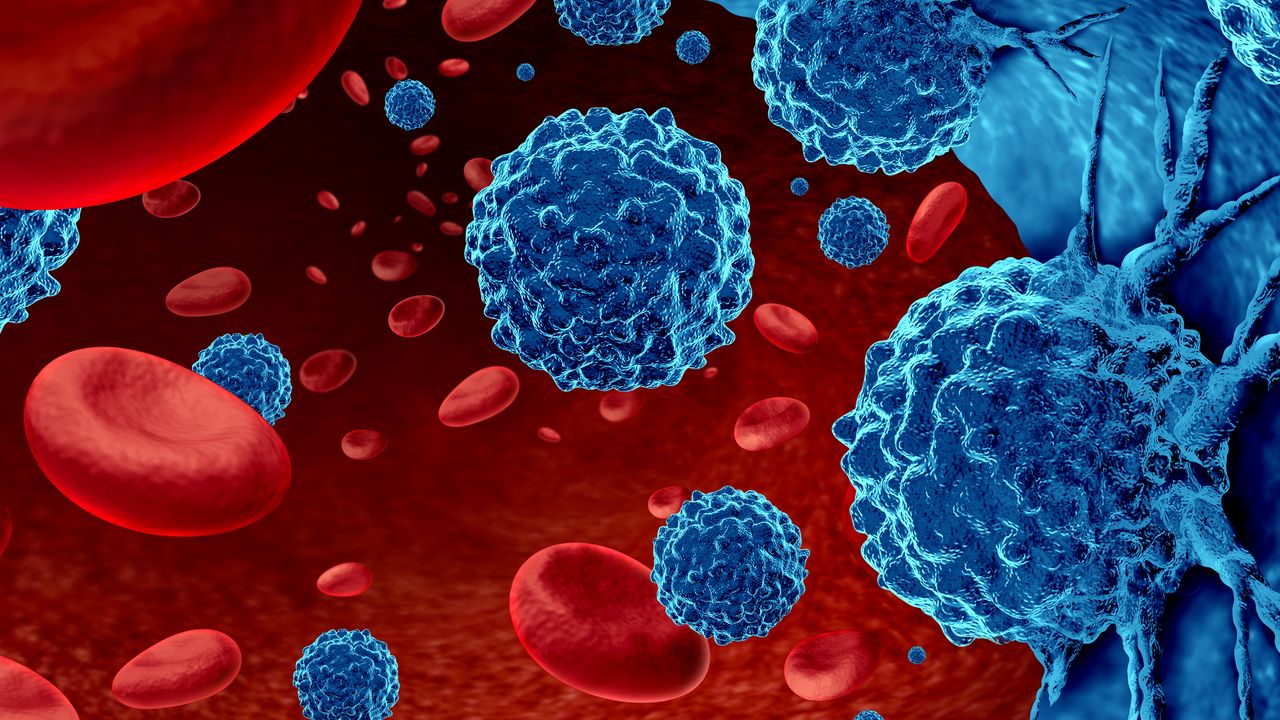日本人の死因第1位である「がん」。身近で怖い病気として知られるがんのリスクを減らすため、定期的にがん検診を受ける人は少なくありません。しかし、検診でがんが見つかり手術したとしても、「命拾いした」とはいえない可能性があるといいます。それはなぜなのでしょうか。本記事では、『健康の分かれ道 死ねない時代に老いる』(KADOKAWA)の著者で医師・小説家の久坂部羊氏が、がん検診の実情について解説します。
がんもどき仮説とは?
「がんもどき仮説」は、簡単に説明すると次のようになります。
がんは一個の細胞ががん化することからはじまり、それが増殖して診断がつくようになるまでは、何年もかかるので、転移するタイプは診断がつくまでに転移しているだろうし、見つかった段階で転移していないもの(イコールがんもどき)は治療の必要がない。
がんを診断するには、最低でも一センチ程度の大きさにならないと見つからず、その時点で細胞数は億単位になっているので、転移するものならすでに細胞レベルで転移しているというわけです。
近藤誠氏はこの仮説に立ち、これまで外科医が手術で命を救ったと思っている患者は、すべてがんもどきなので、手術をしなくても死ななかったと述べて、一大センセーションを巻き起こしました。
このとき外科医たちは激しく抵抗しましたが、手術しなければ患者は死んでいたということは証明できず(すでに手術をしているので)、歯ぎしりしながら地団駄を踏むか、無視を決め込むか以外になかったのです。
私はこの仮説を肯定はしませんが、否定するのもむずかしいと感じています。なぜなら、がんの悪性度の判定は現代の医学ではできないからです。