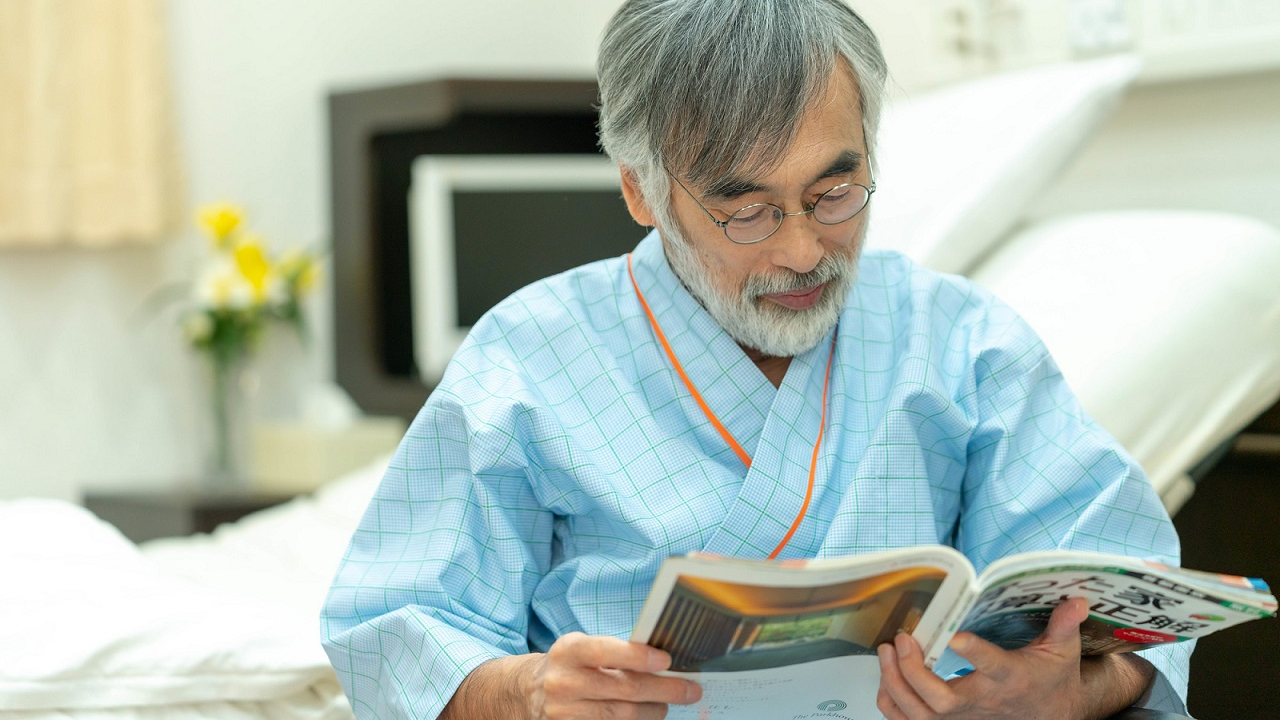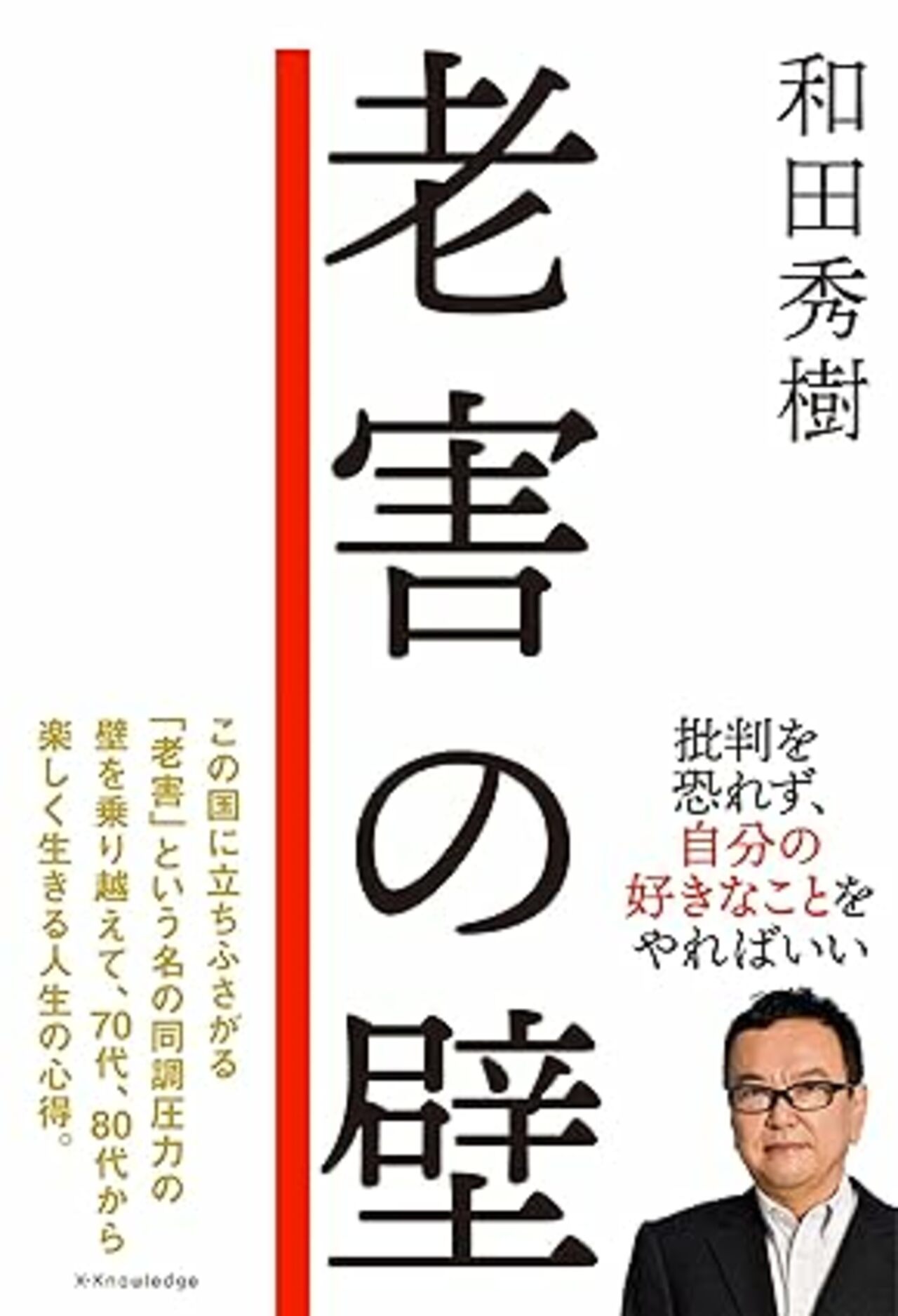日本には、年金暮らしをしている高齢者に対して「ぜいたくをせずに慎ましい生活を送るべきだ」という同調圧力があるものの、本来は高齢者こそお金を使うべきだと、和田秀樹氏はいいます。その根拠について、和田氏の著書『老害の壁』(エクスナレッジ)から詳しくみていきましょう。

「年金暮らしがぜいたくするな」→無視してOK…60代以上の高齢者こそ「お金を使うべき」といえる理由【東大卒医師の見解】
高齢者こそ、お金を使うべきといえる理由
日本には終身雇用制とか年功序列という優れたシステムがありました。定年まで雇ってもらえるという安心感があるから、ローンが組めるわけですし、ボーナスをローンに組み込むことができます。また、年功序列というのは、子どもが進学するとか、お金がかかる年代ほど給料が高くなるというシステムですから、とても理にかなったよい制度です。
ところが、真面目に働いている人と比べて、生産性が上がらない労働者がいるからと、このシステムをやめてしまいました。でも、雇用のシステムを変えたからといって、これ以上、生産性は上がることはないでしょう。
生産が過剰なときはどうすればよいのでしょうか。お米の生産調整のことを覚えていますか。戦後、お米の生産量は飛躍的に伸びましたが生産過剰になったため、政府は1970年に生産調整を始め、それが減反政策へとつながっていきます。
でも米農家は生産しないと収入が得られません。そこで政府は、減反の見返りとして手厚い補助金を与えることにしました。今の消費不況はそれと同じことです。
資本主義という経済システムは、放っておくと、ひたすら生産性を上げようとするから、いずれ莫大な消費不況が起こると予言したのは、近代経済学者のケインズです。だから、消費をどれだけ増やすかというのは、ケインズ以来の重要なテーマなわけです。
消費を増やすには、所得の再分配しかありません。これはケインズも言っていますし、トマ・ピケティなどの最近の経済学者も言っています。
年収300万円の人は、300万円をほぼ消費します。でも、年収1億円の人は年間1,000万円くらいの消費でも十分生活できます。となると、お金のあるところから、ないところに回さないと消費は増えません。これが所得の再分配です。ようするに、お金持ちに対する累進課税を強化するということですが、「新しい資本主義」などと言っている今の日本では難しいでしょうね。
いずれにしても、消費不況時代の消費者はありがたい存在。「消費者は神様」といってもよいでしょう。
「年寄りのくせにぜいたくするな」といった世間の圧力に負けてはいけません。高齢者こそ、もっともっとお金を使って、快を求めて生きるほうが国のためなのです。
老後を元気に過ごすためにいま壊すべき「壁」
現代ほど高齢者が生きにくい時代はないでしょう。かつて、高齢者は敬われた存在だったのに、今まで述べてきたように、「年寄りは運転するな」「年寄りは家でおとなしくしていろ」「タバコは吸うな」「酒は飲むな」「毎日スナックに行くな」「いい年をしてヌード写真なんか見るんじゃない」「ぜいたくはするな」と、世間や家族が同調圧力をかけてきます。
でも言われるままに生活していたら、どんなひどい結果になるかは、よくわかっていたのではないでしょうか。快は奪われるし、健康も損われるし、筋肉が落ちて足腰も弱るし、結果的に早死にすることにもなりかねません。
まずは自分の意思を貫き通すことが大事です。「それをやったら、老害と呼ばれてしまう」と恐れることはありません。老害なんて気にする必要はないのです。老害の壁は「壊すべき壁」です。
そして老害の壁を壊したとき、みなさんはもっともっと楽しく、60代後半、70代、80代を元気に過ごすことができるようになるでしょう。
和田 秀樹
精神科医
ヒデキ・ワダ・インスティテュート代表