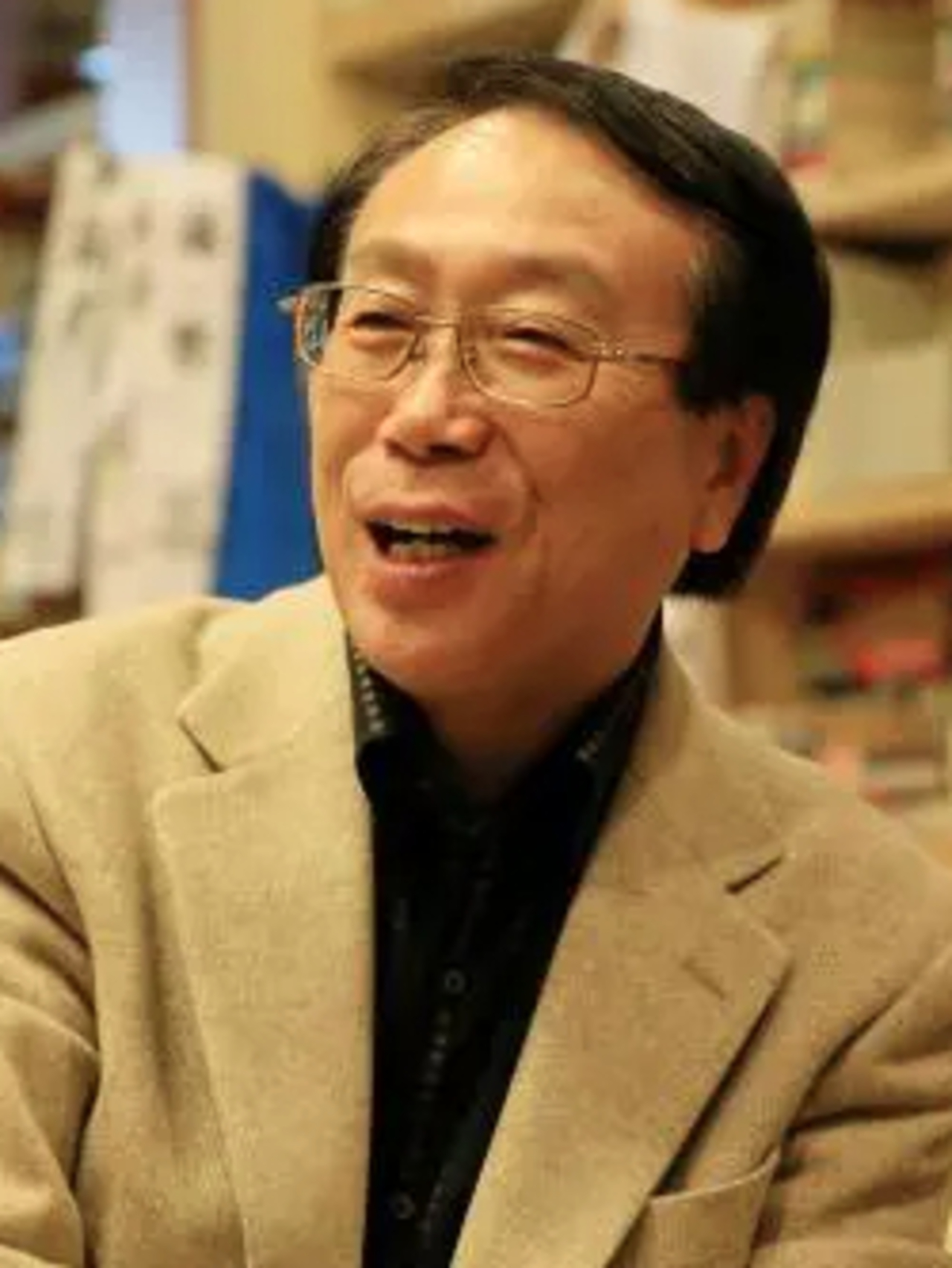温泉に入るとき、どれだけ「入浴マナー」を意識しているでしょうか。入浴における作法は「科学的にも精神的にも理に適っている」と、温泉学者であり、医学博士でもある松田忠徳氏は言います。松田氏の著書『全国温泉大全: 湯めぐりをもっと楽しむ極意』より、特に“源泉かけ流し”の温泉で重要な「入浴マナー」を詳しく見ていきましょう。

中高年男性は特に注意…温泉で〈入浴客の約5割〉がやっている“マナー違反”とは【温泉学者が“正しい入浴法”を解説】
1泊につき「入浴は3回」が目安
江戸中期随一の医学者、香川修徳は温泉学の大家でもありました。彼が著したわが国初の温泉医学書『一本堂薬選』続編(1738年)は、温泉論としての内容も備えた書物ですが、入浴法にもふれています。
「入浴は1日に3回から5回を基準とする。身体の弱い者は2、3回とするべきであろう。強い人はあるいは6回から7回に及んでも害はない。これを過ぎては疲労する」
せっかくの温泉だからと、何回も風呂に入ってのぼせてしまった、という経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。過度の入浴を江戸時代から “欲浴”と称していましたが、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」という言葉があるように、むしろマイナスになります。
香川修徳以降の江戸から明治にかけての温泉論、入浴論でも、入浴回数として3、4回としているものが大半です。しかも当時の温泉浴は病気を治癒するための「湯治」目的であることを考えると、今の時代は1泊の温泉旅行で宿泊日に2、3回、翌朝1回で十分でしょう。私の場合はチェックインした後に、温泉街の外湯(共同湯)、就寝の1時間ほど前と翌朝に宿の風呂に入ります。食前食後、とくに食後は1時間は空けてから入浴します。
温泉浴は想像以上に体力を消耗します。源泉かけ流しの“湯力”のある温泉に浸かると、新陳代謝が促進されかなり体力を消耗するものです。具体的には縄跳びを5分間したときの消費カロリーは約17キロカロリーですが、温泉に5分間じ~っと浸かるだけで約16キロカロリーも消費します。ちなみに5分間のウォーキングでは約7キロカロリーです。驚かれたことでしょう。
ですから、「温泉に入るとスリムになる」といわれるのです。実際には温泉に入ると胃腸の働きが良くなるものですから、食が進んでむしろ逆のことの方が多いのですが――。久々の温泉旅行ではこればかりは仕方のないことですよね。
先に朝風呂に入ると書きました。気をつけたいのは、起き抜けの入浴は避けましょう。身体の機能がまだ活発でないため、急に熱い湯に浸かるのは危険だからです。とくに冬場の起き抜けは、体温が低下しているので要注意です。