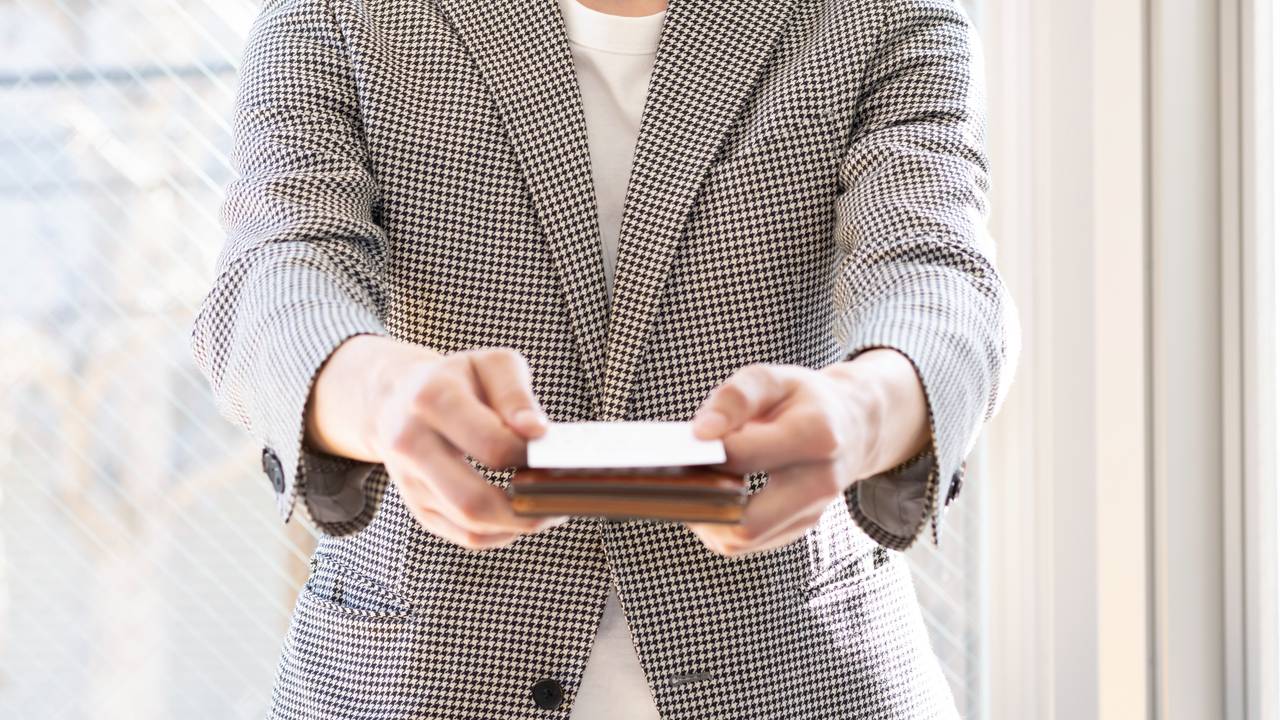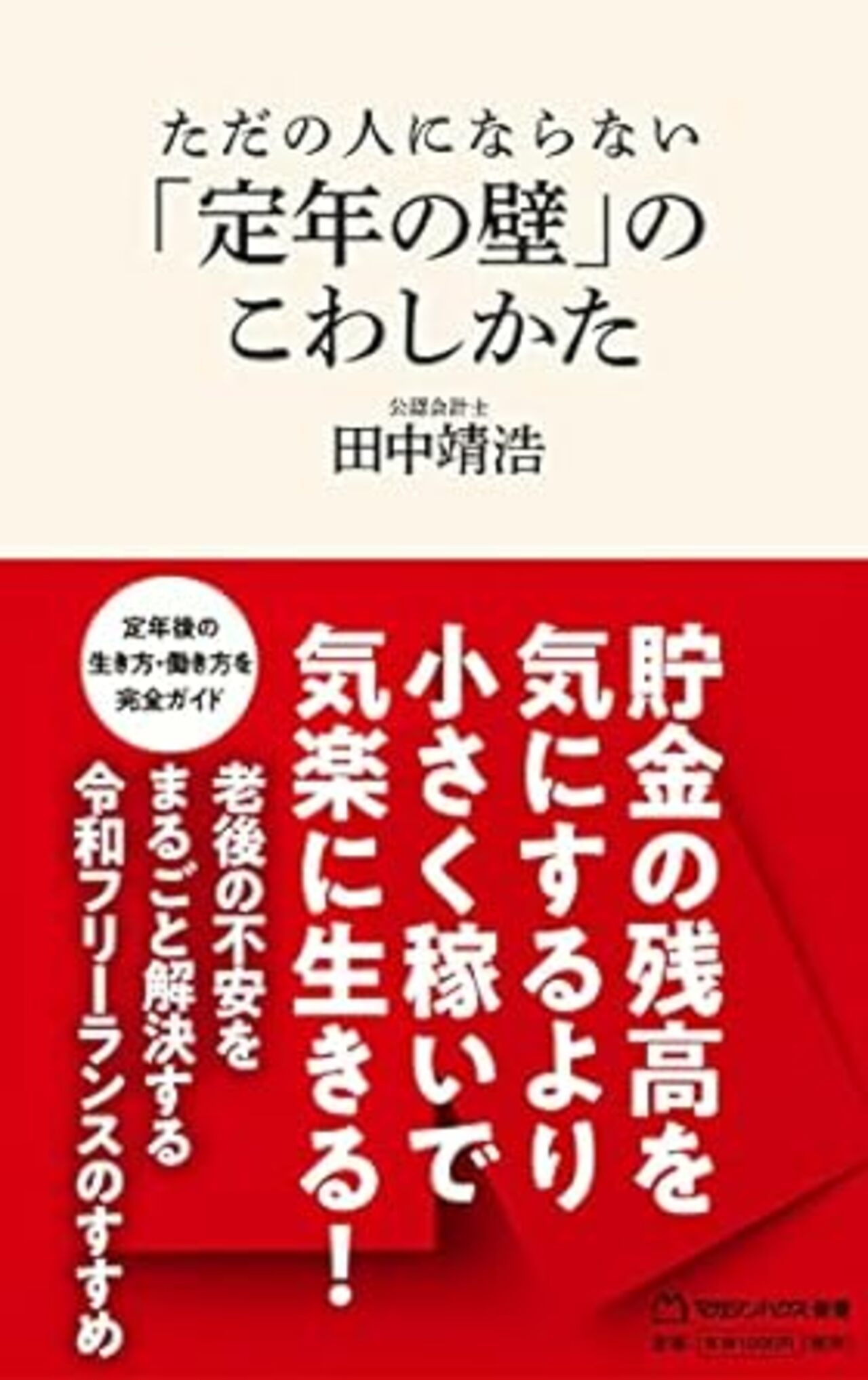定年後の生活について、不安を抱いたことがあるという会社員は多いでしょう。そこで、『ただの人にならない「定年の壁」のこわしかた』(マガジンハウス)の著者で公認会計士の田中靖浩氏が「老後の金銭的な不安」を解消すべく、“貯金”でも“投資”でもない「新たな選択肢」を紹介します。

定年までに蓄えはいくら必要?「老後2,000万円問題」を解決する“貯金”でも“株式投資”でもない「第3の選択肢」【公認会計士が解説】
定年までに貯金はいくら必要か?
長い間安泰だったサラリーマンの老後に不穏な気配が漂っています。
「なんとかなるさ」と高を括っている人がいまだ多数派である一方、「このままで良いのだろうか」と不安を感じている人が増えています。
じわじわ迫る不安感の背景に「この国にはサラリーマン・公務員が多い」事情があります。
サラリーマンや公務員といった勤め人は、定年によって「働くのはこの年齢まで」と区切られます。自分は働きたくても年齢によって強制終了させられるのがサラリーマン・公務員の特徴です。
そんな強制終了があっても文句が出なかったのは、その後に十分な退職金と年金が用意されたからです。それに加えて現役時代に貯金をしておけば、少々の贅沢だってできる。だからみんな定年を受け入れてきたのです。
人の一生を「第1期:子ども期、第2期:大人期、第3期:老人期」に分けるなら、サラリーマン・公務員の生き方は「第1期:子ども期」に勉強して良い会社・組織に入り、「第2期:大人期」をそこで働きながら過ごす。「第3期:老人期」は第2期に蓄えた財産の取り崩しで生活する──と、そんな一生です。
老後の生活になんとなく不安を感じるサラリーマンは第2期のうちに「貯金」しようと考えます。ここで悩ましいのは「定年までにいくら貯金すべきか?」がわからないことです。
老後資金2,000万円問題は“単なる試算”だが…
もともと定年後に向けて関心の高かった「定年後に必要な貯金問題」ですが、これに世間の注目が一気に集まったのが「老後2,000万円問題」。
2019年、金融庁金融審議会「市場ワーキング・グループ」が公表した報告書の「老後に向けて2,000万円の蓄えが必要」の部分がクローズアップされました。金融庁の名とともに「2,000万円」という金額が大げさに報じられ、ワイドショーなどで取り上げられる騒ぎ。これが「炎上」狙いなら大成功ですが、そうではなさそうです。
報告書を読むと2,000万円は試算にすぎません。老後までにどれだけ蓄えればいいのか。その金額は本人の退職金、家族数、生活ぶりなどによってまったく異なります(報告書にもその旨が明記されています)。
2,000万円は「夫婦で月5.5万円不足するとしたら30年で2,000万円不足」という計算にすぎません。ただ、この「2,000万円問題」が話題になったことには理由があります。