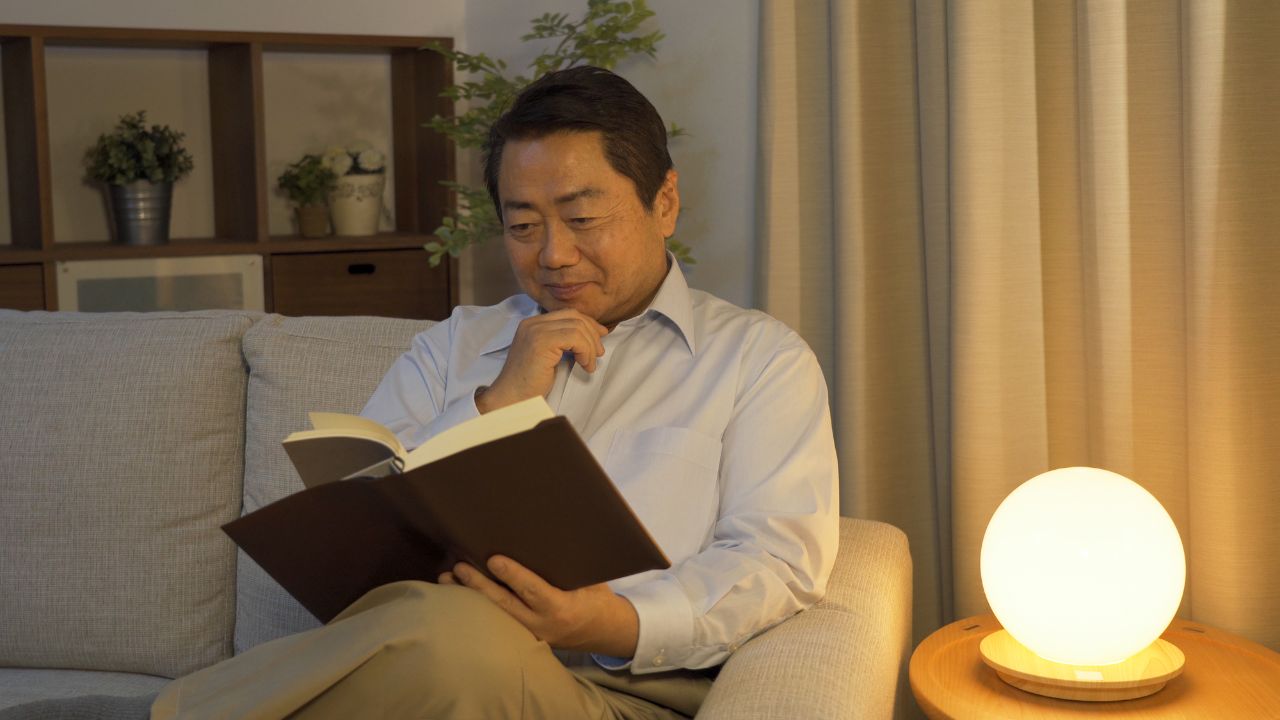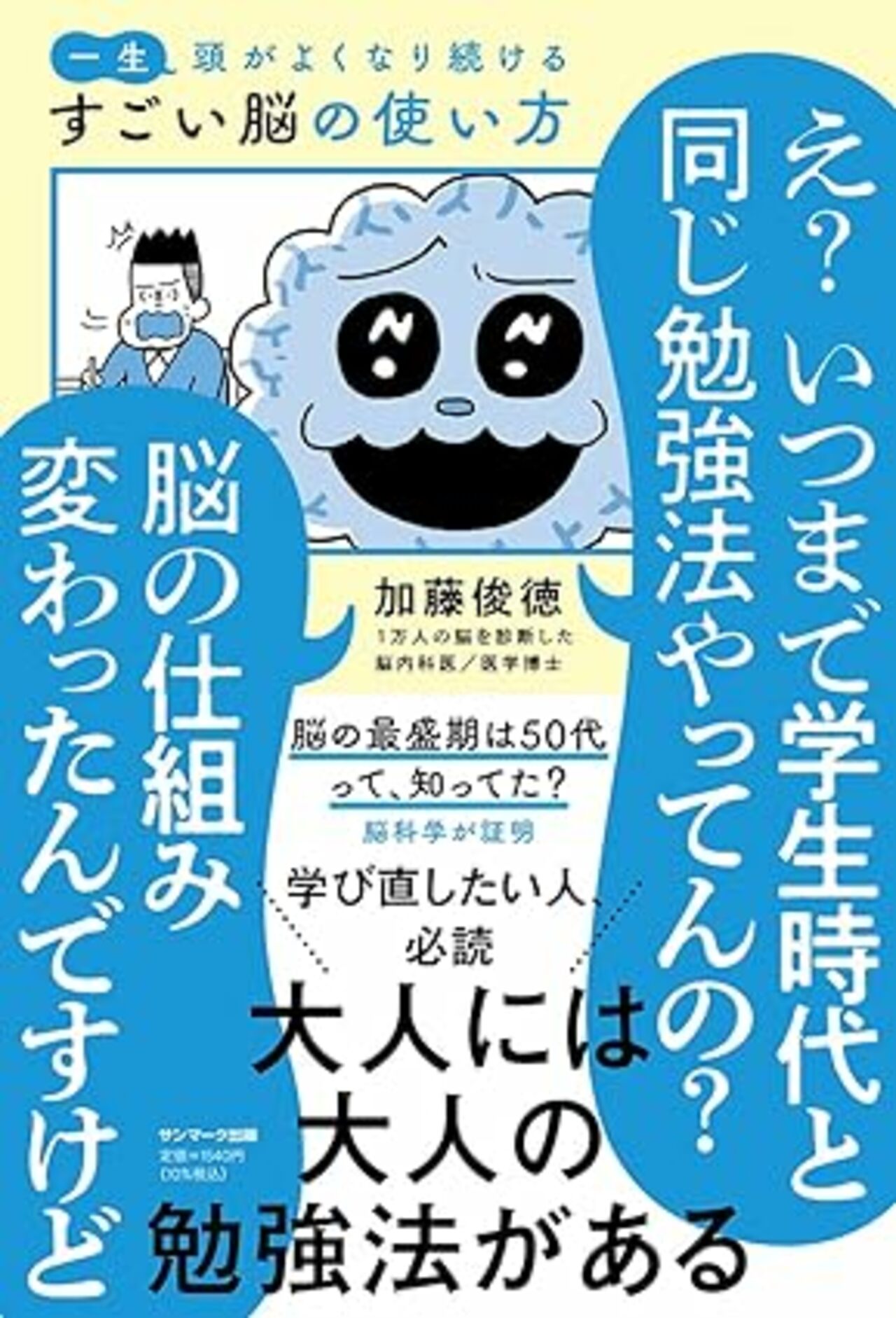勉強そのものを好きではなくてもワクワクした気持ちで勉強することで学習速度が2倍から4倍に跳ね上がると言います。その秘密は脳の海馬がら出る脳波にありました。著書『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』(サンマーク出版)より、 加藤俊徳氏が解説します。

大事なのはワクワク感と納得感!…「あんなに英語を勉強したのに喋れない」と嘆くあなたに試してほしい勉強法【脳内科医が解説】
「なるほど、わかった!」と理解できれば記憶に残る
記憶の調整役・海馬をだまして長期記憶へのルートを開放してもらうテクニックは、ワクワクした気持ちで取り組むことだけではありません。
「なるほどね!」と理解すること。
これだけで理解系脳番地がしっかり働くことになるので、学んだことを無条件に長期記憶として保管することができます。
社会人になってからも学ぶ方が多い、英語を例にご説明しましょう。
日本の英語教育の弊害と言っていいと思いますが、なかなか文法が身につかず、苦労している人はたくさんいますよね。正直に言えば、私も苦労したうちの1人です。
そもそも文法は、相手に伝わるように話すための語順のルールで、日本の学校で重点を置いているのは、このルールを暗記することです。
つまり、記憶系脳番地に頼った勉強法を強いているのです。
学生時代のそういった経験から、大人の脳に切り替わっているにもかかわらず、丸暗記で文法を覚えようとしても覚えられるはずがありません。
なかには、学生時代に暗記を頑張って、文法もかなり覚えたというタイプの方もいるでしょう。しかし、テストの穴埋め問題に答えることはできても、いざ仕事の場面で使いこなすことができるかというと、そこでつまずいてしまう人も多いはず。頭のなかで文章を組み立てている間に話題はどんどん移り変わっていき、話の輪に入れないという悩みもよく聞きます。
英文法は話すためのルールですから、どういうシチュエーションのときにどの文法を使えばいいのかがわかること、これがいちばん大事です。
英文法に限らず、条例でも法令でも化学式でも、どの場面にこの知識を活かすのが適切か理解系脳番地を働かせ、理解しながら学ぶのが正解。
なぜ、理解系脳番地を働かせながら学んだことが、自動的に長期記憶に送られるのかというと、理解するためにはこれまでに蓄えてきた情報を記憶の保管庫から引っ張り出してきて、比較検討したり、新しい情報と結びつけて理解の幅を広げたりする必要があるからです。
このとき、過去に「これは重要」と判断して長期記憶に送った情報と関連するものは、やはり大事な情報である、と記憶の調整役・海馬はそう判断してくれるのです。