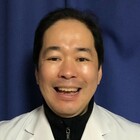(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
日本の小児科における「適応外使用」の現状
実は、冒頭で述べたとおり、小児科で使用される非常に多くの薬剤が「適応外使用」になっています。すなわち、筆者を含め、小児科医はそれぞれの経験則によって薬剤を処方していることになります。
ある調査によると、2001年4月~2015年3月に国内で承認された1,125の薬剤のうち、277(24.6%)の薬剤にしか小児適応が記載されていなかったと報告されています。
では、医薬品を適応外使用するとどういった不都合が生じるのでしょうか? 具体的には、以下のようなリスクが考えられます。
●有効性・安全性などの評価が不十分
……期待される効果が得られなかったり、予測しない副作用が発生したりする可能性があります。
●保険診療の対象とならない可能性
……自費診療となり、費用負担が増えるかもしれません。
●医薬品副作用被害救済制度の対象とならない可能性
……薬が原因で入院治療等が必要となった際に、医療費、年金等を給付する公的な制度の対象とならないかもしれません。
日本で小児に対する「適応外使用」が多い理由
1.小児の治験が困難
では、なぜこうしたリスクを抱えながら、「適応外使用」が続いているのでしょうか。その背景には、「小児の適応への難しさ」が挙げられます。
みなさんは「小児は大人のミニチュアではない」という言葉を聞いたことがありますか? 実は、成人において承認された薬を、そのまま小児に使うことは容易ではありません。たとえば、抗生剤の投与量や投与間隔は成人と小児で大きく異なり、単純に成人用の投与量を体重換算で小児に当てはめるだけではいけないのです。
また、成人と小児では薬の体内動態ひとつをとってもさまざまな違いがあります。体内での薬の動態の因子として吸収、分布、代謝、排泄がありますが、これらはすべて成長・発達の影響を受けるため、小児は成人よりも複雑です。
例として、体重に占める水分量の割合を考えてみましょう。生後すぐの新生児は約80%が水分ですが、加齢に従い徐々に低下し、12歳の時点ではほぼ成人並みの約60%程度となります。すなわち、体重換算で薬の量を決めると、体内での水分量が大きく違うので、薬の効き方も大きく変わってしまうのです。
小児の成長・発達について正しく理解し、適切な評価をする必要があります。したがって、単純に大人の薬を子どもにそのまま「適応内」にさせることはできず、追加の試験が必要となるのです。