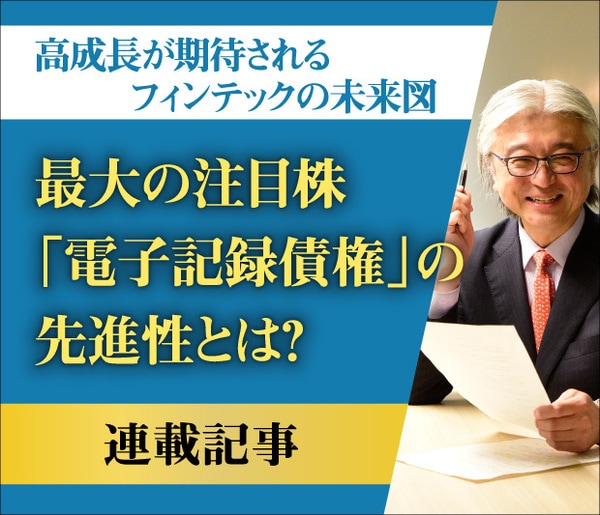契約書のひな型にも必ず入っている債権譲渡禁止特約
小倉 いまの民法でも、債権者は債権を譲渡できると書いてあります。しかし、当事者どうしが譲渡しないという合意(債権譲渡禁止特約)をしたら、譲渡したり担保に提供したりすること自体が無効になる、というのが法律の立て付けになっています。企業間の取引契約の中に、売掛債権の譲渡禁止特約が入っていると、それが金科玉条になってしまい、売掛債権を譲渡したり担保に入れたりすることが一切、できないわけです。
もちろん、民法では債務者側の了解をもらえばいいということにはなっています。絶対ダメではありません。しかし、売掛債権の債務者は一般には大企業で、その下請けである中小企業が、債権譲渡の承諾を頼んだりしたら、「あそこは資金繰りがやばいから取引をやめよう」となりかねません。

代表取締役研究所長
田中丸 修一 氏
田中丸 2000年当時、実際に売掛債権を担保に融資を受けた企業もありました。銀行も、中小企業のために良かれと思って売掛債権を担保に融資したのです。ところが、信用調査会社から「同社は債権を譲渡担保に取られた。したがって危機的な状況にあると推察される」といったコメントを出されてしまいました。まさに、信用不安情報の原因になってしまったのです。
小倉 商取引の契約書のひな型には、まず間違いなく売掛債権の譲渡禁止特約が入っています。特約でもなんでもありません。当事者も、そういう条項があることさえ意識していないのではないでしょうか。
田中丸 そもそもなぜ譲渡禁止特約を入れることになったのか。多くは、中小企業が大手企業に自社の商品を納入する取引契約を結ぶ局面から生じています。大企業は、中小企業から部材を購入する機会が多いのですが、相手はいつ倒産するかもしれないし、何が起こるかわからない。様々なリスクをなるべく事前に回避する契約にしたいと考えるのは当然です。
取引先の中小企業が経営不振になり、売掛債権が反社会的勢力などに渡って、ある日突然、「自分が債権者だから金を払え」といわれて支払うと、コンプライアンス上の問題になりかねません。そこで、債権譲渡禁止特約を入れようということになる。大企業にとっては自然な流れでしょう。いつ頃からそうなったのかは不明ですが、20年前、私がABLを扱い始めた時にはもう当たり前のように入っていました。
小倉 そもそも、企業同士では1回だけの取引というのはめったにない。通常は、恒常的な取引です。経理システムでも特定の支払先が登録されています。そこに、「今回は別のところに振り込んでくれ」といわれると事務処理のミスにつながりかねません。間違って送金してしまえば、返しもらえるかどうかも分からない。
また、売掛債権を担保に融資するには、金融機関との間での三者間契約が必要で、債務者である発注企業の経理部は印鑑を押さないといけない。とにかくリスクがあり、手続き的にも面倒ですから、経理部門は普通、「そんなことを言ってくる取引先は切ってくれ」というのです。
田中丸 金融機関の立場からしても、債務者の承諾について確定日付とかいろいろ法律的な条件があり、ただ印鑑をもらってくればいいというわけにはいきません。やはり面倒くさいとなっていったのです。
180度発想を転換した「債権法の改正」の中身とは?

小倉 しかし、今回の債権法の改正では、条件が揃う場合になりますが、債権譲渡禁止の合意があったとしても、債権譲渡そのものは有効であるということになりました。これまでとはコペルニクス的に180度、発想を変えたのです。売掛債権の譲渡禁止特約があろうが、金融機関としては法律上、担保として売掛債権を譲り受けることが可能になったのです。これは素晴らしいことです。
田中丸 ただ、問題もあります。債権法の改正案を検討していた法務省の審議会では、もうややこしいから譲渡禁止という考え方そのものを法律上、無効にしようという意見があったようです。しかし、それに対して、これまで多くの企業が債権譲渡禁止を有効なものとしてきたのに、ある日突然、それが無効であるということになると、非常に混乱するのではないかという声も上がりました。
そこで、経団連加盟企業などに譲渡禁止特約の必要があるかどうか、ヒアリングを行ったところ、多くの回答は「必要」というものでした。そうなると、さすがに譲渡禁止特約そのものを無効にするのも難しいとなった。中小企業金融の観点からは、債権譲渡は自由とするのがよい。他方、大企業を中心に譲渡禁止特約は維持してほしいという意見も重たい。
そこで、譲渡禁止特約があっても債権譲渡は有効とする。しかし、譲渡禁止特約も認める、というやや分かりにくい形で決着したのです。法務省の見解では、譲渡禁止特約という表現は、民法改正後は「譲渡制限特約」となります。法律上、どんな状態でも債権の譲渡は可能だからです。同時に、支払者である債務者を保護するため、譲渡制限特約に基づく抗弁を認めることになりました。
具体的には、債権譲渡を受けた新しい債権者から支払いを求められた債務者には、3つのオプションが与えられます。
第一は、債権譲渡を認めて新しい債権者に支払うこと。
第二は、債権譲渡制限の特約に基づく抗弁権を行使し、もとの債権者に支払うこと。
第三は、裁判所に供託すること。
いずれかを選べば、それで債務は消滅します。