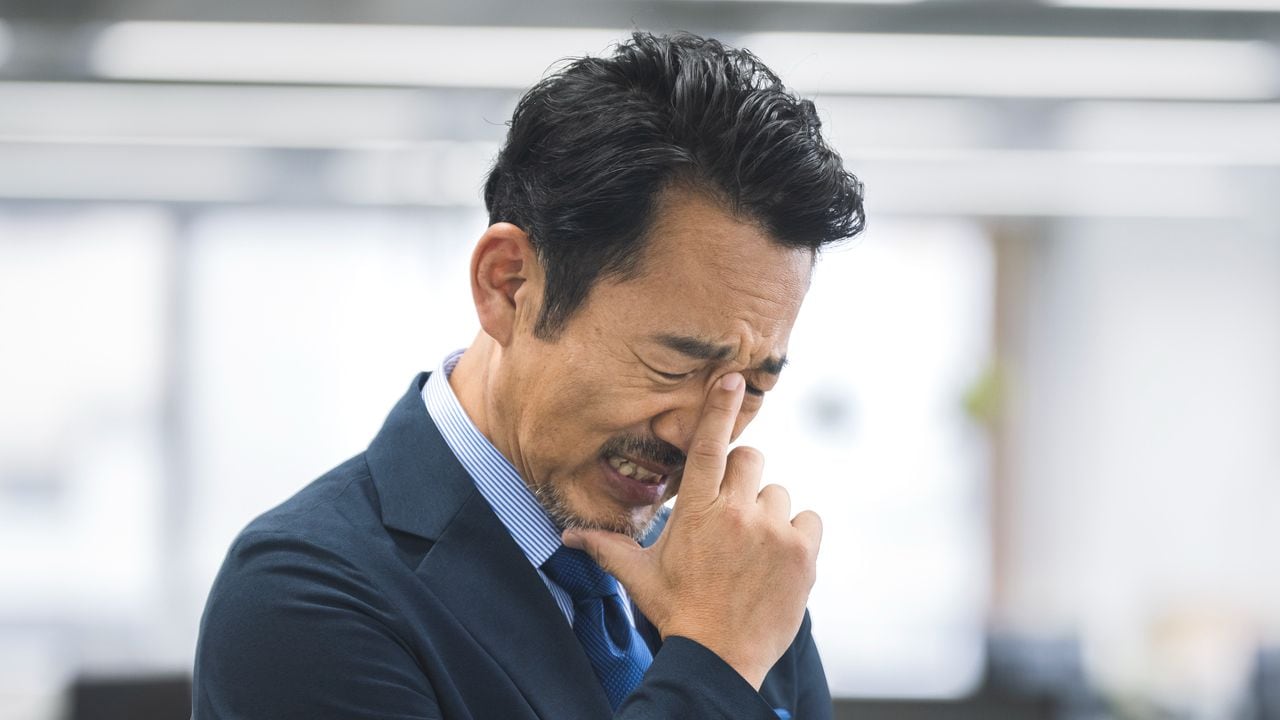 (※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
「元部長」という過去を捨てられず、組織の底辺に沈んだ男
大手建設会社の営業部長として、年収1,200万円を稼いでいた田中一郎さん(60歳・仮名)。60歳の定年を迎えた際、彼は迷わず再雇用の道を選びました。
しかし、提示された月収は28万円。額面の激減に愕然としましたが、「これまでの経験を還元してほしい」という人事担当者の言葉を、文字通り「アドバイザー的な立ち位置」だと解釈し、現場に残る決意をしました。
しかし、再雇用後の実際の仕事は「庶務」でした。若手が多忙で放置している備品整理や、会議室の片付けを命じられるたびに「何かの間違いだろ……。俺の経験を何だと思っているんだ」と心の中で毒づいていました。
そんなある日、田中さんはいつものように、若手社員たちが集まるフロアの片隅で、古い資料のPDF化作業をしていました。そこで耳に入ってきたのは、かつての部下である課長が、トラブル対応で疲弊し、孤立している様子でした。
かつての田中さんなら「俺が代わって交渉してやる」と口を出していたでしょう。しかし、今の自分にその権限はありません。田中さんはふと思い立ち、指示されたわけでもないのに、その課長が翌日の会議で使うであろう膨大な関連資料をあらかじめ整理し、要点を付箋でまとめてデスクに置きました。
「翌朝、彼が『田中さん、これ助かりました。昨夜はこれを作る余裕がなくて……』と、久しぶりに私の目を見てお礼を言ったんです。部長時代の『ご指導ありがとうございます』という社交辞令ではなく、一人の同僚としての、等身大の感謝でした」
田中さんは気づきました。
「かつては、彼らを思い通りに動かすことが私の仕事でした。でも今は、彼らが気持ちよく動けるようにすることが私の役目なんだと、再確認できた。面倒なプライドが邪魔をして、自分の役割が見えていませんでした」
それからの田中さんは、文字通り「最高の雑用係」に徹するようにしたといいます。備品が常に整い、資料が先回りして用意されている。田中さんがいるだけで、チームの事務的ストレスが激減しました。かつての部下たちも、今では「田中さん、ちょっと相談いいですか」と、現場の愚痴や悩みをこぼしに来るようになりました。
「上司ではないからこそ、彼らの本音が聞ける。今の私は、部長だった時よりも、組織の『潤滑油』として機能している実感があります」









