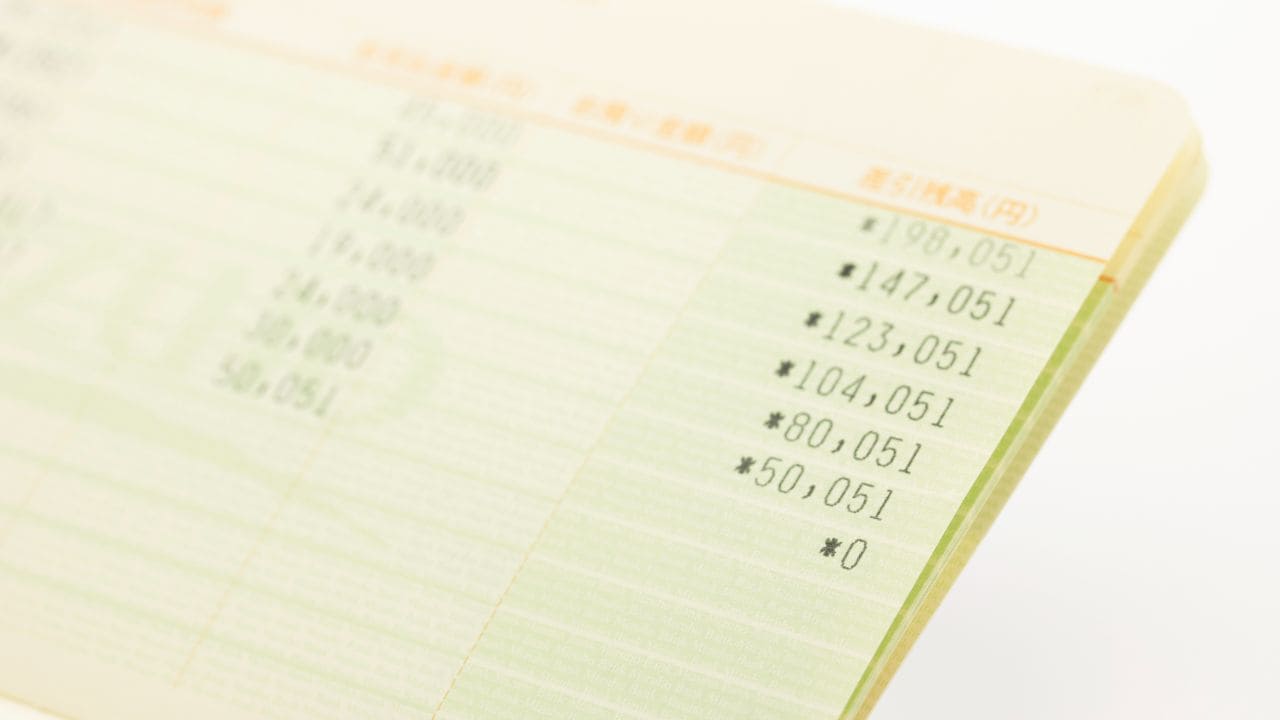 (※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
「お金がない」!は、長い年月をかけて忍び寄る
A夫婦の家計に、目に見える「大きな無駄遣い」はありませんでした。むしろAさんもBさんも、堅実に暮らしているという自負があったほどです。外食は月に1〜2回程度。ブランド物には興味もなく、海外旅行も数年に一度。それでも家計は、じわじわと崩れていました。
「見えない支出」の正体
「子どもたちには不自由させたくない」
「せっかく都内に住んでいるのだから、ある程度は便利さも大事」
そんな思いが重なり、教育費や住居費に加え、日常生活も“そこそこ快適”をキープ。
・中学受験のための塾代:年間100万円以上
・私立高校・大学の学費と仕送り:計1,000万円以上
・住宅ローンの月々返済:約17万円
・マイカーの維持費:年間約40万円
・親の介護費用:週2回の訪問介護+デイサービス利用
気づけば、生活を“回す”ことにすべての収入が吸い取られ、手元にお金が残らない体質になっていたのでした。夫婦の共通認識は、
「まだなんとかなる」
「子どもが卒業すれば、楽になるよ」
「ローンもあと少しだし……退職金で一気に返そう」
「年金もあるし、老後はなんとかなるさ」
A夫婦は、お互いに“なんとなく”安心していました。けれど、その「なんとなく」が、もっとも危険なサインだったのです。定年退職のあと、生活は一変しました。Aさんの退職金で住宅ローンを完済。子どもたちへの支援、Bさんの母親の介護費用も継続。そのうちの半分以上が、わずか1年半で消えていったのです。
「貯金って、使い始めると早いのね……」Bさんがつぶやいた言葉に、Aさんは返す言葉がありませんでした。
安心できる暮らしは、感覚ではなく設計でつくる
A夫婦の事例から見えてくるのは、「高収入でも安心できない家計」が、誰にでも起こりうるという現実です。ここではA夫婦の状況を分析し、見落とされがちな3つのポイントを整理します。
視点1:支出の「見える化」とライフプラン設計
A夫婦は、教育費や住宅費、介護費用など、支出の多くを「必要経費」として把握していたものの、それが家計全体でどれだけの比率を占め、将来どのような影響を及ぼすかまでは把握していませんでした。ポイントは、「いま、なにに、いくら使っているのか」だけでなく、「将来、なんのために、いくら必要か」を明確にしておくこと。家計簿が続かなくても構いません。最低限、「固定費・変動費・特別な支出」に分けて可視化し、将来の支出予測(ライフプラン)と照らし合わせることが重要です。
視点2:貯蓄と投資の優先順位づけが不在
A夫婦は、子どもたちへの教育支援や生活水準の維持を優先するあまり、「将来の自分たちのためのお金」をあと回しにしてきました。つまり、“貯めるべき時期に貯めなかった”ことが最大の失敗だったのです。特に40代〜50代前半は「貯蓄のゴールデンタイム」で、子育てや住宅ローンのピークと重なる反面、収入も最も安定する時期。この時期に老後資金の積み立てを意識的に行っていたかどうかが、60代以降の生活に大きな差を生みます。さらに、超低金利時代においては「貯蓄だけ」では資産は育ちません。投資信託やNISA、iDeCoなども活用し、長期的に資産を“働かせる”発想が必要です。
視点3:「退職金があるから大丈夫」という過信
「退職金でローンを完済して、あとは年金でなんとかなるだろう」A夫婦のように、退職金を“最後の砦”と考えている人は少なくありません。しかし実際には、退職金は一時的な資金であり、長期的な生活費や医療・介護費をカバーし続けるには不十分なケースが多いのが現実です。また、まとまったお金が入ると「安心して使ってしまう」心理が働き、必要以上に生活費が膨らむことも。退職金は“残りの人生のライフライン”であることを理解し、計画的に配分する必要があります。









