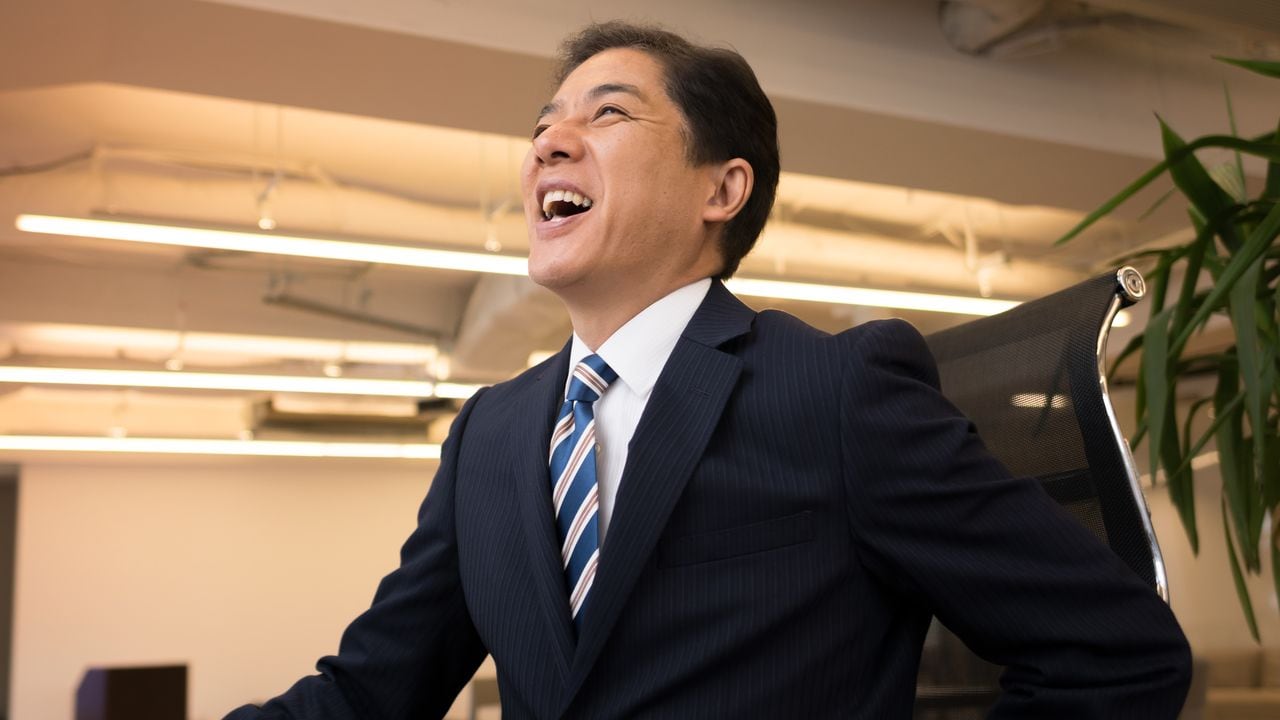 (※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
2025年度の年金の支給額と将来の年金不安
公的年金の支給額は物価と賃金の変動に応じて年に1回改定となります。2025年度の支給額は、去年の物価上昇率が2.7%、過去3年間の名目賃金の上昇率が2.3%になったことを受け、1.9%引き上げることを決定。老齢基礎年金は月額69,308円と、前年度から1,308円増えて、3年連続の上昇となりました。しかし、将来の年金の給付水準を確保するためのマクロ経済スライドにより、引き上げ率は賃金の伸びより0.4%低く抑えられ、実質的に目減りとなります。
また5年に1度行われる昨年の財政検証では、現役世代の平均収入を100として、夫婦2人のモデル世帯が受け取る年金額の割合である所得代替率が示されました。2024年度は現役世代の平均年収37万円に対して、モデル世帯の年金額は22.6万円、所得代替率は61.2%。そして2037年度、経済成長率が1.1%の場合、所得代替率は57.6%。経済成長率マイナス1%の場合、所得代替率は50.4%、経済成長率マイナス0.7%の場合、50.1%と予想。プラス成長であれば6%程度目減りにとどまるものの、マイナス成長の場合、2割目減りという未来が確実視されています。
将来、年金がもらえたとしても、当てにすることはできないかもしれない……そんな未来にただ不安になるしかありませんが、そんななか、「私は大丈夫。たとえ年金がなくても余裕です」と胸を張る加藤浩介さん(仮名・58歳)。公務員の定年は現在段階的に延長中で、昭和41年生まれの加藤さんの場合、64歳が定年になる予定です。
安定感は誰もが認めるところの国家公務員。加藤さんの現在の月収は50万円ほどだといいますが、国家公務員の定年退職後の生活は決して楽とはいえません。人事院の調査によると18.2%、約2割の定年退職した国家公務員が「生活が苦しい」と回答しています。一方で加藤さんは、「定年後に不安はありません。しっかりと資産運用をしてきたので」といいます。









