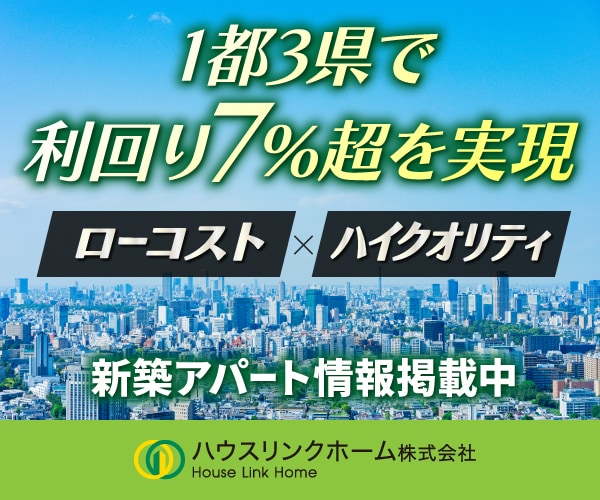大人気の新築木造1棟アパート「カインドネスシリーズ」資料請求はコチラ>>>
サブリースとは?その仕組みと種類
「サブリース」は、多くの不動産オーナーの間で活用されている賃貸経営戦略の一つです。サブリース(sub lease)を直訳すると「又貸し」、すなわち「転貸」という意味になります。転貸というと賃貸借契約上は禁止事項になっていることが多いため、オーナーにとって不利益につながるような悪いイメージに受け止められがちです。
不動産投資におけるサブリースとは、その多くが、不動産管理会社が物件購入者(=オーナー)からその物件を借り上げ、さらに第三者へ貸し出すという仕組みです。ここではまず不動産管理会社とオーナーとの間で賃貸借契約(=マスターリース契約)が締結され、さらに不動産と第三者(=実際の入居者)との間で賃貸借契約(=サブリース契約)が締結されます。この二重の契約関係が、オーナーのリスク回避対策として有効に働くのです。
不動産投資において最もリスクとなるのは「空室」です。入居者が引っ越してしまい空室になれば、当然ながら家賃収入はゼロになります。しかしサブリース契約が結ばれている賃貸物件は、空室になっても家賃収入が途絶えません。なぜなら、オーナーとマスターリース契約を結んでいる不動産管理が空室中も家賃相当額を支払い続けてくれるからです。
サブリースには、「家賃保証型」(入居中はもちろん空室時も家賃が支払われるタイプ)と、「パススルー型」(空室時や家賃滞納時は家賃収入が支払われないタイプ)の2種類があります。前者は不動産管理に支払う手数料率が家賃の10~20%相当額と高めになり、後者の手数料率は家賃の5~10%相当額と若干抑え気味になっています。昨今は前者の家賃保証型サブリースを提案する不動産管理が大半を占めているようです。
家賃保証型サブリースで仮に家賃を10万円とし、オーナーが不動産管理に支払う手数料率を20%とした場合、オーナーは毎月8万円の家賃収入が得られ、不動産管理には2万円の手数料が入ることになります。
大人気の新築木造1棟アパート「カインドネスシリーズ」資料請求はコチラ>>>
サブリースの「メリット」とは
サブリース最大のメリットは、賃貸経営における「空室への不安」を払拭してくれる点です。もちろんその他にも魅力はあります。それは、オーナーが入居者のプロフィールを確認して契約可否を判断したり、入居者と直接会ってやり取りしたりする必要がない点です。サブリースにおける賃貸借契約の当事者は入居者と不動産管理であり、オーナーはある意味「部外者」といっても過言ではありません。すべての入居者対応は不動産管理がやってくれるので、オーナーは本業に専念することができます。
もうひとつは、競合する賃貸物件とせめぎ合う心労がないことです。従来のオーナーは1日でも早く空室から脱したいがために、大枚をたたいて室内設備をリニューアルしたり、相場を激しく下回る激安家賃で入居者獲得を目指したりするもの。しかしサブリース契約を締結していれば、空室期間中も期日通りに家賃が入ってくるので、ムダな設備投資や家賃値下げの負い目に晒されることはありません。
大人気の新築木造1棟アパート「カインドネスシリーズ」資料請求はコチラ>>>
サブリースの「デメリットと注意点」
前述の通り、サブリース契約を締結すると不動産管理に対し5~20%程度の手数料を支払うことになります。たとえば家賃10万円で手数料が10%なら、1万円は不動産管理に渡り、オーナーの手元に残るのは9万円です。考え方によっては「毎月1万円の損失」とも取れます。しかもこの月額10万円という家賃が周辺相場より安い設定であったら、将来の売却価格にも悪い影響を与えます。
マスターリース契約の相手方である不動産管理を含め、賃貸借契約上の賃借人には「賃料減額請求権」が認められています。早期に空室を埋めることを条件に、不動産管理は大幅な家賃値下げを迫ってきます。どんなにリフォームしても建物自体の経年劣化は止めることができません。空室リスク回避のため、ある程度の値下げは仕方ないことかもしれません。
大人気の新築木造1棟アパート「カインドネスシリーズ」資料請求はコチラ>>>
サブリースは「やめておけ」といわれる理由
空室が長く続けば、サブリースを請け負う不動産管理も資金繰りが厳しくなり、最終的には経営破綻に陥ってしまう場合もあります。不動産管理の収益は、投資物件売買時の仲介手数料と、その後のサブリース契約手数料のみです。サブリースを請け負う不動産管理が経営破綻に陥る典型的なパターンは、新規オーナーから得た仲介手数料を既存オーナーの家賃保証に流用し、やがて資金が枯渇して倒産してしまうという至極単純なものです。
これから不動産投資を始めようという人たちに実践していただきたいのは、入口となる不動産管理の業務実績と資金力をしっかり吟味することです。これは大手の不動産管理だからといってないがしろにできることではありません。むしろ中小の不動産管理のほうが専門性の高いサービスが提供でき、投資案件やサブリース運営にも長けているかもしれません。規模を問わずできるだけ多くの不動産管理の門戸を叩き、運営要望や将来目標をすり合わせながら、自らの投資スタイルに合致した不動産会社を見つけていただきたいと思います。