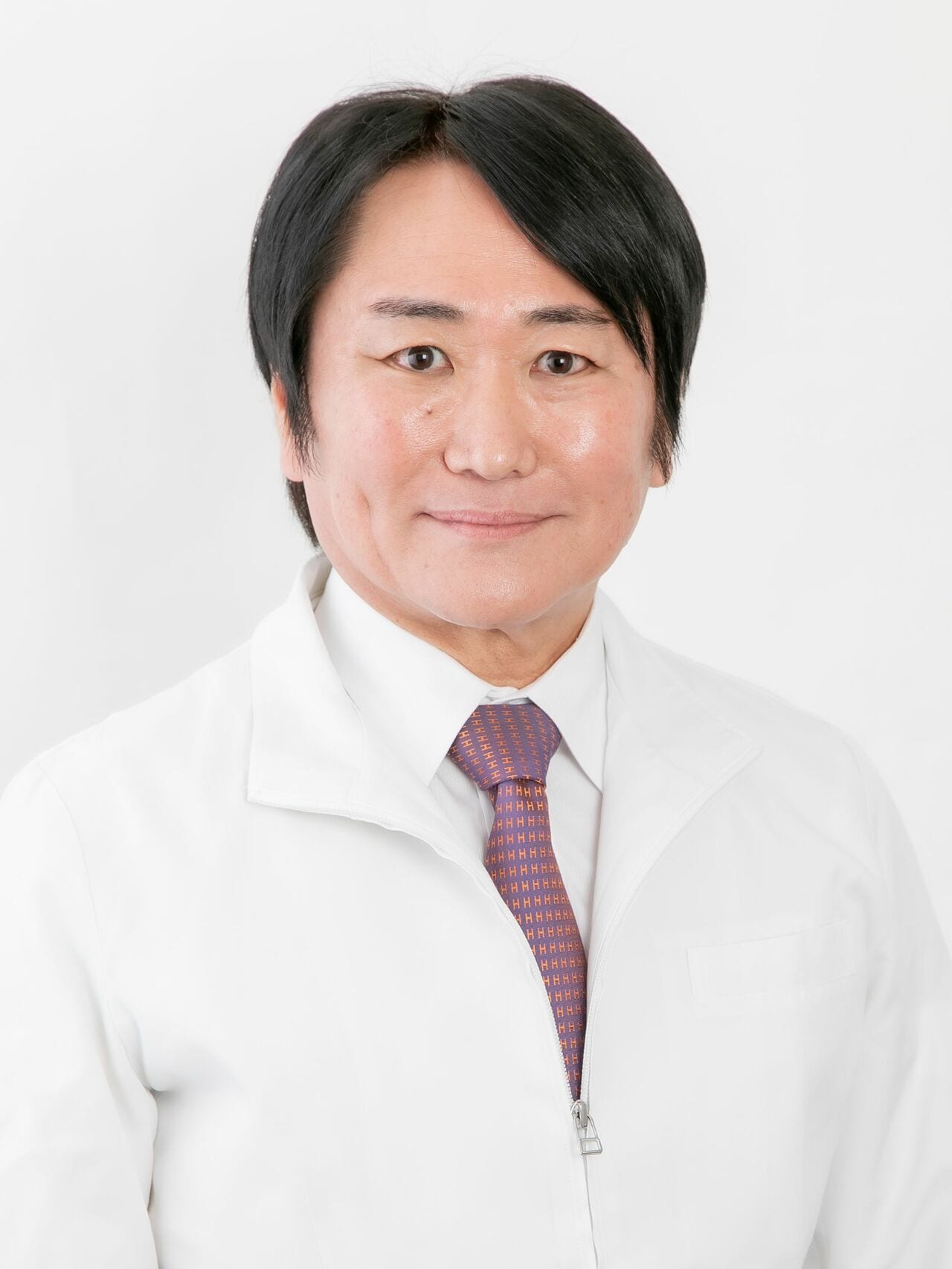春は歓送迎会が最も多く行われるシーズン。お酒を飲む機会が増えますが、飲酒する際にむせた経験はないでしょうか? もし、20代と比べてその頻度が高くなっている場合は要注意! 単なる加齢のサインではないかもしれません。40代・50代から始まるこの病気は、放置すると要介護・死亡リスクを高め、医療費負担の増加や生産性低下に繋がる可能性も。健康寿命を延ばし、活気ある経済社会を維持するためにも、早期対策が重要です。本記事では幸町歯科口腔外科医院院長の宮本日出氏が、意外と知られていない口腔機能に関する病気について解説します。

飲むときに、むせる…50代の2人に1人、発症4年後に死亡するリスクは2.1倍。疑うべき「恐ろしい病気の名前」【歯科医師が警鐘】
放置すると要介護・死亡リスクが高まる「恐ろしい病気」
要介護状態や死亡するリスクについて、40〜50歳代の方は「まだまだ先のこと」と考えていないでしょうか? しかし、40歳代の約4割、50歳代の2人に1人が、すでに要介護や死亡リスクが迫ってきている可能性があります。
お口の働き(口腔機能)には「食べる(咀嚼)」「嚥下(飲み込む)」「話す(会話)」などがありますが、これらの機能が低下すると「口腔機能低下症」という病気になります。病名を聞きなれない人も少なくないと思いますが、これは2018年に厚労省により指定された比較的新しい病気です(保険適用)。この病気の怖いところは、全身機能低下の兆候となることです。口腔機能は全身の衰えの前に低下するため、全身機能のバロメーターとして見逃せないのです。口腔機能が低下すると、低下していない人に比べ2年後に全身が衰える「フレイル」や「要介護状態」になるリスクが2.4倍になります。
そしてこの口腔機能の低下は、前述したように40〜50歳代から始まっているのです。しかし、対策はさほど難しくなく短期間で機能は向上するので、いかに早く対策を取るかが全身の衰えを防ぐポイントとなってきます。
「むせる」頻度が増えたら歯科に行くべき理由
口腔機能のなかで特に嚥下機能は大切で、嚥下機能が低下すると誤嚥性肺炎になる可能性が非常に高まります。この嚥下機能が低下し始めると最初に出てくるのが「むせ」なので、「むせ」が続くなら歯科医院で機能検査を受けてください。
ただし、以前よりむせるようになったというのは経験則からの判断になるので、自覚することは難しいかも知れません。なぜなら、小児期の口腔機能も関係するからです。最近は、小児でも口腔機能が十分に発達しなかったり、機能獲得が不十分だったりと、口腔機能の障害が急増しています(「口腔機能発達不全症」という病気です)。口が半開きになったいわゆる「お口ポカン」の状態が特徴的な症状で、意識して小児の口元を見ると意外に多いことに気づくと思います。当院の調査では半数以上の子どもが「口腔機能発達不全症」と診断されました(対象:391人)。
小児期の口腔機能は生涯にわたり影響をおよぼし、普通に生活をしているだけでは機能は正常になりません。子どものときに機能が低い人は大人になっても機能が低いまま。ほんの少しの衰えが始まる40歳代から口腔機能低下症になります。すなわち、20歳代でも機能が低い人はむせることが多く、年齢を重ねてむせる頻度が多少増えても機能低下の自覚は困難だというわけです。
口腔機能低下症の対策にいち早く取り組んでいる志木市(埼玉県)では、嚥下機能が衰えている人を対象に測定会・指導会・講演会などの行政事業を行っていますが、飲みこみに悩みのある人はわずか3%で、残り97%の人は機能低下に気づけていません。
これらのことを考慮すると、40歳からは年に1回は歯科医院で検査を受けて自分の口腔機能を確認することが肝要です。心配な方は、半年ごとに検査を保険治療として受けられるので、受診するとよいでしょう。