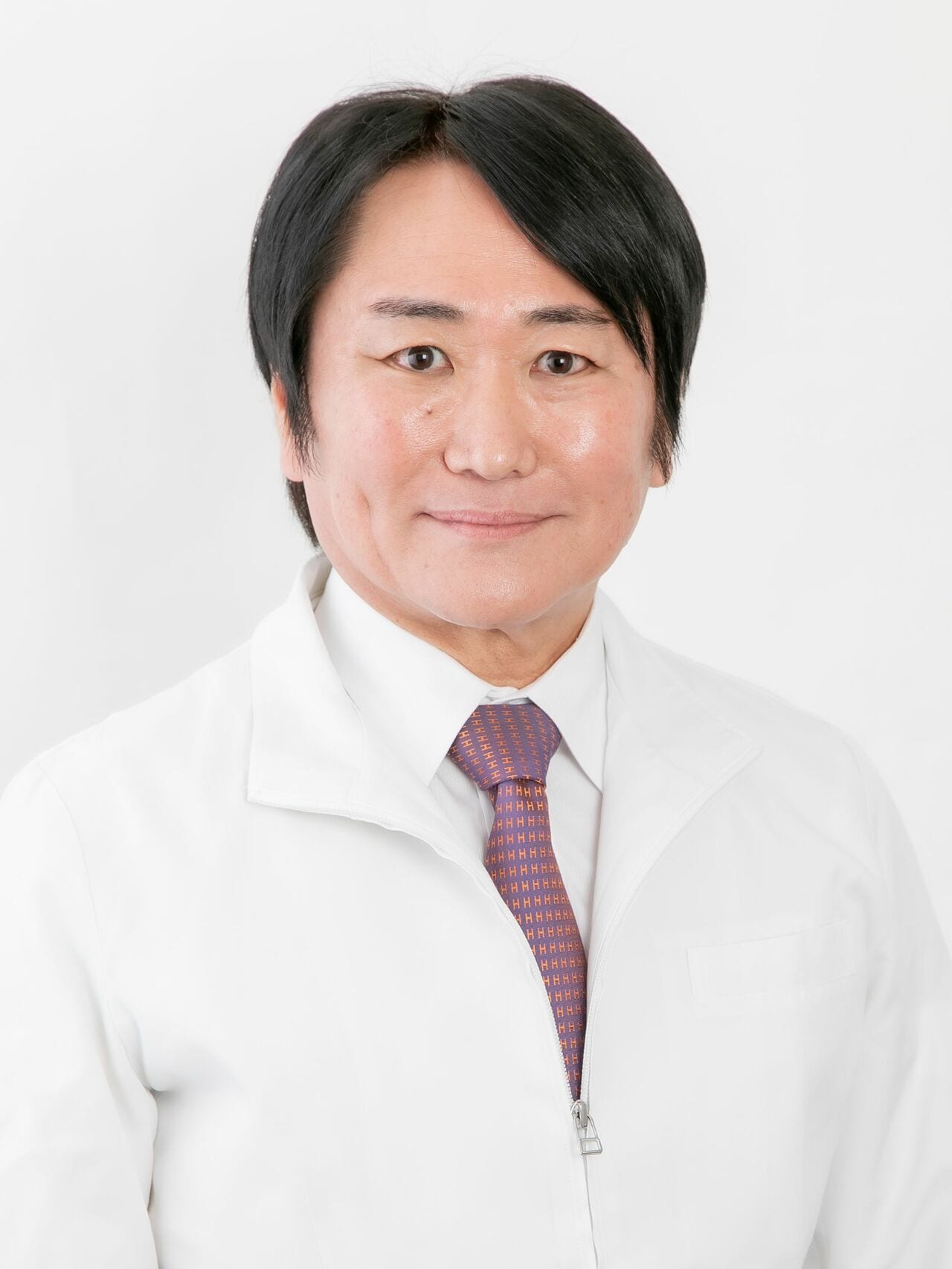「うちの子、食事の音が気になる……」そう感じている親御さんはいませんか? 子どもの「くちゃくちゃ食べ」は、叱るだけでは解決しません。しかし放置すれば、健康リスクを著しく脅かすだけでなく、将来的な医療費負担の増加にも繋がることから厚労省も注視している大きな問題なのです。本記事では幸町歯科口腔外科医院院長の宮本日出氏が、口腔機能低下がもたらす弊害について解説します。

「クチャクチャ食べる子ども」が増えている理由…大人になって命を危険に晒す可能性も【歯科医師が警鐘】
給食の安全性に関する議論と新たな視点
口腔機能と窒息リスクの関連性
昨年2月に福岡県で給食のうずらの卵を喉に詰まらせた事件がありました。その際には、
「うずらの卵の大きさが大き過ぎるので小さくすべきだ」
「給食の時間が短く、ゆっくりと食べる時間がないからだ」
「生徒が給食を食べている状況を先生が観察できる環境にないからだ」
といったさまざまな議論がなされました。確かにこれらを議論し、より安全な給食環境を築くことは大切だと考えます。一方、うずらの卵が給食に出るのは昭和の時代からです。給食の時間も以前とさほど変わらず、先生の給食時間の環境にも大きな変化はないように感じています。
この件で我々歯科医療界の立場から伝えたいのは、「口腔機能」に着目してほしいということです。食べる機能、つまり「咀嚼機能」が十分でないと食べ物を噛んで細かくできずに、丸呑み状態になります。さらに飲み込む機能である「嚥下機能」が不十分だとしっかりと飲み込めません。これらが重なり、食べ物を喉に詰まらせる可能性があるのです。
口腔機能の発達不全がもたらす影響
筆者がオーストラリアのアデレード大学時代に行った研究のなかで、咀嚼機能が弱くなると顎の骨の発達が悪くなることを発見しました。また顎の成長に左右で差が出て、顔が歪んでしまいました。日本での研究においては、顎の骨の大きさを左右で変えると、上手く食べられず、食事が口から漏れて十分な量を摂取することができないことも証明されました。つまり顎は、機能することで発達していくのです。
口腔機能の発達不全は顎の成長に影響をおよぼすだけでなく、歯並びも悪くします。歯並びが悪くなれば歯磨きが上手にできずに磨き残しが出て、むし歯の原因になり、大人では歯周病の原因にもなります。
また、食事も固いものが食べにくくなるため、自然と柔らかいものを好んで食べるようになりますが、柔らかい食べ物はビタミンとタンパク質が少ない傾向があり、栄養が偏りやすくなります。