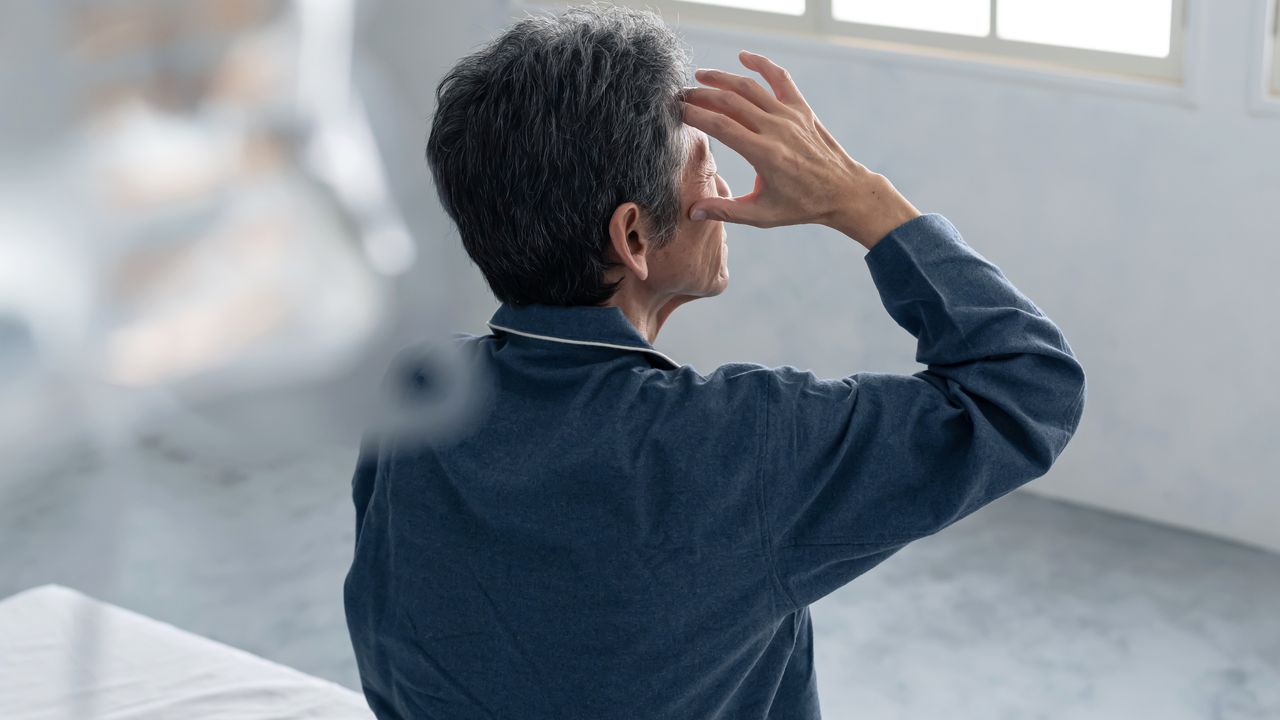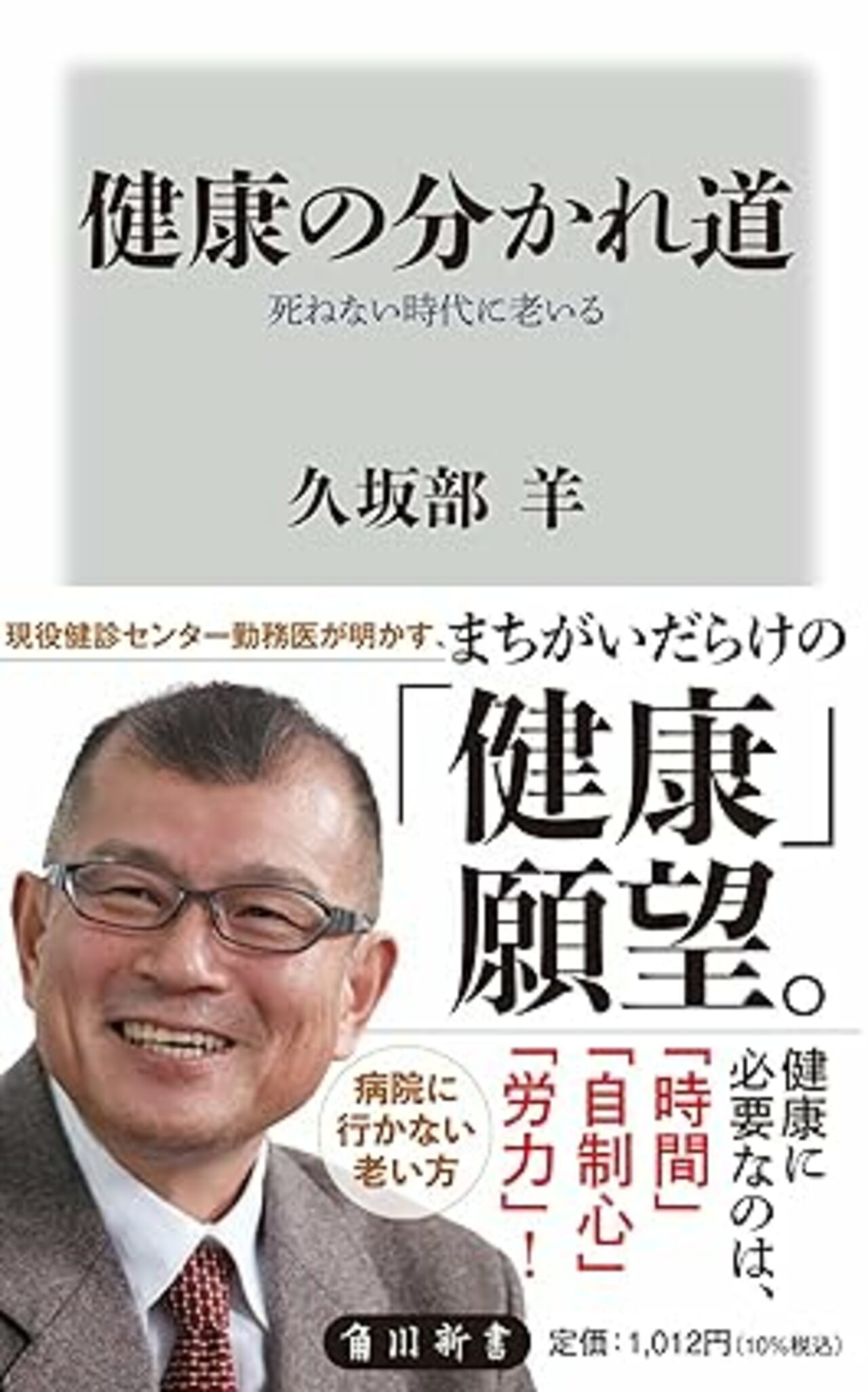戦後、日本人は自由・平和・豊かさを求めて努力を重ねてきました。ところが、それによって生じた弊害もあります。それは昔はなかった、新たな「生きづらさ」です。本記事では、『健康の分かれ道 死ねない時代に老いる』(KADOKAWA)の著者で医師・小説家の久坂部羊氏が、現代社会で精神の健康を保つ難しさについて解説します。
精神の健康を保つのは至難の業
肉体的な健康はもちろん、精神面での健康も大事です。いくら身体的に問題がなくても、心が病んでいれば幸せとはいえません。逆に、身体の病気があっても、精神面で満たされていれば、心は穏やかで幸福を感じることができるかもしれません。であれば、求めるべきは肉体の健康ではなく、精神の健康ではないでしょうか。
ところが、現代はこの精神の健康を獲得することが至難の業になっています。私はもともと精神科医ではありませんが、医学概論などの講義を受け持っていた福祉系の大学で、精神保健学の講義もしてほしいと頼まれ、一から勉強することになりました。
精神保健学は精神病学とはちがいます。精神病学は精神の病気を扱いますが、精神保健学は精神の健康をテーマにしています。
学んでみて驚いたのは、精神の健康を保つことが現代ではいかに困難かということでした。理由はやはり今の日本がむかしに比べ、自由で平和で豊かだからでしょう。そのせいで、国全体に過剰な優しさと思いやりが広がり、逆に精神的な満足が得にくくなって、心を病む人が増えているのです。もちろん、優しさも思いやりも大事ですが、過ぎたるは猶(なお)及ばざるがごとしです。
また、医学の進歩により、新しい概念が詳細かつ広範囲になり、かつては「ふつう」の辺縁に含まれていた人が、今は精神障害と判定されるようになりました。「発達障害」「適応障害」「学習障害」「人格障害」「注意欠陥多動性障害」「自閉スペクトラム症」「アスペルガー症候群」などと診断されると、それはレッテル貼りとなり、当人も周囲もそういう「障害」だと思い込むようになります。
私が医学生だった四十数年前は、精神科医が扱う病気は、「躁鬱病(現在の双極性障害)」「精神分裂病(現在の統合失調症)」、「てんかん」の三つが中心で、「神経症」はいわゆる「ノイローゼ」扱いで、さほど重視されていませんでした。
それが今や、患者が急増したことに伴い、心療内科とかメンタルクリニックとかいうジャンルで、多くの医者が治療に当たっています。対象となるのは、「パニック障害」「不安障害」「適応障害」「睡眠障害」「過食症」「拒食症」「アルコール依存症」「薬物依存症」「ギャンブル依存症」「新型うつ病」などです。
さらには、いわゆるひきこもりやいじめ、不登校、学級崩壊、家庭内暴力、虐待、自傷行為、数多のハラスメント被害、SNSでの攻撃、誹謗中傷などは、精神の不健康に留まらず、場合によって自殺にまで人を追い詰めます。
かつて、日本が非民主的で封建的だったころには、不自由で戦争もあり、貧しい人が多かった代わりに、ここまで挙げたような状況はさほど問題にはなっていませんでした。社会の側に配慮する余裕がなかったこともあるでしょうが、多少の異常があっても、本人も周囲もそれはそんなもんだと思い、いたずらに状況を悪化させることが少なかったからだと思います。
医学が進歩し、社会が苦しんでいる人により細やかに配慮するようになったのはよいことですが、そのことによって新たな問題も発生したのは、進歩が常に孕む〝業〞ともいうべきものでしょう。