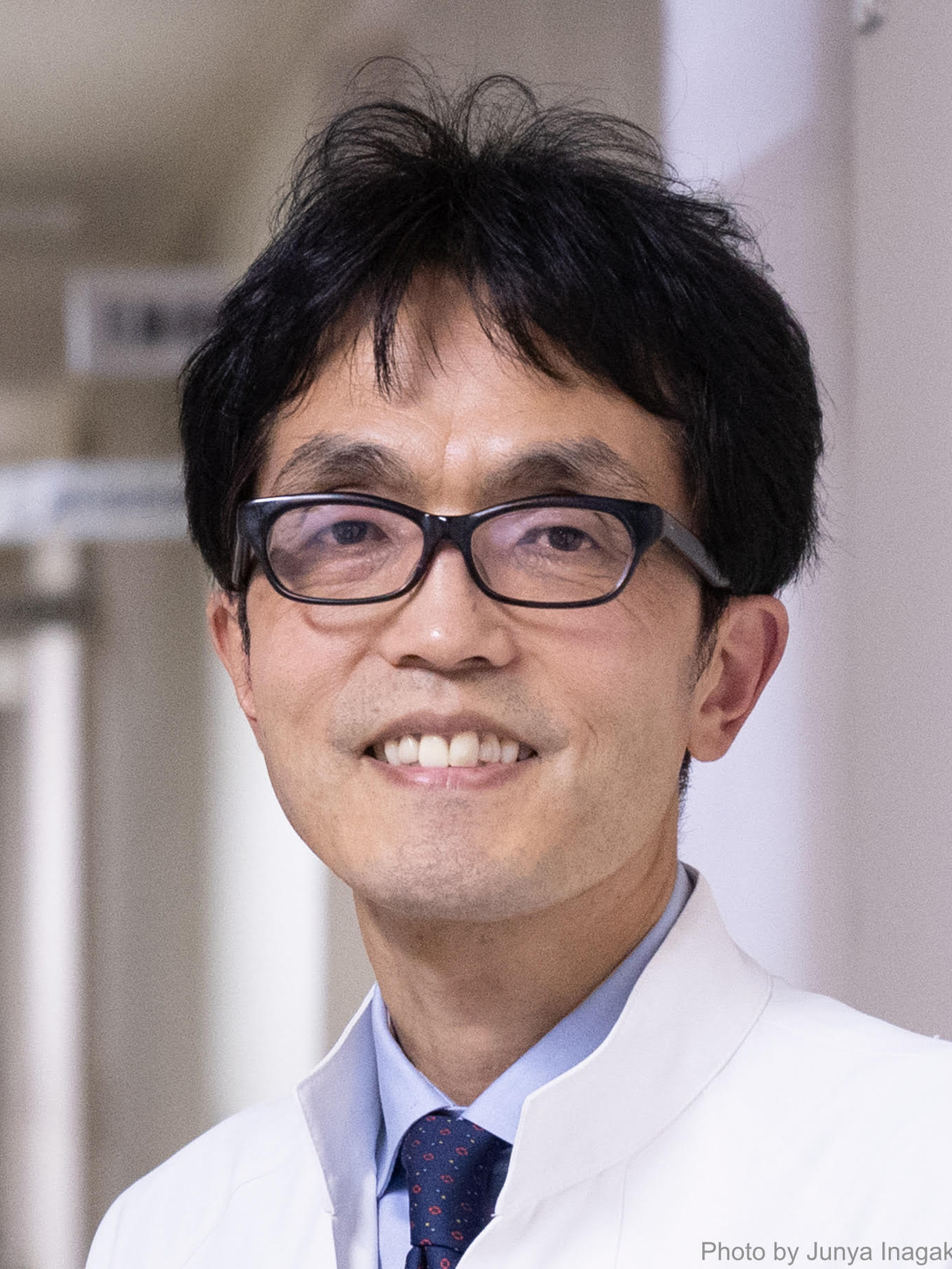国民の2人に1人が罹患する「がん」は、40~50代以降に罹患率が高まっていくそうです。長寿化が進む日本において、がんは決して他人事ではありません。そこで、医師で『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)著者の勝俣範之氏が、がんを取りまく現状と、がんと告知されるまでの具体的な流れについて解説します。

“日本人の2人に1人”が経験する病…「がん」と診断されて5年後に生きている確率は?【医師が解説】
拍子抜けするほど淡々と…「がん告知」の実際
O:そうした検査をして、がんだと確定すると、お医者さんから患者さんに対して、いわゆる告知があると思うのですが、最近ではどんな感じで伝えられることが多いのでしょう? やはり心の準備が必要なぐらい、重々しい雰囲気なのでしょうか?
勝俣:告知と聞くと、まるで裁判官から判決を言い渡されるようなものものしいシーンを思い浮かべてしまう人もいますね。テレビドラマや映画などの影響だと思いますが、現在のがんの告知のほとんどは、非常にあっさりとしたものであることが多いかもしれません。
告知を受ける方が拍子抜けするほど、淡々と「がんです」と告げられるのが、今は一般的だと思います。
O:そうなんですか! それだけ、お医者さんにとっては、がんは特別な病気ではないということですか?
勝俣:すでにお話ししたように、日本人の2人に1人はがんになる時代です。もはや医療の現場では、がんは珍しい病気ではありません。そのせいか、昨今の医師はがんの告知をすることに、ほとんどためらいがありませんね。
患者さんの気持ちを考えれば、もう少し気を遣ってもよいのではないかと思うこともありますが、そこまで気配りしてくれる医師は最近では少ないと思います。
O:がんの告知があっさりしたものとは思ってもみなかった人たちは、よけいにショックを受けそうです。
勝俣:それどころか、最近では、告知に続いて今後の治療の段取りや予後(見通し)についても、矢つぎばやに話しだす医師も珍しくありません。病院やクリニックによっては、「うちでは治療ができません。紹介状を書くので、ここに行ってください」と、そっけなく大きな病院を紹介するケースもありますよ。
O:そんなふうにあっけなく告知された患者さんのほうは、すんなり受け入れられるものでしょうか?
勝俣:そうですね、なかには精密検査を受けた時点で、がんと診断されることを予想していたという方もいないわけではありません。しかし、たいていの患者さんは、まさか自分ががんになるとは思ってもみなかったというのが本音だと思います。
それなのに、いきなり医師から「あなたはがんです」と告知されるものですから、びっくり仰天してしまい、頭の中が真っ白になって、医師が言うこともまったく頭に入ってこないという状況になられます。たとえていねいにお伝えしても、呆然としたまま、診察室を出ていかれる方も多いですね。
O:私もがんだと言われたら、きっとそうなると思います。
勝俣:日本人の2人に1人ががんになるという情報はどこかで知っていても、それはあくまでも情報として知っているというだけで、まさか自分がと、想像もしていなかったという人がほとんどだと思いますね。
ですから、がんと告知された途端、どうしていいかわからなくなってしまうというのもわからないでもありません。だからこういう心のケアもがん治療の範疇なのです。
勝俣 範之
日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科
教授/部長/外来化学療法室室長