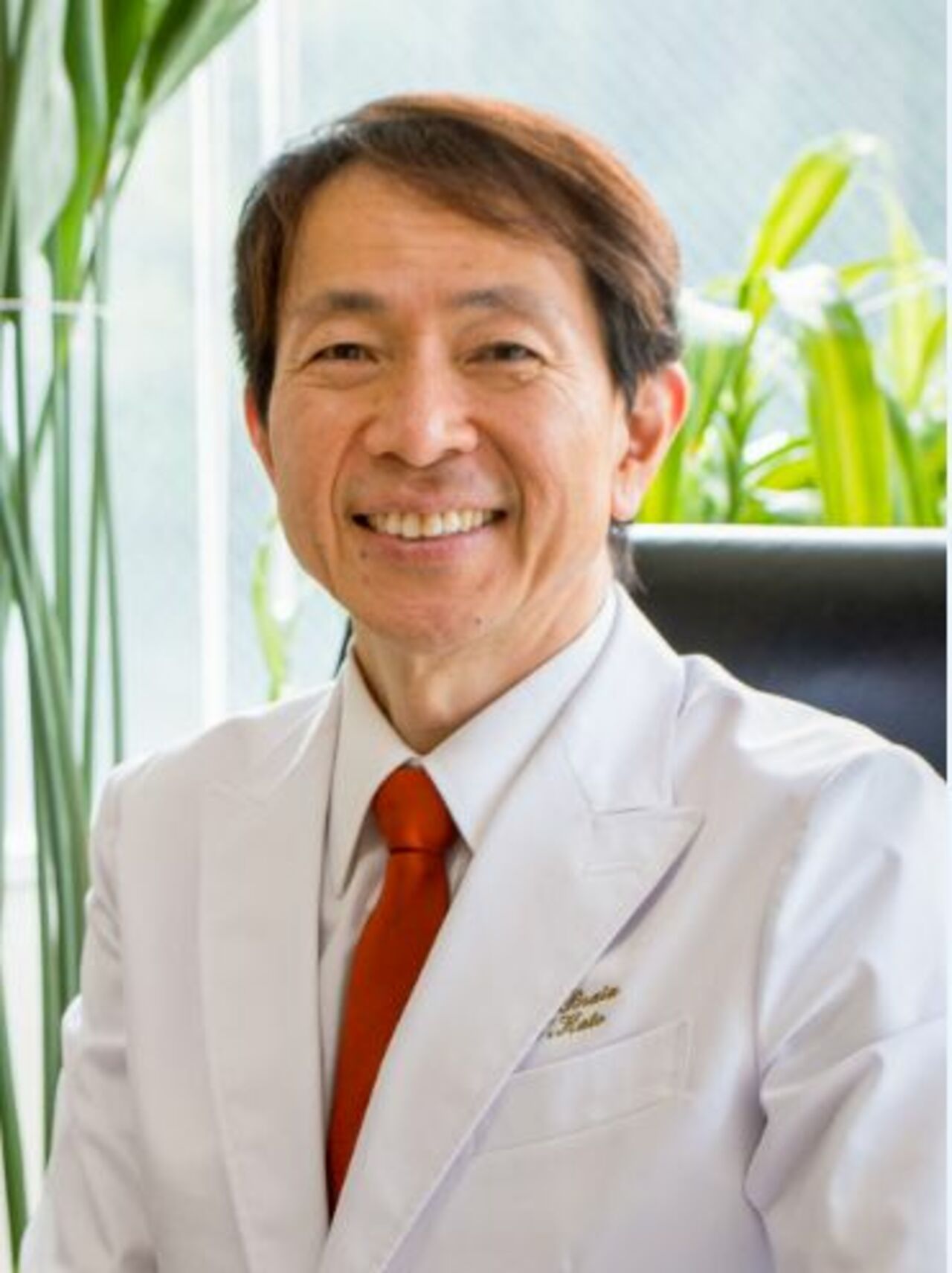NHKの連続テレビ小説や大河ドラマなど、「始めと終わりは何となく覚えていても真ん中のストーリーは覚えていない」なんてこと、ありませんか? それは学んだことの最初と最後が記憶に残りやすいという脳の特性のせい。そんな特性を生かして記憶力を底上げする仕組みについて、著書『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』(サンマーク出版)より、 加藤俊徳氏が解説します。

大河ドラマの始まりと終わりは覚えていても真ん中がすっぽり抜けているのはなぜ?記憶力定着の仕組み【脳内科医が解説】
気分転換のスマホはNG?記憶力キープのコツは…
新近性効果は、1976年にアメリカの心理学者N・H・アンダーソンによる模擬裁判の実験結果から提唱されたものです。
1つのグループは検事側→弁護側の順で証言を、もう1つのグループには最初に弁護側、最後に検事側の証言をまとめて述べます。
これにより、陪審員がどのような判断を下すかを見るというのが実験の内容でしたが、どちらのグループも最後に証言を提示した側が勝訴するという結果になりました。さまざまな議論を尽くしても、人は途中の経緯を忘れやすく、終盤の意見をより記憶してしまうのです。
ビジネスシーンではプレゼンの順序を決めたり、顧客へ商品を訴求したりする際に、初頭性効果と新近性効果はセットとして活用される場面も多いようですが、こと勉強に関してもこの2つはセットで働いています。
勉強においても学んだことの最初と最後が記憶に残りやすいのです。
つまり、復習をするときは、記憶に残りにくい真ん中から始めたり、復習回数を増やすというのが賢いやり方です。
前日に1〜10ページまでを勉強したなら、翌日は4ページあたりから始めれば、記憶の穴を効率よく埋められます。
脳の特性をよく理解した上で、強く定着したところを伸ばすだけではなく、弱い部分を補うように埋めていくというやり方で記憶力を底上げすることができます。
また、1966年に行われた記憶の仕組みを探るための実験に、もうひとつヒントがあります。
被験者を3つのグループに分け、15の単語を覚えてもらいます。グループAには覚えた直後に単語を回答してもらい、グループBは覚えた直後に10秒間、グループCは30秒間、数字を叫ぶという妨害行為を行った後に回答してもらいました。結果は、グループAは最初と最後の正解率が高く、グループBとCは最初の正解率が高くなりました。
最初は記憶するものが少ないので、すべてのグループにおいて記憶力が高い状態です。しかし最後に関しては、妨害行為のないAのグループだけ正解率が高くなりました。
あなたは、勉強直後に気分転換とばかりにスマホでニュースやツイッターなどを見てはいませんか? その行為こそが、後半で勉強したことが忘れやすくなる妨害行為なので気をつけましょう。
加藤 俊徳
加藤プラチナクリニック院長/株式会社脳の学校代表
脳内科医/医学博士