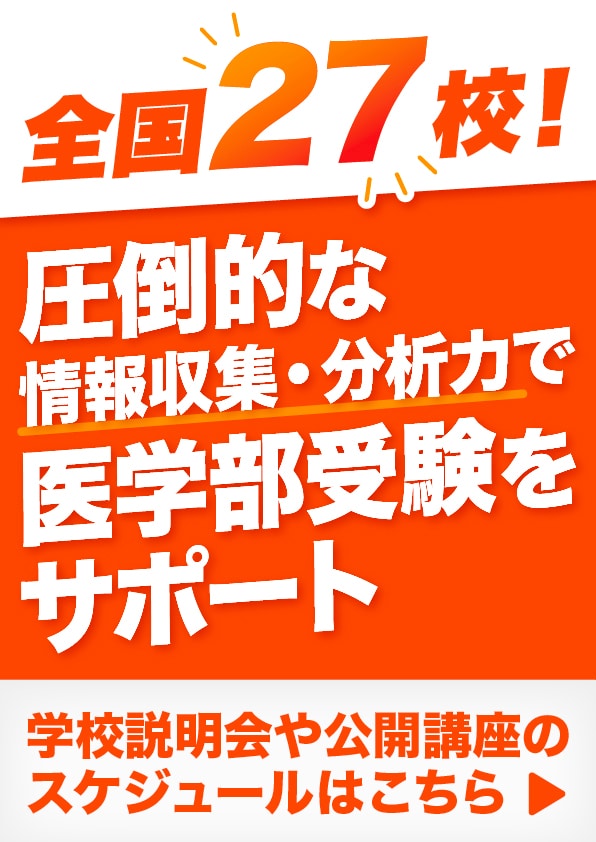音楽業界から一転、20代前半で医学部受験をスタート
小児科クリニックの院長として、地域医療に取り組む鈴木大次郎さん。その経歴は特殊です。地元の公立高校を中退後、通信制高校を経て音楽系専門学校へ。卒業後は東京で音楽関係の仕事をしていました。しかし、23歳のときに一念発起し、医学部受験を目指すことに。実質2年間の猛勉強のすえ、見事に医学部合格を勝ち取ったのです。
鈴木さんが好きな音楽の仕事をやめて、医師になろうと思った理由は何だったのでしょうか。
鈴木:「父は会社員、母は主婦という一般的な家庭で育ちました。祖母が耳鼻科の開業医だったので医療は身近に感じてはいましたが、私自身は医師になろうとはまったく考えていませんでした。
医師を志したのは、大きく3つの理由があります。一つは高校時代の親しい友人が亡くなったこと。その後しばらくして祖母が病気で倒れたこと。さらに父も大病を患ったこと。これらが重なり、『自分が地元に戻って地域医療に貢献しなければ』という気持ちが湧き起こったのです」
最初の1年は独学で、「勉強の仕方」から学び始めたが…
とはいえ、大学受験の最難関である医学部を目指すのは、あまりにもハードルが高かったのではないでしょうか。
鈴木:「恥ずかしながら、高校は地域で最底辺といっても差し支えないレベルで、勉強はほとんどしませんでした。ただ、勉強そのものは決して嫌いではなく、小学生の頃はむしろ好きでした。中学・高校はスポーツや遊びに夢中で、勉強にはまったく興味が向かなかったのです。
しかし、だからこそ偏差値の概念や医学部が難関だという意識もほとんどなく、ある意味フラットな気持ちで受験勉強を開始できました。『やればできる』という、根拠のない自信がありましたね」
そこから独学で受験勉強を始めた鈴木さん。しかし、1年経っても成績は伸びませんでした。
鈴木:「当たり前といえば当たり前の結果です。最初は勉強の仕方すらわからず、市販の受験関連本で勉強法から学び始めたくらいでしたから。このまま1人で勉強を続けるのはムリだと判断し、1対1の個別指導かつ確立された合格メソッドを実践しているメディカルラボにお世話になることにしました」
気になる学費は、幸いにも、祖母が「孫がいつか医師を志すときのために」と用意してくれていたお金がありました。
鈴木:「祖母には本当に感謝の気持ちしかありません。入校した私は、1年で合格するつもりで気合いを入れて勉強しました」
学力状況に合わせて「基礎中の基礎レベル」からスタート
そうはいっても、道のりはかなり厳しかったはずです。当時、鈴木さんの担任講師を務めたメディカルラボの可児良友先生は、次のように振り返ります。
可児:「経歴は聞いていましたが、入校時の『学力診断テスト』の結果はさすがに驚きました。英語、数学、化学、生物の4科目すべてが、大手予備校の模試に置き換えると偏差値20レベル。特に厳しかったのは英語で、アルファベットの文字さえ怪しい状況でした」
メディカルラボでは、医学部合格に必要な力をつけるために、個々人の学力状況に合わせ、基礎固めから応用レベルまでの年間カリキュラムを作ります。鈴木さんの場合は、まさに基礎の基礎レベルから始めることになりました。
可児:「全科目、カラーでわかりやすく丁寧な解説が載っている参考書と、それに付随する問題集を組み合わせました。すべて市販のテキストです」
他の生徒を圧倒する勉強量に、自ら取り組んだ
鈴木さんは、個別授業で基礎を徹底的にたたき込む一方で、自分のできる範囲で問題集に積極的に挑戦していきました。
鈴木:「市販のテキストはすごく勉強しやすかったですね。数学や生物など好きな科目は問題集を自分でどんどん進め、わからないところは授業で教えてもらいました。苦手な英語は、英単語をひたすら覚えるといった基本的な勉強に力を入れました」
入校当初から「1年で合格を目指す」と意気込んでいた鈴木さん。その言葉どおり、勉強量は他を圧倒していたと可児先生はいいます。
可児:「『宿題をたくさん出してほしい』という本人たっての希望があり、各教科で相当な量の宿題を持ち帰っていました。予備校が終わったらファミレスへ行き、そこで深夜2時頃まで取り組んでいたようです。いつも全力で、努力を惜しまない姿が印象に残っています」
鈴木:「メディカルラボは本当に集中できる環境でしたから、こういうと語弊があるかもしれませんが、勉強がすごく楽しかった記憶があります。私は最低レベルからスタートしたこともあって、取り組んだ分だけ着実に成績の伸びを実感でき、ゲーム感覚で受験勉強を進められました。特に可児先生の担当科目だった生物はすごく得意になって、まるで最強の武器を手に入れたかのような気持ちでした」
「早く合格すること」を重視し、夏の時点で私立専願へ
受験勉強を半ば楽しんでいたという鈴木さんですが、もちろん苦労したこともあります。
鈴木:「再受験生ならではかもしれませんが、地元の友人たちが社会人として成功していくなかで、自分だけ学生のまま立ち止まって足踏みしている感覚に陥りました。授業料や生活費も祖母や親頼みですから、やはり心苦しさがあります。
だからこそ、常に『ありがたいな』という感謝の念を大事にしていました。こうやって勉強させてもらえているのは、決して当たり前のことではなく、家族の応援があってのことです。そう思えばこそ、一刻も早くここから脱しなければという強い気持ちを持てました」
実際、遊びや飲み会の誘いは一切断り、受験勉強に専念したという鈴木さん。その努力が実り、1年目の受験では関東の私立医科大の1次試験にパス。最終合格は果たせなかったものの、医学部合格に向けて確かな手応えを得ました。
自信がついた鈴木さんは、国公立医学部も視野に入れ、国語と社会の勉強にも着手します。少しでも学費の負担を軽くしたいという思いからです。しかし、国語の成績が思うように伸びませんでした。
鈴木さんは、開業して地域医療に取り組むと決めていました。開業するなら体力のあるうちにという考えがありましたが、国公立を目指すならさらに時間がかかります。
鈴木:「年齢的な面での焦りから『1日でも早く開業して地域医療に携わりたい』という思いがありましたので、夏の時点で私立に絞りました」
そして迎えた2回目の受験は、可児先生の適切な受験校選びのアドバイスも奏功し、首都圏、中部、関西圏など5校を受け、すべて1次試験を突破。最終的に、自宅に近い藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)に入学しました。
実質2年間の受験勉強で医学部合格を果たした背景には、鈴木さんの勉強に取り組む真摯な姿勢、努力があったことはいうまでもありませんが、加えて、可児先生は医学部合格の秘訣を次のように述べます。
可児:「気持ちが前向きというか、いつもポジティブでしたね。また、メディカルラボのようにマンツーマン形式の予備校は生徒どうしでの交流がしづらいイメージがあるかもしれませんが、大次郎さんはメディカルラボ内でも広い交友関係を築いていました。そうした社交性、人間性も成績が伸びる要素の1つかなと思います」
鈴木:「遊びや飲み会に誘ってくる地元の友人とは一定の距離を取りましたが、同じ医学部受験を目指す仲間は、切磋琢磨できる大切な関係です。周囲とズレたことをやっていては受かりませんから、『今どのあたり?』と勉強の進捗を伝えあったり、情報交換したりなど積極的に交流をしました」
「目標」をもって突き進めば、結果はあとからついてくる
鈴木さんが小児科医を選んだのは、大学時代に短期留学したアフリカのザンビアでの経験が大きく影響したといいます。
鈴木:「ザンビアは経済的に厳しく、医療環境も整わないなかで、現地の子どもたちの元気さ、明るさに感動しました。日本は少子化問題で暗いニュースが多く、このままでは日本の未来はどうなるのかという思いから、自分にできることとして、『小児科医となり地域医療に貢献すること』を決意しました」
その夢、目標に向けて、2024年、鈴木さんは念願のクリニックを開業しました。
鈴木:「クリニック内の意見箱に、毎日、子どもたちが手紙を入れてくれます。可愛い絵とともに『だいじろう先生いつもありがとう』などと書いてあるのを見ると、本当に励みになります。
私は、自分の手の届く範囲を幸せにしたいという気持ちをずっと持っています。開業以来、手の届く範囲が少しずつ広がりながら地域医療に貢献できている実感が湧き、医者になってよかったと心から思います」
医学部合格や医師免許の取得がゴールではなく、医師として何を実践したいのか。鈴木さんは、「地域医療への貢献」という明確な目標があったからこそ、再受験という大きなハンデを乗り越えて、医学部合格を勝ち得たのではないかという印象を強く受けます。
鈴木:「受験勉強をするなかでは、いろいろな不安や迷いが生じるでしょう。しかし、とにかく自分の目標に向かって、自分の信じた道を突き進むことが大切だと思います。そうすれば結果はあとからついてきます」