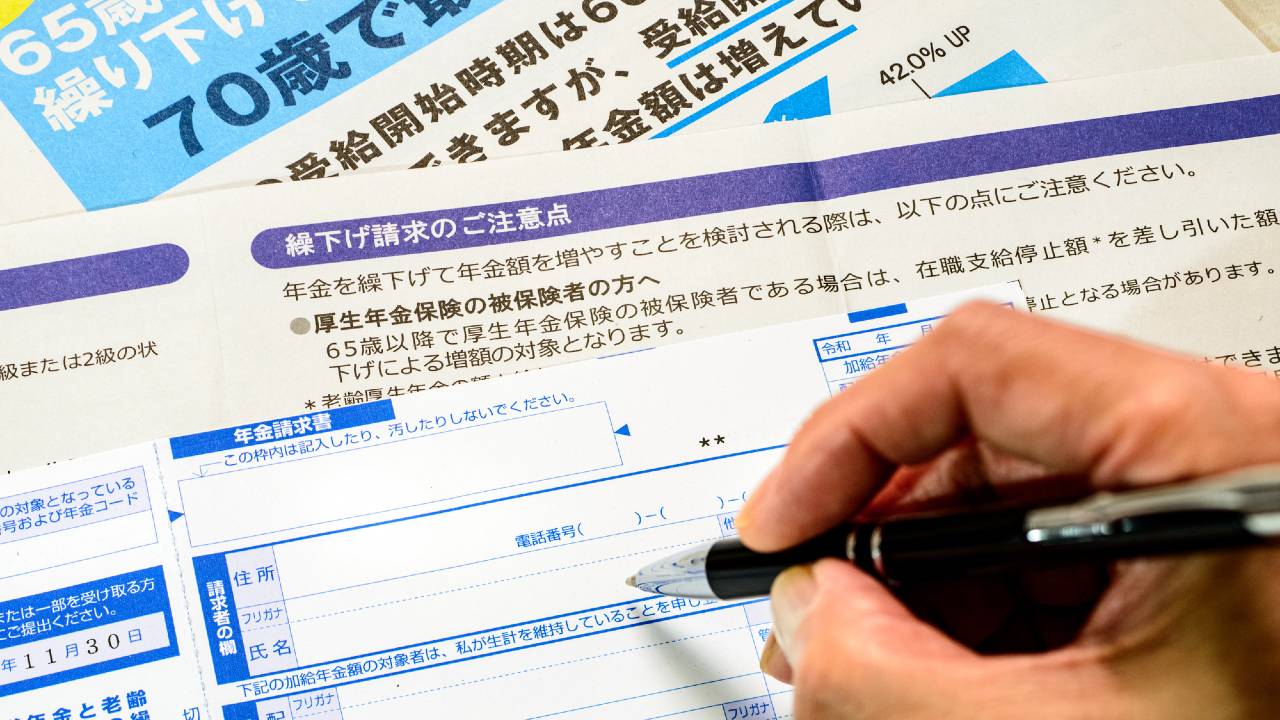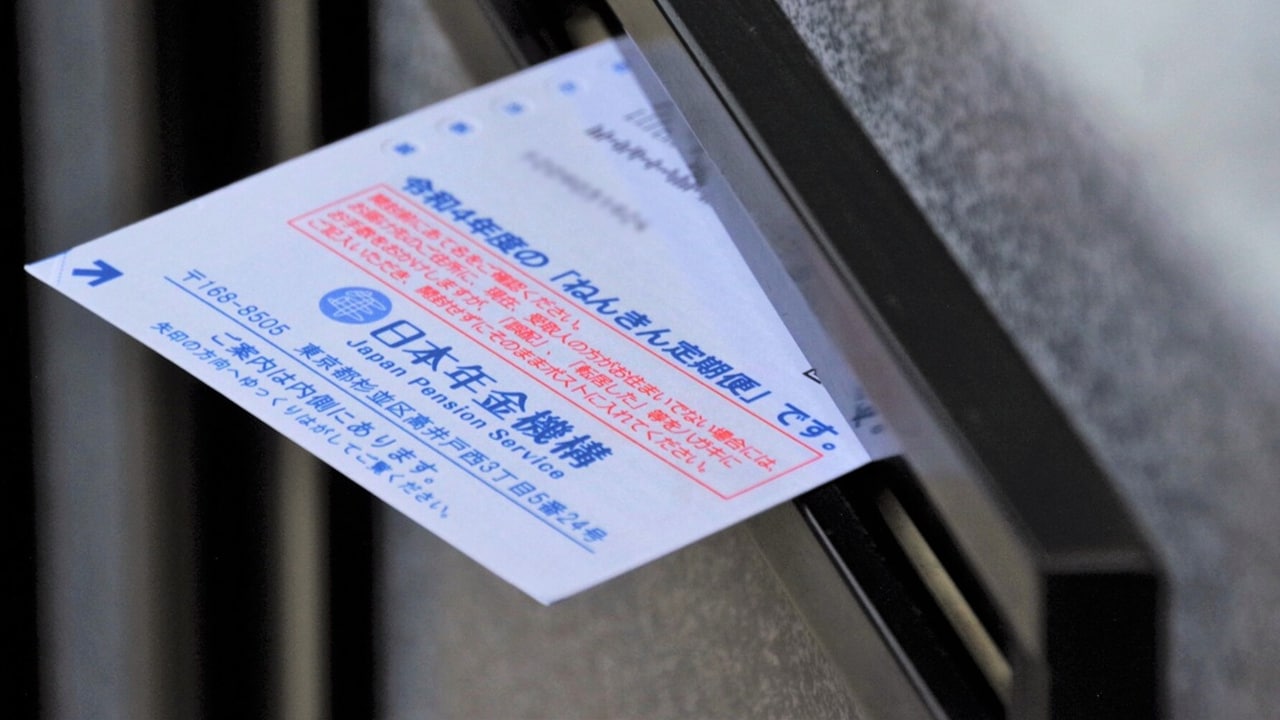女性のほうが長生きする傾向にあるため、夫の死後に妻が1人残されるケースは少なくありません。その際に大きく変わるのが年金受給額。想像以上の減少に驚いたという声も多く聞かれます。そこで、今回は老後の生活に大きな変化が起こった田中さん親子の事例と共に、いざというときに役立つ「年金生活者支援給付金」についてCFPの伊藤寛子氏が解説します。

(※写真はイメージです/PIXTA)
もっと早く帰っていれば…1年ぶりの帰省で発覚した実家の「変わり果てた様子」に息子呆然。年金暮らしの81歳母が涙ながらに語った“困窮”の理由【CFPの助言】
「年金生活者支援給付金」支給対象者かどうかを判断する方法
年金生活者支援給付金の支給対象となる人には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」がはがきで送られてきます。届いたはがきを元に申請手続きを行わないと、給付金を受け取ることはできません。
田中さんの母は、父が存命で年金をもらっていたころは、この制度には該当していませんでした。父が亡くなり、母自身の年金額(遺族年金は含まれません)が基準額以下であり、住民税非課税世帯となったことで、新たに制度に該当しました。
そのため、母の元には「年金生活者支援給付金請求書」のはがきが届いていましたが、よくわからなかった母は、そのまま放置してしまったのです。
給付金額は年金の上乗せとして十分な額ではありませんが、給付要件に該当している間はずっと受け取り続けることができます。
利用できる制度をきちんと活用するためには、給付金などの存在を知っておくことが大切です。しかし、年金制度は複雑で、年金の種類や制度も複数あり、なかなか把握するのが難しいでしょう。書類を見てもよくわからない場合は、まずこどもに聞いてみるのはもちろん、年金事務所などの担当部署に書類を持参して教えてもらうこともできます。