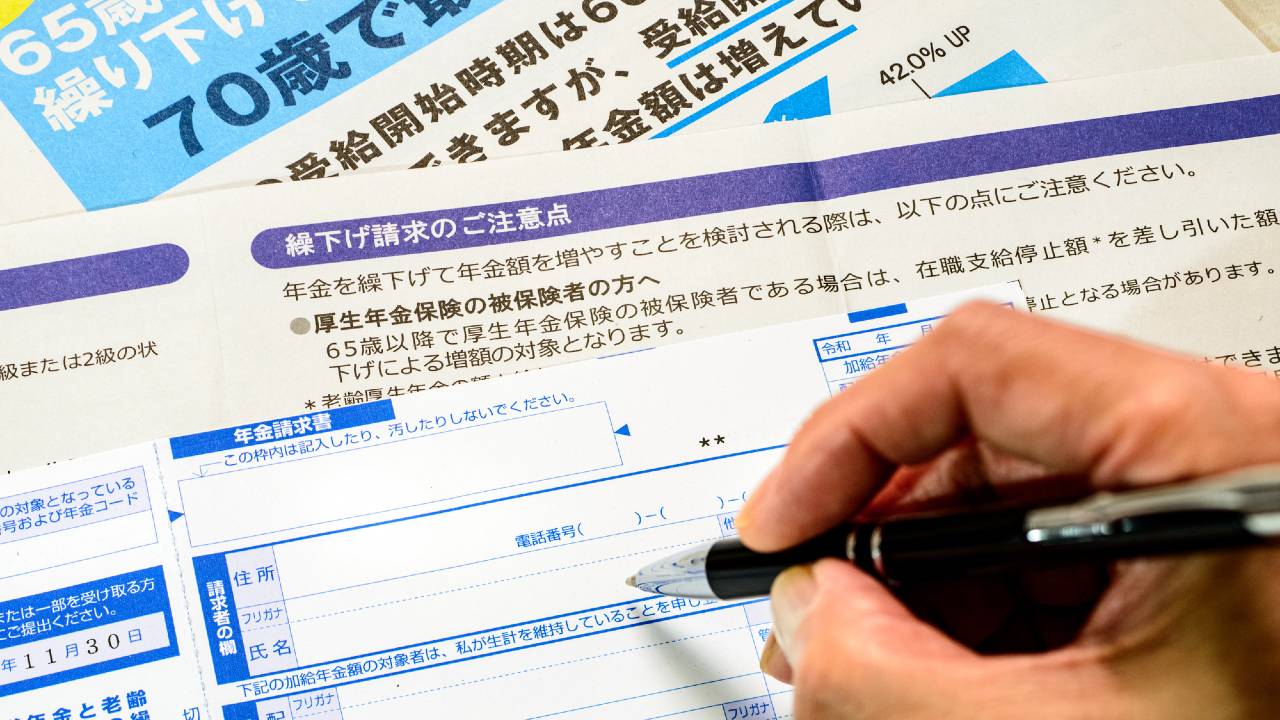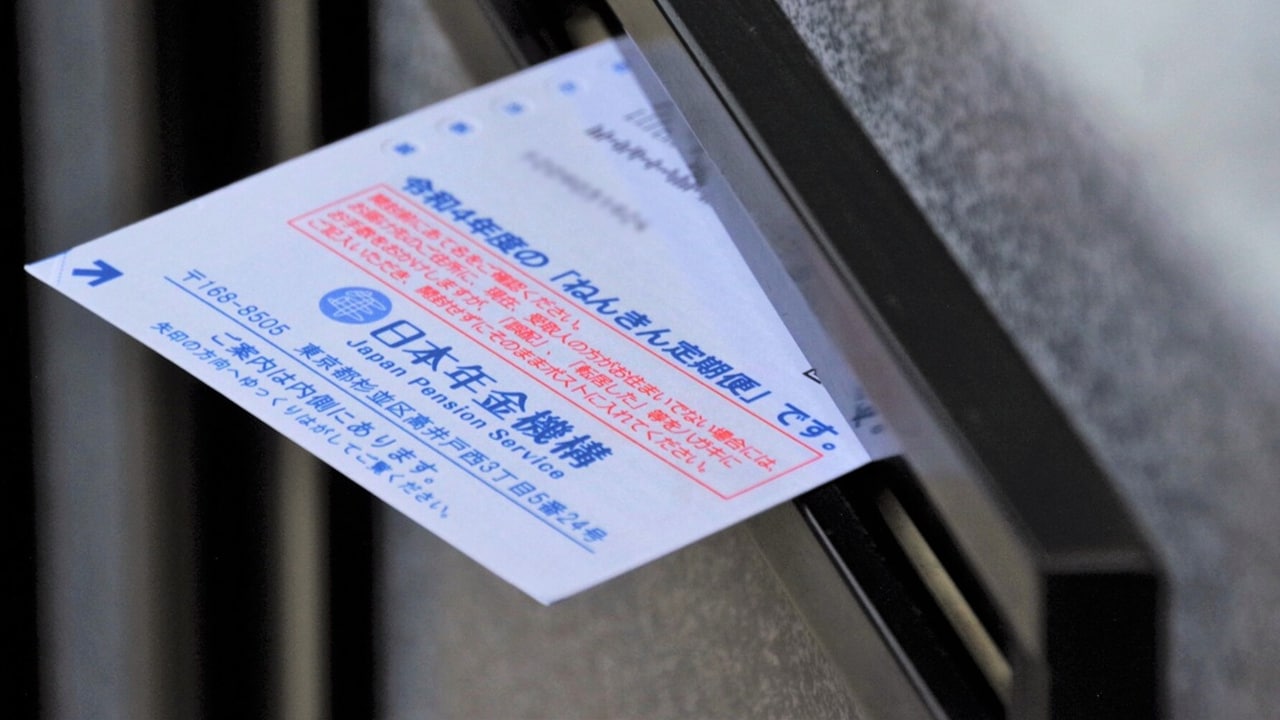女性のほうが長生きする傾向にあるため、夫の死後に妻が1人残されるケースは少なくありません。その際に大きく変わるのが年金受給額。想像以上の減少に驚いたという声も多く聞かれます。そこで、今回は老後の生活に大きな変化が起こった田中さん親子の事例と共に、いざというときに役立つ「年金生活者支援給付金」についてCFPの伊藤寛子氏が解説します。

もっと早く帰っていれば…1年ぶりの帰省で発覚した実家の「変わり果てた様子」に息子呆然。年金暮らしの81歳母が涙ながらに語った“困窮”の理由【CFPの助言】
遺族年金の仕組みとは?年金額がガクッと減る理由
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者だった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、いずれかまたは両方の年金が支給されます。「遺族基礎年金」を受け取ることができるのは、「子のある配偶者または子」です。子とは、18歳になった年度の3月31日までにある人、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人をいいます。
上記の条件に合致しないため、田中さんの母は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。
一方、「遺族厚生年金」は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者・子・子のない配偶者・父母・孫・祖父母」の順に、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。老齢厚生年金から国民年金に相当する額を差し引いた、報酬比例部分の4分の3の額を「遺族厚生年金」として受け取ります。死亡した人が受け取っていた老齢厚生年金の全額を受け取れるわけではありません。
さらに、65歳以上で「自身の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取る権利があっても、どちらも全額受け取れるわけではありません。自身の老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金については、老齢厚生年金に相当する額は支給停止となるため、差額分のみが支給される仕組みになっています。
田中さんの母の場合、生前の父と2人で受け取っていた年金額は、合計でひと月当たり約20万円でした。父が亡くなったことにより、専業主婦だった母が受け取るひと月の年金額は、自身の老齢基礎年金が約5万円、遺族厚生年金が約6万円、年齢に応じた加算がつき合計約12万円になりました。しかも社会保険料などが引かれ、実際に振り込まれる金額はさらに減ります。
年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」とは?
父が健在のときには思いもしなかった年金の少なさに、この先暮らしていけるのか、不安とストレスを抱えきれなくなったものの、「息子には迷惑をかけちゃいけないと思い言えなかった」と涙で話す母に、「まずは家のなかを片づけて、どうしていったらいいか一緒に考えよう」と田中さんは声をかけ、散らかった部屋を片づけ始めました。
すると、片づけの最中に、積み重なった書類のなかから「年金生活者支援給付金請求書」と書かれたはがきを発見したのです。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額が一定基準額以下の人に対して、生活の支援を目的として、年金に上乗せして支給するものです。以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
(2)同一世帯の全員が住民税非課税であること。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれの人は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの人は887,700円以下であること。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額は、月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。たとえば、国民年金保険料を40年(480月)納付した人の場合は月額5,310円で、20年(240月)納付した人の場合は半分の月額2,655円になります。