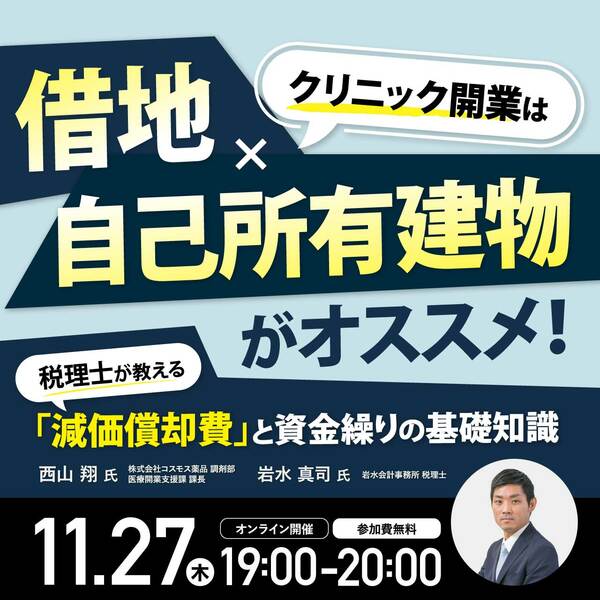「働き方改革」で、休日夜間診療所はスムーズな受診が困難に
従来の医師の勤務形態を大きく変える「医師の働き方改革」ですが、現時点ではまだ移行段階であるため、タイムカードのように労働時間は厳密には管理はされてはいません。しかし、これまでの医療現場の「過重労働が当たり前」となっていた風潮から、時間外労働を自院勤務先で多く費やすことになり、大学医局などの指示による、派遣先となる地域の医療機関勤務が困難となるなど、当初の懸念が現実化しつつあります。
地域によっては、大学や基幹病院からの医師派遣で成り立っていた休日夜間診療所(主として市町村が運営、地域医師会が担当)の休廃止・統廃合などが行われています。
その理由は、前述のとおり、地域医療機関への医師の派遣が「時間外労働」とカウントされるためです。大学病院や中核病院から医師の派遣が打ち切られたり、突然の病院の急変対応で中止されたりする事態が発生しています。
そのため、とくに休日夜間診療所には、以前のようなスムーズな受診が困難になってきました。医師会側もその対策として、患者数を少数にすることで、時間外労働にカウントされない「宿日直許可」として、「常態として診療勤務をしない」申請を行い、実際に許可を受けた医師会の休日診療所もいくつか存在しています。
医師会診療所が「宿日直許可」を取得できるかどうかが、大学病院などからの医師派遣の継続有無の生命線となるのです。
休日診療所・開業医たちが繰り出す「苦肉の策」
宿日直許可が取得されると、勤務先以外の休日診療所の従事が医療機関での勤務としてカウントされなくなります。すると、派遣医師の立場からは給料の問題が、地域の医師会の医師からは救急当番負担の減少が、なにより地域住民は、小規模の休日診療所の統廃合により遠方へ受診をしに行くという利便性の低下が、重大な懸念点となります。
休日診療所の多くは市町村市が運営しており、地域住民のための医療提供による公益性を守るため、医師会会員の努力に加えて大学病院・基幹病院の勤務医の協力で成り立っています。
一方、開業医も高齢化が進行し、とくに休日・夜間に具合が悪くなることが多い小児科では、小児の診療に慣れている小児科標榜医や専門医資格を有している医師がメインで勤務に入るものの、休日診療所の勤務が免除されるひとつの基準である「70歳」を超えてもなお、自院のクリニックに加え、年に12回以上も休日診療所の勤務を実施している現状があります。
小児科に限っては、大学病院に年に50回の派遣を依頼しており、依存状態となっていますが、前述した「働き方改革」における宿日直許可が取得できない場合には、大学病院・基幹病院からの派遣となる医師がいなくなり、休日診療所が維持できなくなった市町村もあります。
苦肉の策として、民間の人材紹介会社にフリーターとされる医師を対象としてスポット勤務を依頼した場合もあるのですが、質が担保されず苦情が多いなどの問題もあります。最終的には、休日夜間診療所がこの働き方で機能不全に陥った場合、地域の入院を担当する基幹病院が、こうした軽症の休日夜間診療も担当せざるを得ないといった事態になっています。
現状は「医師が存在しない」のではなく…
ただ、実際には「医師が存在していない」のではなく、休日夜間診療所でまっとうに勤務を遂行ができる、経験のある医師が少ない、地域医療で活躍ができる医師が減少している、というのが現状だといえます。
近年の統計では医師は33~34万人いて、医師国家試験の合格率は90%を超えています。
大学病院や地域基幹病院で「全人的なかかりつけ医」として責任を持って働くことのすばらしさや、近年クローズアップされている「総合診療医」の魅力について、大学側が医学部の学生たちに、もっと強く訴えかけることが重要でしょう。
医学部実習や2年間の初期臨床研修の間でも、訪問診療・地域の総合クリニックなどでの勤務体験などの社会的な要素をもっと訴求していかなければ、地域医療の崩壊は目に見えています。
休日診療所が機能不全になり、地域の病院が軽症の休日診療所の業務を兼任することによっても、すでに入院医療に弊害が生じています。
昨今のケースでは、16歳の男性が2回、休日診療を行っている基幹病院で研修医に急性胃腸炎と診断されたものの、最終的には上腸間膜動脈症候群であり、死亡した不幸な事例がありました。
この事例では病院側が過失を認めましたが、画像検査所見の異常の見落としや、指導医のチェック不足なども推察され、質が担保されるべき医療現場での「マンパワー不足」が浮き彫りになった印象でした。
地域社会による「診療体制の変更」を受け入れが課題に
とくに地域医療では、小児科の救急・分娩対応が困難となっており、遠方への受診を余儀なくされる例もあります。また、近年では外科系の診療科(とくに心臓・消化器)が、働き方改革により緊急手術が困難となっている事案も多く、命の砦となる診療科のパフォーマンスが明らかに低下しているのです。外科の例では、予定していた腫瘍の手術もスケジュールが組めず、手術当日になっても、他院で対応困難となった緊急症例と手術が急遽差し替えとなり、予定手術が延期となる事例も散見されます。
今後は、診療体制の変更について、地域住民や地域社会に少しずつ受け入れてもらうことが重要となるでしょう。医師が負担を抱え込むのではなく、患者とその家族と協力して、双方が歩み寄るなかで医療を提供していく必要があるといえます。
日本は世界に例のない超高齢化社会が進行しています。それにともない医師の労働人口も減少していくことから、従来のような利便性を追求するような考え方を転換し、できる範囲の医療レベルを公表し、患者側と協同で治療に取り組むべきところまで来ている現状があるといえます。
武井 智昭
株式会社TTコンサルティング 医師