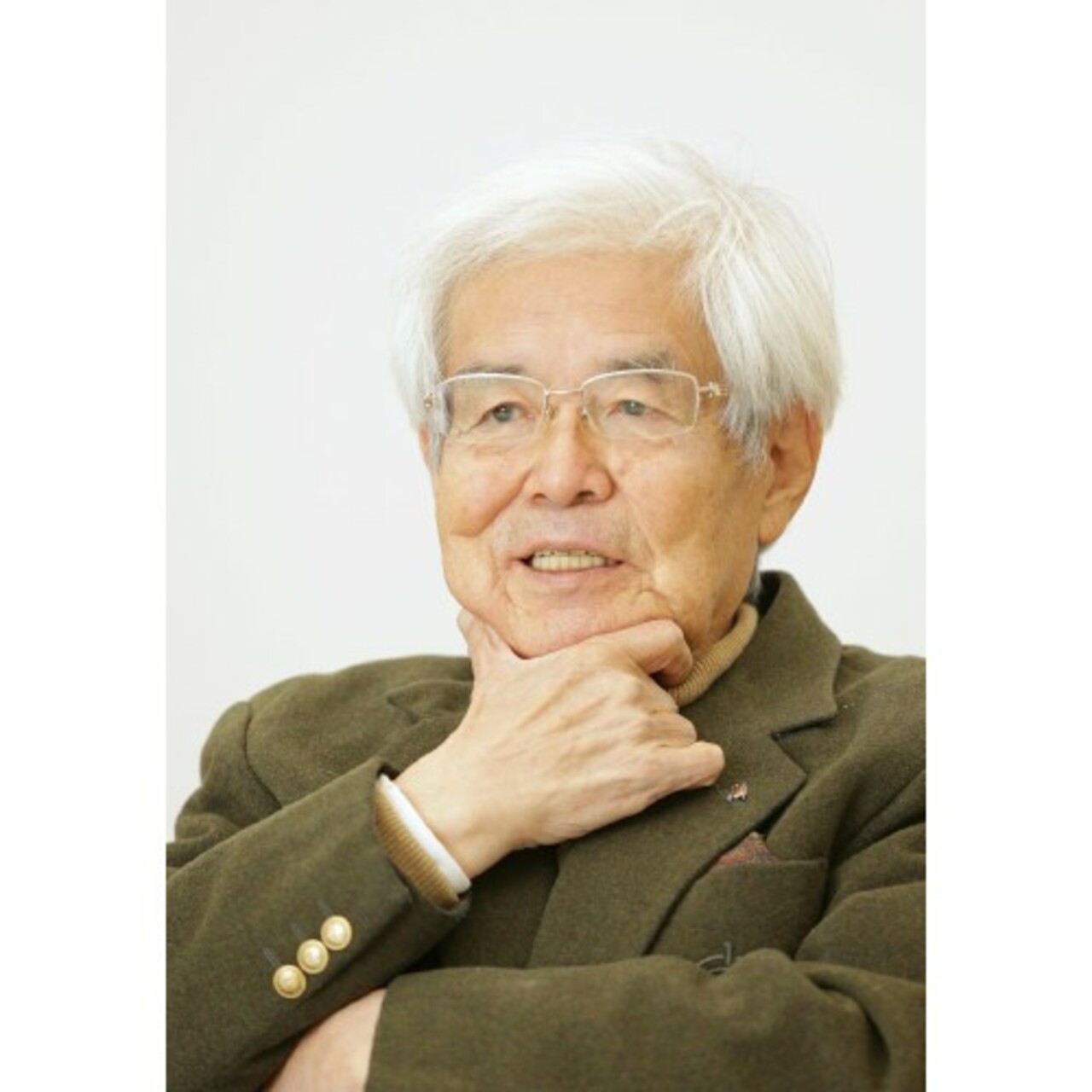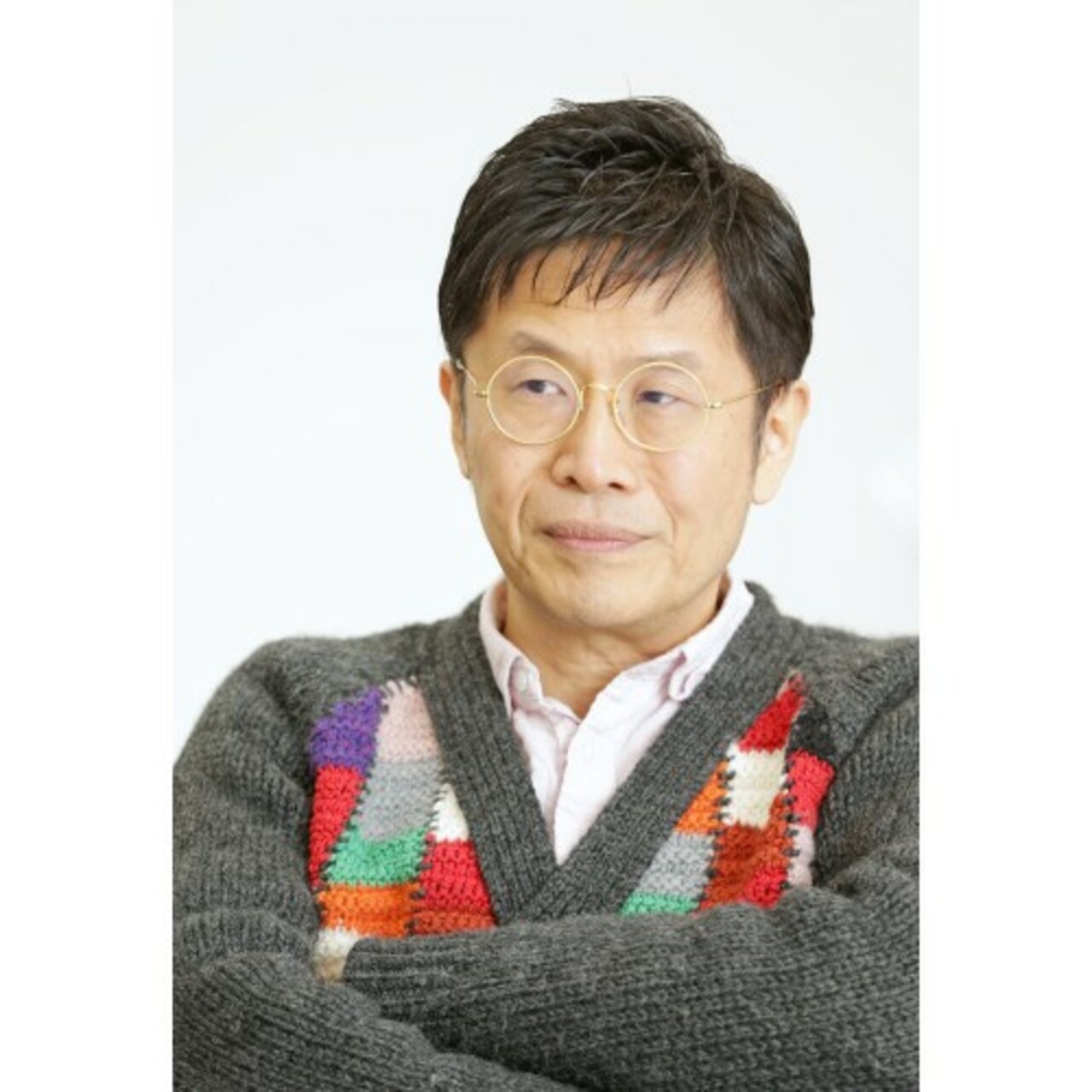認知症をいかにして防ぐか、というテーマに興味を持つ人も多いのではないでしょうか。日々、技術革新が進んでいく脳科学の世界で、今浮き彫りになってきた問題がある、と医師の養老孟司氏は言います。養老氏と名越康文氏の共著『二ホンという病』(日刊現代)から、詳しく見ていきましょう。

【養老孟司×名越康文】ピアノの練習をするとボケにくい?…〈認知症予防〉に脳科学があまり役に立たない、意外すぎるワケ【対談】
脳科学的に、認知症を防ぐことは難しいが…
― 一般化できないというのは興味深いですね。そうすると認知症をいかにして防ぐかというテーマを導き出すのは困難ということでしょうか。
養老 固定しちゃうと難しいと思いますね。だから、もっと幅広く老化を防ぐとかね、そういう話になるでしょ、そういうものは。でも、案外、片付く可能性があるかもしれません。
この間、宮崎徹さん(元東京大学大学院教授)との対談で、「ネコは30まで生きる」という話をしたんです。その時、タンパク質の話になってね。体の中でいらなくなったものを血液中の細胞が食べてくれる。その標識物質であるタンパク質のAIM(apoptosisinhibitorofmacrophage)が、ネコにはあるんだけど働いてないんですね。他のものにくっついちゃっている。
ネコ科の動物は腎臓病で死ぬんです。腎臓はしょっちゅうゴミがたまるでしょ。それを片付けるマーカーがない。そういうふうなものが分かっていくと、脳みその場合も、アルツハイマーの場合も、ゴミがたまるんですよ。たまってるから片付けなきゃいけない。その作用がうまく働いていない。
一般に老化を防ぐって話は今、ずいぶん出てきていますね。認知症の場合、脳に絞り込んでいるから、そこだけ抑えればいいかというとそうはいかない。
― 名古屋大の先生の腸内細菌叢の研究で、ニコチンを摂取するとパーキンソン病が発症しにくいという発表がありました。発症メカニズムに腸内細菌叢が関連していると。
養老 従来の科学がですね、1対1の因果関係を追いかけ過ぎて、それで追いかけられないものを全部落っことしていった、残していったのです。残してきたものが、いわゆる問題となっているわけです。それ、だいたい生き物の特徴ですね。網の目のように。仏教的世界になっちゃう。一神教じゃ片付かないですね。
名越 本来網の目の世界でさまざまなものが兼ね合って現実は生まれ続けているけれど、それを直前の世界の因果関係だと誤解してしまうと、こぼれ落ちているものが無限に出てきますよね。そこをどうとらえ、対処していくかが課題でしょうね。
― そこに気づいて、地道に研究をされている動きがあるのでしょうか。日本の場合、基礎科学に予算がつきにくいです。
養老 科学には予算がなかなかつかないですからね。きちんとした因果関係というか、分かりやすい、ああすればこうなるという型でないと、評価されないんで。評価されないとおカネがつかない。結論がなかなか出しにくい、あれもあります、これもありますじゃ聞いてもらえない。そういう科学に適した分野と、適さない分野があって、脳なんか、若いころ僕は、きれいに理屈でいけるもんかと思ったけど、技術が進んでくるほど、割り切れない部分がある。
ということで、今では腸内細菌叢まで考えなきゃいけなくなっているわけです(笑)。専門家は絶対に脳と言いますよ。それ、臨床でも前から言われていることですけどね。内科なんか全部臓器別に分かれているでしょ。そうすると、その専門家というのができちゃってね、そういう人たちは、よそから言われることを嫌がる。ネコのAIMの話もそうですよ。
名越 当分、難しいと思いますね。根本的な構造が違うわけだから。いまだに論文書いても1対1対応で、因果関係がはっきりしない限りおカネがつかないのだから、よほどドラスティックなこと、例えば論理的であると認定される様式自体が変わらなければ無理でしょうね。例えば今は三段論法だけれど、お経などは五段論法で書かれたものがあると聞きます。僕も一時いろいろ調べてみたけど、結局分からなかった。どちらにしても今も、ああすればこうなる、に頼るしかない。
養老 孟司
医学者、解剖学者
名越 康文
精神科医