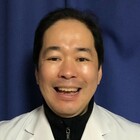(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
公認心理師と臨床心理士との違いは?
さまざまな心理的なサポートができる公認心理師。今まであった「臨床心理士」とはなにが違うのでしょうか。
ひと言でいうと「国家資格であるかどうか」と「他の職業との連携が法的に明記されていること」の2つがあげられます。
「臨床心理士」とは、臨床心理学にもとづく知識や技術を用いて、精神的な問題にアプローチする“こころの専門家”のこと。
昭和63年に設立された日本臨床心理士資格認定協会が実施する資格試験に合格し、認定された人が臨床心理士になることができます。公認心理師の設立までは臨床心理士が、医師とは違った側面で心のカウンセリングの中心を担ってきました。
しかし、臨床心理士は国家資格ではないため、カウンセリングの質にバラつきがある可能性があったことや、臨床心理士に強い権限を持たせにくい点がネックになっていました。
そこで、平成29年に公認心理師法が施行され、平成30年より国家資格である公認心理師の制度が始まったのです。
公認心理師では、保健医療、福祉、教育等その他の分野の関係者等との連携や資質の向上を日々行っていくことも法律上に明記されています。つまり、国家資格として行政や教育、福祉の現場に介入することができるようになったのですね。
そのため、公認心理師の仕事は、従来のカウンセリングや心理療法、心理検査だけにとどまりません。これまで以上に多職種やコミュニティのなかで心理的な側面から連携をとり、メンタル面で悩む方の幅広いサポートができるようになったのです。
公認心理師になるためには長い年月が必要
国家資格である心のプロフェッショナルである「公認心理師」。公認心理師になるためには実は長い道のりがあります。
公認心理師になるためには、まず「公認心理師カリキュラムを持つ4年生大学の学部」を卒業しなければいけません。そこで、下記のように膨大なカリキュラムを4年間の間で学びます。
・心理学概論
・臨床心理学概論
・心理学研究法
・心理学統計法
・心理学実験
・知覚、認知心理学
・学習、言語心理学
・感情、人格心理学
・神経、生理心理学
・社会、集団、家族心理学
・発達心理学
・障害者、障害児心理学
・心理的アセスメント
・心理学的支援法
・健康、医療心理学
・福祉心理学
・教育、学校心理学
・司法、犯罪心理学
・産業、組織心理学
・人体の構造と機能及び疾病
・精神疾患とその治療
・関係行政論
・心理演習
・心理実習(80時間以上)
このように見ると、公認心理師になるためには、さまざまな側面の心理学だけでなく精神疾患といった症状や関連した行政にいたるまで、医学や法律についても幅広く学ぶのですね。これだけでも膨大な量の心理学の研鑽が必要なことがわかります。
それだけに留まりません。さらに特定の期間で2年以上の実務経験を積むか、公認心理師カリキュラムを持つ大学院に入学・修了し国家試験に合格する必要があります(図表)。
大学と大学院の6年間のカリキュラム、そして国家試験に合格しなければならないことなどを考えると、公認心理師は「プロ」として長い年月と努力が必要な資格であることがわかるでしょう。