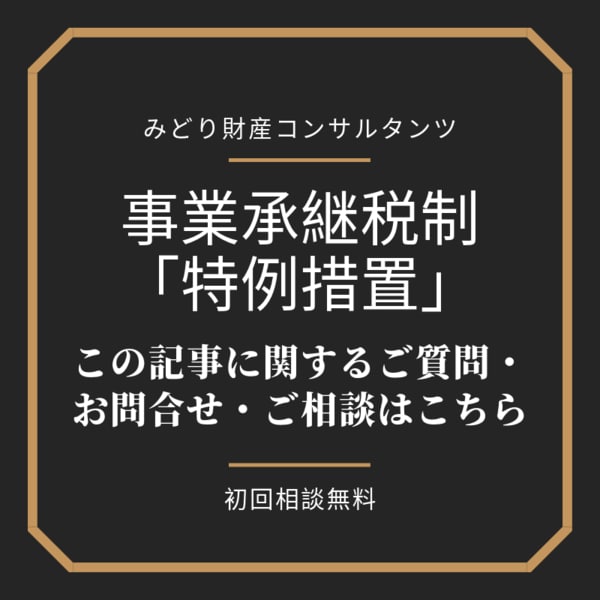特例措置を受けると「経営の自由」が失われる恐れも
前回(第2回『「特例措置」には落とし穴も?将来を見据えた活用上の留意点』)は、事業承継税制の「特例措置」を利用するうえでの留意点について説明しました。「贈与税・相続税がゼロになる」というのは、あくまでも一時的な話で、「いつかは、誰かが税金を納めなければならなくなる」という現実はご理解いただけたのではないでしょうか。
さらにいえば、「特例措置」を利用したとしても、いつかは納めることになる贈与税・相続税の負担が軽くなるわけではありません。むしろ、納税を「先送り」している間に会社の事業規模や資産規模が大きくなって、自社株の評価が上がってしまったら、後継者はより大きな納税負担を負うことになりかねません。これを避けるためには、むしろ、なるべく自社株評価を下げておいて、早めに贈与や相続を済ませてしまうほうが得策となるケースも少なくないのです。
このほかにも「特例措置」には、利用することによって生じるいくつかのデメリットがあります。もともとの事業承継税制では、「承継後5年間、平均8割の雇用を維持すること」という要件を守ることが大きなデメリットになっていましたが、第1回(『自社株の贈与・相続税がゼロに?事業承継税制「特例措置」とは』)で述べたように、「特例措置」には、この要件が守れなくても納税猶予を継続できる救済策が盛り込まれました。「守らなくてもよくなった」といえるほどの要件緩和ではありますが、すべてのケースに適用されるわけではありません。納税猶予と引き換えに、経営状況にかかわらず雇用を維持しなければならなくなるというのは、経営者にとって非常に大きなリスクです。
【初回相談無料!】
この記事に関するご質問・お問い合わせ・ご相談はこちら
また、「特例措置」を利用すると、M&A(企業の合併・買収)を利用した事業承継が困難になるということも、かなり大きなデメリットだといえるでしょう。
「特例措置」を利用して納税猶予を受け続けるためには、贈与を受け、相続した後継者がすべての株式を持ち続けなければなりません。たとえ一部でも売却すれば、その時点で猶予が終わり、贈与税・相続税を納めなければならなくなるのです。
最近では、事業を継続したいけれど後継者がいないといった理由で、M&Aによる事業承継を選択する中小企業が増えています。コア事業に専念するために、その他の事業を売却するといった選択をする企業も少なくありません。「特例措置」を利用すると、納税猶予と引き換えにそうした選択ができなくなり、経営の手足を縛られてしまうのです。
少子・高齢化や、それに伴う人口減少とともに、日本の中小企業を取り巻く経営環境は年を追うごとに厳しくなっています。時代の変化に応じて“生き延びる”ためには様々な策を講じ、しかもそれらを柔軟に変えていく必要がありますが、経営の自由度が失われることによって、それができなくなってしまう恐れがあるわけです。
他の相続人との間で争いが生じるケースとは?

「特例措置」を利用するにあたっては、もうひとつ注意しなければならない問題があります。それは、相続が発生したときに、「特例」を受けられない他の親族との遺産分割をどのように処理するのかという問題です。
相続税は、自社株だけでなく、被相続人(前の経営者)が保有していたすべての財産に対して課税されます。自社株を相続した後継者は「特例措置」によって納税が猶予されても、他の財産を相続した相続人には特例は認められません。そのため、どうしても納税負担の不公平感が出てしまい、相続人同士で揉める原因となりやすいのです。
また、自社株が相続財産のかなりの割合を占める場合、後継者とその他の相続人の間で相続する財産の配分に差が生じてしまいます。その場合、たとえ被相続人が遺言で配分を指示していたとしても、他の相続人から遺留分(相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産)の減殺請求をされる可能性があります。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害している相続人などに対してその侵害額を請求することです。
また、被相続人が遺言を遺していなかった場合、相続財産は法定相続分に応じて相続人が分け合うことになりますが、全相続財産に占める自社株の割合が法定相続分を上回ると、後継者が他の相続人に対して不足分の現金を支払うなど、何からの形で穴埋めをしなければならなくなります。
遺留分減殺請求については、現時点では現物や自社株などの有価証券を分け与えて解決することも可能ですが、2020年4月の民法改正によって、原則的に金銭で侵害額を賠償することが義務付けられるようになります。つまり、後継者は「特例措置」によって相続税の納付を先送りされたとしても、遺留分を侵害された他の相続人に支払うために、多額の現金を用意しなければならなくなるのです。
ただし、これでは後継者にとってかなりの負担となるので、平成20年(2008年)に経営承継円滑化法という民法の特例が認められました。相続人同士の話し合いのもとで、①後継者が相続した自社株については遺留分の算定基礎から除外するか、②自社株の評価については、後継者が贈与を受けた時点の評価額で固定する――という2つが認められるようになりました。あくまでも「相続人同士が合意すれば」という話なので、①については現実的にかなり厳しいと思いますが、②については何とか話し合う余地があるかもしれません。
生前に贈与された自社株を相続財産に持ち戻す場合、相続時よりも贈与を受けた時点のほうが、評価額が低いこともあります。その評価額に固定できれば、遺留分の請求額を減らせるのですから、腹を割って話し合ってみてはどうでしょうか。
ちなみに、相続人同士でしっかりと話し合って、財産配分の合意が得られなければ、相続時に事業承継税制を利用することはできません。相続人同士の争いによって、「特例措置」が受けられなくなるというリスクも考慮しておくべきでしょう。
【初回相談無料!】
この記事に関するご質問・お問い合わせ・ご相談はこちら