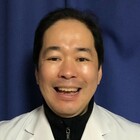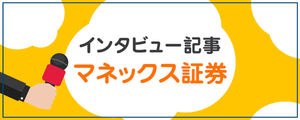(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
楽観的には考えられない「早生まれの子ども」の特性
早生まれの子どもを持つ親は「早生まれの子どもは損をするのではないか……」という思いを持っている人もいます。小さなころは1歳の差がとても大きく出るため、不安があるのでしょう。
児童精神科医としても、そういった不安を持っている保護者に対して、「大きくなれば追いつきますよ」と元気づけたいのですが、そうはいきません。なぜなら、いくつかの研究によって、それは楽観的な考えであることがわかっているからです。
幼稚園、保育園や小学校低学年では、「3月生まれの子ども」と「4月生まれの子ども」にとって、その差(年齢相対効果)はあまりにも大きく見えることでしょう。しかし、小学校高学年ともなれば、その差も縮まってくるように思えるかもしれません。
ところがある研究で、同一学年の最年長者と最年少者のあいだにはおおよそ偏差値2~3の差がみられるほか、最終学歴にも差が生じると結論づけています。また早生まれの子は、学校の教師や友人と良好な関係を結べないと感じるなど「対人関係の苦手意識」が高いそうです。加えて、1~3月生まれの人は4~6月生まれの同学年の人と比べて、30~34歳の所得が4%低いと結論づけています。
他にも、プロサッカーのJリーグ選手は、4月生まれから3月生まれにかけて選手の割合が減少していくことを結論づけています。さらに、プロ野球選手の割合は4~6月生まれと1~3月生まれとで、3倍の差があることを明らかにしており、高校野球甲子園大会出場者でも、同様に生まれ月によって差があることがわかっているのです。
「1年の差」は大きく、大人になっても影響する
早生まれの子どもと遅生まれの子どもの差は、自分自身が周りと比較してしまうことや、周りの友だちや大人が評価してしまうことにより、自尊感情や自己評価が低下するためだと考えられています。「頑張っても勝てない」という経験が積み重なるためです。
反対に、遅生まれの子どもは早生まれの子どもに対して、優位な気持ちや周りからの評価によって、自尊感情や自己評価が高まることが考えられています。
人は他人と比較してしまう生き物であり、それによって喜んだり、落ち込んだりします。児童精神科学では子どもの心診療を行ううえで、子どもの自尊感情や自己評価が今後の人生を送るうえでもっとも重要であると考えられています。
「やればできる」「他人がどう言おうが平気だ」
そういった気持ちがあれば、たいていのことは乗り切れます。「自分はちゃんとした人間だから、自分で考えて行動できる、周りの意見に流されない」と思うことで、問題行動を起こさない自立した大人に育っていくと考えられています。
しかし、自尊感情や自己評価が低ければ、劣等感に苛まされ、チャレンジをしない人になったり、自分自身を責めたり、他人のせいにしてしまったり、周りの意見に流されやすく、問題行動を起こすリスクが高くなるともいわれているのです。