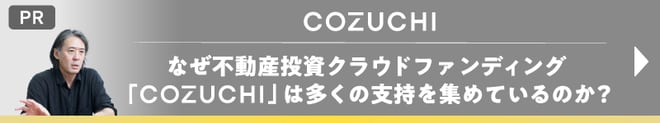高配当株とは?
高配当株とは、配当利回りの高い株式銘柄のことです。東京証券取引所プライム市場の2024年5月時点の単純平均利回りは「2.12%」なので、この水準を大きく上回る「3%以上」の配当利回りであれば、高配当株といえるでしょう。
配当利回りの数値は「1株あたりの年間配当金÷株価×100」の式から算出可能です。たとえば、株価1万円、1株当たりの年間配当が300円の銘柄なら、その配当利回りは「3%」となります。
配当利回りが高い銘柄を保有していると、投資額に対してより大きな配当が得られます。配当所得を重視し、高配当株を積極的にポートフォリオに組み込んでいる投資家も少なくありません。
「高配当株はおすすめしない」と言われることがある理由
配当所得を得るうえで効果的な高配当株ですが、買うべきでないと考える投資家もなかにはいます。ここからは、「高配当株はおすすめしない」と言われることがある理由について解説します。
大きなキャピタルゲインを狙いにくい
キャピタルゲインとは、保有銘柄の株価上昇によって売却時に得られる利益のことです。高配当株は株価が上がりにくく、大きなキャピタルゲインを狙いにくいことが1つ目のデメリットです。
高配当株の企業は成熟期にある場合が多く、グロース株のように急激な成長はあまり期待できません。通常、事業で得た利益は、さらなる成長のために事業に再投資するか、配当で株主に還元するといった使い道があります。すでに成熟している企業は成長できる余地が少ないため、利益を事業拡大よりも株主への配当に多く回し、資本効率の改善を狙う傾向にあるのです。
ただし、高配当株の企業が新規事業に参入した場合や、市場全体が好調である場合などは、大きく株価が上昇する可能性もあります。
キャピタルゲインについて詳しくは下記記事も参考にしてください。
キャピタルゲインとは?インカムゲインとの違いと税金について解説
減配や無配のリスクがある
株式投資の前提として、配当による還元は企業の義務ではなく、あくまでも企業のさじ加減次第です。高配当だからと思い、購入した株が減配や無配になるリスクは常にあるため、気を付けなくてはなりません。
減配や無配によって配当所得が減ると、高配当株を保有しているメリットはあまりなくなります。なぜなら、前項で解説したように、高配当株は大きなキャピタルゲインが狙いにくい傾向にあるためです。
また、配当がなくなるだけでなく、減配や無配によって株価が下がる場合もあります。見込んでいた配当が得られないことに加えて、株価の下落で二重の損失となるため、減配や無配のリスクは事前に考慮しておく必要があるでしょう。
配当金の多寡が資産規模に左右される
配当金の多寡が資産規模に左右されることも、「高配当株はおすすめしない」と言われることがある理由の一つです。株式の保有数が増えるほど配当金も多くなりますが、資産規模が相当大きくないと、配当所得だけで生活するのは難しいでしょう。
たとえば、配当利回り「3%」の銘柄で年間300万円の配当所得を得るためには1億円の資産が必要です。業績悪化による減配や株価下落などのリスクを考慮すると、さらに大きな資産がなければ厳しいといえます。
株価上昇で大きく資産が増える可能性も低く、一方で減配などによる株価の下落リスクがあることも踏まえると、高配当株は少ない資産で購入してもあまりメリットがない銘柄だといえるのです。
高配当株にもメリットはある
さまざまな理由から「おすすめしない」と言われることがある高配当株にも、メリットがないわけではありません。ここでは、高配当株ならではのメリットを2つ紹介します。
定期的な収入が期待できる
高配当株の企業は成熟期にある場合が多く、市場でも一定のシェアを獲得しているため、安定的に利益を生み出しています。高配当株を所有しているだけで、配当金による定期的な収入が期待できることは大きなメリットだといえるでしょう。
年金生活が不安な人などは、高配当株による定期収入が心強く感じられるはずです。
一度購入すれば放置できる
一度購入すれば放置できることも、高配当株の魅力の一つです。成長が見込める企業の株を狙う場合、売買を行なうタイミングなどを適切に見極めなくてはなりません。
一方、高配当株は前述のとおり株価が比較的安定しているため、複雑な投資戦略を練る必要がありません。高配当株は、基本的に大きなキャピタルゲインを狙うのが難しいため、売買タイミングは重視せず、最初の銘柄選びだけ気を付けて購入してしまえば、あとは放置して配当金を受け取るだけにできます。
株式投資のことがよくわからない初心者でも、ポートフォリオに組み込みやすい単純さが高配当株には備わっています。
避けるべき高配当株の特徴
高配当株を買う場合は、いくつかの特徴を備えた銘柄を避けるのが賢明です。ここからは、避けるべき高配当株の特徴を4つ紹介します。
配当性向が100%超
「配当性向」とは、1株当たりの利益に対する配当金の割合のことです。配当性向が100%を超えている場合、企業が得ている利益以上の金額を配当に割いていることになり、持続可能な状態とはいえません。減配や無配のリスクがあるため、高配当だからといって安直に飛びつかないよう注意が必要です。
配当性向が100%を上回るケースとしては、配当金が上がる、業績悪化によって利益が下がるという2つの可能性が考えられます。特に、業績悪化によって配当性向が高まっている場合、減配や無配に加えて株価下落に発展することもあるので要注意です。
一般的に、健全な配当性向は50%以下といわれています。高配当株を選ぶ際は、配当利回りだけでなく、配当性向が健全な数値であるかどうかにも注意を払うことが肝要です。
配当利回りが高すぎる
ほかの銘柄に比べて配当利回りが高すぎる高配当株にも注意が必要です。極端に高い配当を設定している場合、企業は配当のために継続的に利益を上げなければなりません。財務状況が不安定なら減配や無配になるリスクも大きいため、高すぎる配当利回りには気を付けましょう。
配当利回りが高くなる要因は、配当の増加、もしくは株価下落の2つです。配当が増えるのではなく、株価が下がったことで配当利回りが高くなっている場合は、特に注意する必要があります。
配当利回り上昇の背景には経営状態の悪化などがあり、減配や無配につながるリスクが高いためです。前述のとおり、東京証券取引所プライム市場の2024年5月時点の単純平均利回りは「2.12%」です。大きく乖離した配当利回りを設定している銘柄は業績悪化などの可能性も考慮するようにしましょう。
業績悪化が続いている
高配当株のなかには、業績悪化による株価下落を懸念して、高配当を維持している企業もあります。業績悪化が続いている企業の場合、配当に回すだけの利益を得られなくなり、高配当を持続できなくなる可能性が高いです。ある企業の業績の実態を把握したいときは、営業利益や経常利益を確認するとよいでしょう。
配当利回りが高くても、営業利益や経常利益が減少していたり、不安定だったりする企業は避けるのが賢明です。
配当額が急に上がっている
配当額が急に上がっている銘柄は、一時的な高配当株である可能性があるので注意しましょう。というのも、配当額の急増の背景には、特別配当や記念配当が出されている場合があるためです。
こうした臨時の増配は1年限りのもので、翌年になると標準的な配当額に戻ります。配当利回りを見るときは、一時的な増配がないかどうかを確かめることも重要です。
高配当株を選ぶときのポイント
高配当株を選ぶときは、避けるべき銘柄の特徴を押さえつつ、株主資本配当率などに注目しながら比較検討するのがおすすめです。ここからは、高配当株を選ぶときのポイントを3つ紹介します。
複数の業界から選ぶ
1つ目のポイントは、複数の業界から高配当株をピックアップすることです。特定の業界の銘柄に集中すると、株価下落で大きなダメージを負うリスクが大きいでしょう。そのため、金融・運送・商社・インフラのように、複数の業界から銘柄を選んでポートフォリオを組むことが大切です。
どの銘柄にすればよいのかわからないという人は、人気のある投資信託の構成銘柄などを参考にするとよいでしょう。10~20ほどの銘柄を選定し、リスク分散を意識しましょう。
株主資本配当率(DOE)に注目する
2つ目のポイントは、配当性向よりも「株主資本配当率」(DOE)に注目することです。「DOE」(Dividend On Equity)とは、株主資本に対する配当割合を示す指標のことです。配当性向を左右する純利益は期によって変動しますが、株主資本は事業が赤字にならない限り大きく減ることはありません。配当方針に、配当性向ではなく「DOE」を掲げている企業なら、安定的な配当が期待できるでしょう。
安定性が重視される高配当株選びでは、「DOE」に注目することをおすすめします。
累進配当株を狙う
3つ目のポイントは、「累進配当株」を狙うことです。累進配当とは、減配をせずに配当維持もしくは増配を目指す配当政策のことです。累進配当政策を掲げている企業なら減配のリスクは小さく、安定的に配当を得られるでしょう。
累進配当株では企業が配当を下げないと宣言していることから、株価が下落しにくいメリットもあります。ただし、企業の中期経営計画などで累進配当政策を掲げていても、その期間終了後に累進配当を継続する保証はありません。また、企業を取り巻く環境の急激な変化などから企業が反故にする可能性もあります。
信頼性の観点から、累進配当の10年以上の実績があるか、配当性向は「30%以上」であるかといった点を確認しておくとよいでしょう。
まとめ
高配当株は減配や無配のリスクがあり、大きなキャピタルゲインも得にくいことから、気を付けるべき点もある投資対象です。
デメリットを把握したうえで高配当株に魅力を感じる場合は、今回紹介した避けるべき銘柄の特徴を参考にしつつ、DOEなどに注目して銘柄を選ぶとよいでしょう。

【監修者】
名前:齋藤 彩
急性期総合病院において薬剤師として勤めるなか、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。
保有資格:CFP(CertifiedFinancialPlanner)、1級FP技能士、薬剤師免許