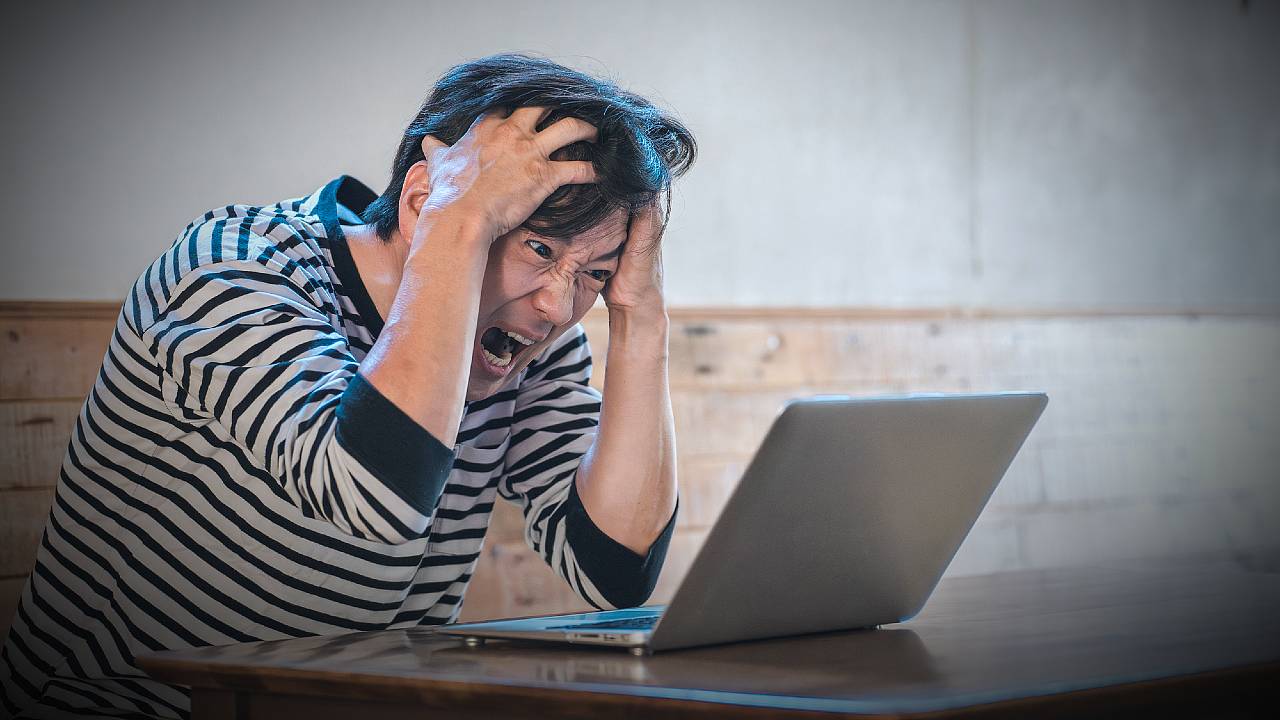親の援助で夢のマイホーム購入を実現できるのは、家計にとっては非常にありがたいことです。しかし、「親と同居」という条件付きの場合、生活面・金銭面のさまざまなメリットと同時に、見過ごせないデメリットも潜んでいます。ルールや距離感を曖昧にしたまま進めてしまうと、かえってトラブルの火種になることも。今回は、そんな「ありがたさの裏側」に潜む現実を、ある40代夫婦の事例をもとに、CFP®の伊藤寛子氏が解説します。

おとなしく賃貸にしておけばよかった…世帯年収700万円・貯蓄300万円の40代夫婦、70代親からの「ありがたい援助」で新築マイホーム購入を実現。歓喜に沸くも、わずか1年で「もう限界」…家庭崩壊危機へ【CFPの助言】
同居前の話し合いと対策が、幸せな同居生活実現のための鍵
マイホーム購入という、大きな金額と決断が必要となる場面での親からの援助はありがたいことですが、せっかくの援助が重荷や火種とならないように、慎重な判断が必要です。
同居後の「想定外」を避けるため、生活・金銭ルールなどについて、まずは夫婦間でしっかり話し合ったうえで親とも話す機会を持ち、同居前に共通のルールや認識を持っておくことが大切です。
また、親からの資金援助を受けて二世帯住宅を建てる際には、税制面でも注意が必要です。住宅取得のために親から受ける援助の額が大きい場合、贈与税の課税対象になる場合があります。「住宅取得等資金の贈与の非課税制度※」などを利用すれば、一定額までは非課税にすることも可能です。
※贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となる制度(参照:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁)
ただし、援助を受けた子の年収が一定以下であること、建物の登記が実際の資金負担割合に沿っていること、などの条件に該当している必要があります。
二世帯住宅には建物の構造として、「完全分離型」と「同居型」がありますが、固定資産税や相続時の評価額に違いがあります。玄関やキッチンも別の「完全分離型」の場合、お互いの生活リズムや距離感が保たれるメリットはありますが、「別の家」と捉えられるため、税制上の優遇が受けられないデメリットもあります。
親からの資金援助や相続を考えるうえで、同居する子どもの他にきょうだいがいる場合は、不公平感が生まれないよう配慮も必要になります。
資金援助や登記、構造の選択など、後々のトラブルや余計な税負担を避けるためにも、事前に税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することが重要です。
二世帯住宅は、家族にとって大きな転機になるものです。資金計画の面でも慎重な判断が必要ですが、今後どのような暮らしをしていきたいのか、介護や相続についてどんな考えを持っているのか、家族で話し合う機会を持つことが、同居のトラブル回避だけでなく、家族が理想とする暮らしや未来を手に入れるための、いいきっかけにもなるでしょう。
伊藤 寛子
ファイナンシャル・プランナー(CFP®)