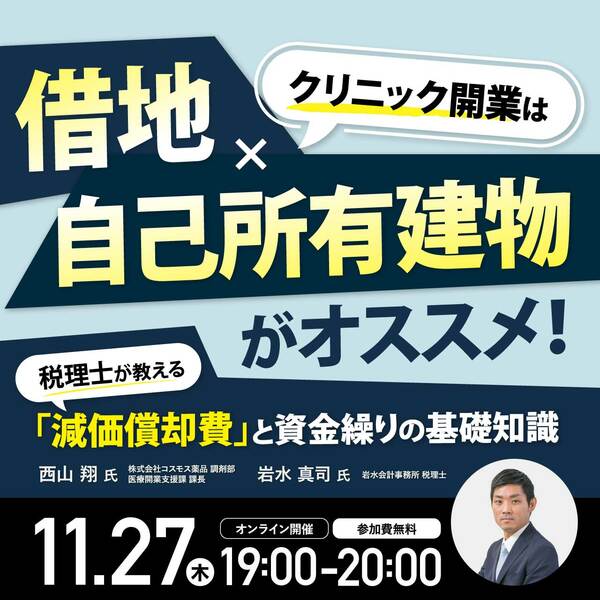そもそも「認定医療法人制度」とはどのようなもの?
「認定医療法人制度」とは、「持ち分あり医療法人」が「持ち分なし医療法人」へ移行する際に、移行計画の認定を受けることでさまざまな優遇措置を受けられる制度です。移行計画の認定制度が実施されるのは平成29年10月1日から令和8年12月31日までとなっています。
すべての医療法人のうち、約60%が持ち分の定めのある医療法人です。この場合、相続が発生した際には出資持分に対し相続税が課税されます。また、持ち分の定めのある医療法人が、持ち分の定めのない医療法人へ移行する(出資者が出資持ち分を放棄する)場合、原則として医療法人に対し贈与税が課税されます。
認定医療法人制度は、一定の要件(認定要件)を充足した認定医療法人が、持ち分の定めのない医療法人に移行する場合に、贈与税を課さないとする制度です。ただし、持ち分の定めのない医療法人へ移行後、6年間は認定要件を充足し続ける必要があります。
認定医療法人制度の適用を受けるには?
認定医療法人制度の適用を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1. 移行計画の内容が社員総会において決議されたものであること
2. 移行計画の有効性及び適切性に疑義がないこと
3. 計画に記載された移行期限が5年を超えないこと
4. 運営に関する要件をすべて満たしており、かつ、移行後6年間は要件を維持し続けること
なお、上記「4. 運営に関する要件…」の具体的な内容は以下の通りです。
①法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと
②役員に対する報酬等が不当に高額とならないような支給基準を定めていること
③株式会社等に対して特別の利益を与えないこと
④遊休財産額は事業にかかる費用の額以下であること
⑤法令違反、帳簿書類の隠ぺい等その他公益に反する事実がないこと
⑥社会保険診療等が全収入の80%を超えていること
⑦自費患者に対する請求額の基準が社会保険診療報酬と同一の基準であること
⑧医療収入が医業費用の150%以内であること
認定医療法人制度のメリット
では、認定医療法人制度の適用を受けた場合のメリットについて確認してみましょう。
◆相続税の納税負担がなくなる
最も大きなメリットは「相続税の納税負担がなくなる」という点です。
認定医療法人となり移行計画を実行すれば、出資持分がなくなるため、出資金に相続税がかかるという事態が起こりません。事業承継の際、高額の相続税が課されて大きな負担となるケースが多くみられますが、同制度の利用によって、そのような事態を避けられるのです。
また、出資者が出資持分を放棄して持分なし医療法人へ切り替わる際、通常であれば医療法人に贈与税が課されます。しかし、認定医療法人となれば、持分なし医療法人へ移行する際に発生する贈与税が非課税となります。
このように、認定医療法人になると、法人形態の切り替え時、および事業承継の際の税負担がなくなります。
なお、医療法人の出資者が亡くなったときにまだ移行がすんでいなくても、相続税の申告期限の時点で認定医療法人であれば、対象の相続税は猶予されます。
その後、持分なし医療法人への移行が完了すれば、猶予されていた相続税はそのまま免除となるしくみです。
◆出資者から払戻請求を受ける恐れがなくなる
持分なし医療法人へ移行すれば、出資者から払戻請求を受ける恐れがなくなります。
仮に、医療法人の設立時にAさんとBさんがそれぞれ1,000万円ずつ出資したとします。この場合、Aさん・Bさんそれぞれの出資持分は50%です。
そして、医療法人の設立後利益が蓄積され続け、医療法人の純資産が1億円になったと仮定しましょう。Aさん・Bさんはともに出資持分50%を有するため、医療法人の純資産の50%である5,000万円の請求権を有します。
もしこの状態でAさんが払戻請求を実施した場合、医療法人は5,000万円という高額の払い戻しをする義務が生じてしまいます。
持分なし医療法人へ移行すれば「出資持分」という概念がなくなるため、払戻請求が行われる懸念もありません。
◆同族経営を継続できる
認定医療法人制度において、社員や役員の構成に非同族を求める要件はありません。そのため、同族経営を維持しつつも、出資持分に対して相続税が課税される事態を避けられます。
持分を放棄しても社員としての議決権が失われるわけではないため、運営権限がなくなるという懸念は不要です。
認定医療法人制度のデメリット
一方、認定医療法人制度の適用を受けた場合のデメリットについて確認してみましょう。
◆移行後6年間は運営状況を厚生労働省へ報告する義務がある
認定医療法人制度を利用する場合、移行後6年間は運営状況を厚生労働省へ報告する義務があります。
同制度は、持分なし医療法人への移行計画について厚生労働省からの認定を受けた場合に利用できる制度です。そのため、移行が計画通りに行われたか、移行後の運営に計画との大きな相違がないかのチェックを受ける必要があります。
運営状況の報告における必要書類の数が多く、報告の手間がかかる点は大きなデメリットです。
◆医療法人に多額の剰余金があっても請求が不可能
認定医療法人制度を利用して持分なし医療法人への移行を行ったあと、医療法人に多額の剰余金があっても請求は不可能です。
持分なし医療法人とは、名前の通り出資者が持分を持たない医療法人です。そのため、移行計画に沿って持分なし医療法人へ移行したあと、出資者の持分はすべて失われます。
同制度を利用するメリットのひとつとして、「出資者から払戻請求を受ける恐れがなくなる」を挙げました。大きな払い戻しをする必要性がなくなるのはメリットですが、同時に、出資者の権利が失われる点はデメリットともいえるでしょう。
◆残余財産分配請求権がなくなる
持分なし医療法人への移行後は、残余財産分配請求権も失われます。
医療法人における残余財産分配請求権とは、医療法人が解散する際に法人が有する資産の分配を受ける権利であり、通常、出資持分に応じて分配が行われます。しかし、移行後は出資持分を放棄することになるため、残余財産分配請求権もありません。
もし多額の資産を持つ医療法人が解散となった場合、残余財産は国等に帰属となります。
将来に経営リスクを残さないため、移行の検討も選択肢
現状においては、持分あり医療法人の数が多く、認定医療法人制度の活用が進んでいるとはいいがたい状況です。これは制度を活用するメリット以上に、持分を放棄することや制度を活用することへのデメリットが医療業界で広まっていることが大きな要因とされています。また、制度そのものが複雑で、検討すらできていない法人も一定数あります。
ただし、将来の相続税・贈与税などの税制上のメリットを考慮した場合、将来、事業承継の時期が到来したとき、納税資金等に余裕がある保証は必ずしもありません。
将来に経営リスクを残さないためにも、資金余力の程度にかかわらず、一度、顧問税理士等に相談し、持分なし医療法人への移行は検討されてみてはいかがでしょうか。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所 税理士/CFP