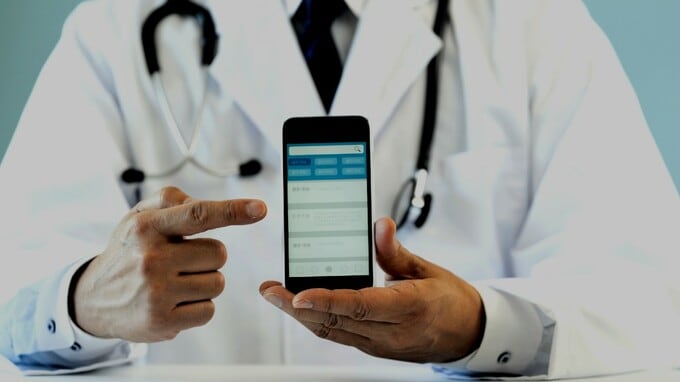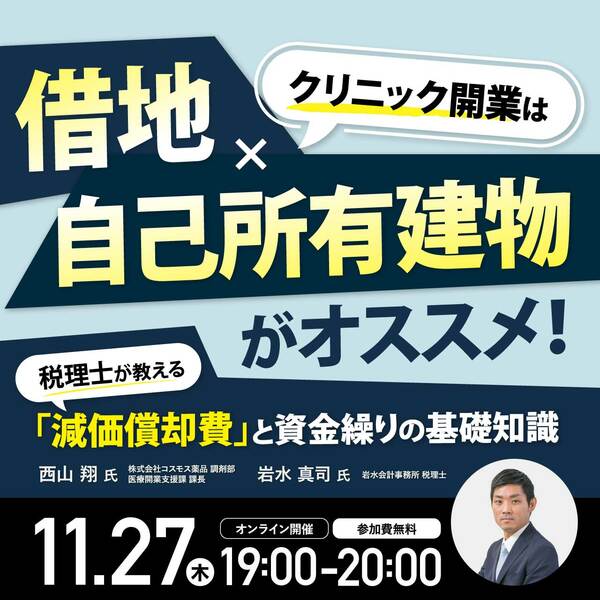今回の処分の概要
ニュースでも広く内容について報道されましたが、今回の事案について簡潔にポイントをまとめると、
●処分を受けたXクリニックは、インフルエンザワクチンの接種を行っていた
●来院した患者に、XクリニックのGoogleマップ上のクチコミに☆5又は☆4の投稿をすることを条件に接種費用を割り引くことを伝えた
●その結果、来院した複数名の患者が、Xクリニックのクチコミを投稿した
●投稿したクチコミのうち、☆5の投稿45件について、ステマであると判断された
という内容になっています。
今回のステマ規制は、内閣府によって告示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)され、同年10月より施行された新しい規制でした。そして、その新しい規制の最初の処分の対象となった企業が今回のクリニックです。
Web広告を行っている業界は非常に多岐に渡るなか、初の処分対象者が医療機関・クリニックになったことは、クリニック経営者にとっても非常にショッキングであり、不安になっている経営者も多いと思われます。
このような処分が下された背景
そもそも、ステルスマーケティングとは、広告・宣伝であるにもかかわらず、消費者に対して広告・宣伝であることを隠し気づかれないように行われる広告・宣伝行為のことをいいます。
そのため、今回処分を受けた対象となった投稿についても、「Xが行った広告・宣伝であるのに、他の患者に対してそれがわからないように行われたものである」と認定されたことに注意が必要です。すなわち、患者が行ったクチコミは「患者自身がクリニックの感想を任意にレビューしたもの」ではなく、「実際にはクリニック自身が行った広告宣伝である」という認定になったということです。
ここで注意をしなければいけないのは、
●優良誤認表示
→「待ち時間なくワクチン接種ができた」「看護師の対応が丁寧だった」など、サービスがほかのクリニックよりよかったという内容
●有利誤認表示
→「価格がほかのクリニックより安かった」といった、価格や取引条件が他のクリニックよりよかったという内容
で処分されたわけではない、ということです。すなわち、患者が☆5のレビューをしたことによって、処分されたということではありません。
非常にややこしいのですが、クリニック側にて「患者に対して、☆5または☆4投稿をしてもらうことを条件に」、「費用の割引をすることを伝え」、「その通りの投稿を患者が行った」という経緯からすれば、当該投稿は「事業者が自らのサービスについて行った表示であり、それは一般消費者から見れば判別がむずかしいもの」と認定された、というしくみになっています。
よりわかりやすく、砕けた言い方をすれば、対価をもらったうえで具体的な投稿の内容まで指示されて行った当該投稿は、「もはや患者による任意のクチコミではなく、クリニック自身にて行われた広告と何ら変わらないものであるといえ、他の患者から見たときに、患者の任意のクチコミかクリニックの広告なのかわからない」ものだと認定され、ステマ規制の対象となった、ということです。
接種費用の割引をしなければよかったのか、☆5または☆4と指定したことが悪かったのかという議論は、関係がないものではありませんが、本質ではないという点に注意が必要です。
クリニックが取るべき対応策はあるのか
では、このようなステマ規制に対して、クリニックが取るべき対策はあるのでしょうか?
当然、まだ始まったばかりの制度であり、処分例が積み重なっているものではないことから、先例に倣った対策が考えられず、それがより対策をむずかしくしているといえます。もっとも、ステマ規制に係る内閣府告示等から、適正な広告となるように気を配ることは可能ですので、その点から対策をするべきだといえます。
①事業者による広告の場合
まず、事業者による広告の場合、「広告である」ということが一般の患者にとってわかりやすいことが重要です。SNSのハッシュタグ等で、「#PR」と付されているものを見たことがあるかと思いますが、これはその一例です。広告であることの表示はもちろん、表示自体も小さい・視認しにくいといったことがないよう工夫をする必要があります。
②第三者によるクチコミの場合
この場合は、クリニックにとって高い広告効果を見込める一方、Xと同様の処分がされないよう、とくに注意が必要です。患者による任意的なクチコミの投稿と評価されることが必要であり、クリニック側からの働きかけは行いにくいことが現状です。
あくまでも「他の患者様の参考になるよう、インターネット上でのクチコミの投稿をお願いします」という程度に留め、
●投稿を積極的に行ってもらうための利益の供与
●投稿内容の具体的な指示や要望
●クリニック内で職員が見ている状況での投稿要望
を行わないことが重要です。
③外部専門家との連携
ステマ規制はまだまだ新しい規制であり、十分な処分例の蓄積がなく、ボーダーラインが曖昧な現状です。そのため、外部の専門家を招き、クリニックとしてだけではなく、クリニック職員に対しても、広告規制に関する知識を高め、管理体制を構築することが、適切なリスクマネジメントになるといえます。
これまでと同じ広告手法では、手痛い処分のリスクも…
今回、Xに対してなされた処分は、医療業界・クリニックに対して非常に大きな衝撃を与えたといえます。ステマ規制は、消費者保護の観点から強く要請されるものであり、なんら注意を払うことなくこれまでの広告と同じ方法を行っていると、手痛い処分を受ける可能性も否定できません。
処分の内容について正しく知り、しっかりと対策を講じることが必要であることは間違いなく、専門家への相談を含めて検討することが重要です。
寺田 健郎
弁護士 弁護士法人山村法律事務所